|
6. 認証基準以外のチェック項目
認証基準以外のチェック項目は、認証の基準とはしないが、グリーン経営推進チェックリストで定めている到達度を確認する。
審査員用チェックリストでは、認証基準以外のチェック項目を、単線枠内に明朝体で表している。
〔例〕認証基準と認証基準以外のチェック項目
| (拡大画面:32KB) |
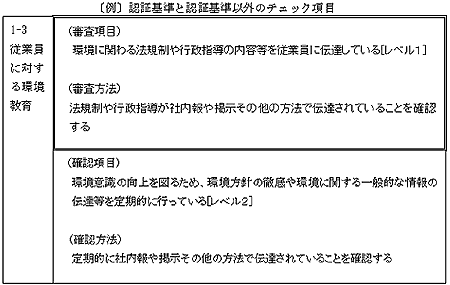 |
(1)認証基準(レベル1)を満たしているかどうかを審査する(二重線枠内)。
(2)認証基準に対して適合している場合には、審査員用チェックリストの適の欄に記録する。
(3)次にグリーン経営推進チェックリストのレベル2を満たしているかどうかを確認する(単線枠内)。
(4)レベル2まで到達している場合は、審査員用チェックリストの適の欄に記録する。
(5)レベル2を満たしていなければ、審査員用チェックリストの不の欄に記録する。
(6)いずれの場合も認証基準(二重線枠内)はレベル1で設定されているので、レベル1を満たしていれば、当該の小項目は適合と判断することになる。
(1)審査前会議
審査の開始にあたり下記の内容で、審査前会議を開催する。事業者側の責任者(必ずしも経営者であることは要さない)及び連絡担当者の出席を会議前に依頼すること。
1)審査の時間割
2)審査確認項目の説明
3)審査の進め方の説明
(1)「審査員用チェックリスト」に確認事項等を記入する旨の説明
(2)審査方式であるサンプリング審査の意味
4)審査結果の取扱いの説明
(1)不適合事項の扱い方、是正処置の確認方法
(2)審査結果の判定と審査員の役割
5)審査後会議の開催予定
6)その他
(1)審査員と事業者側の面談者は、対等な関係であることを説明
(2)機密保持、守秘義務の宣言
(3)案内者の依頼、連絡担当者との連絡、調整方法
(2)実地審査の方法
| 1) |
審査は、質疑応答を交えて「審査員用チェックリスト」の審査項目ごとに確認、評価を行い、問題点(不適合事項)を検出する。 |
| 2) |
審査はサンプリング方式で確認する。これは、事業者の規模に応じて適切な文書、記録類等を抽出して確認する方式である。 |
| (1) |
サンプルは、原則として審査員が自ら選択すること。ただし、グリーン経営取組み開始時期が最近のため適用事例が少ない場合は、事業者側が用意するサンプルで確認することもやむを得ない。その場合、評価結果の客観性に疑義が生じないことを、別の観点から補完的に確認する。 |
| (2) |
サンプルは直近のものに限定せずに、出来る限り時系列的に抽出する。 |
(3)実地審査の進め方
| 1) |
「審査員用チェックリスト」に従って、時間を守り審査を進める。ただし、予想外の事情により審査の進捗に支障を生じそうになった場合は、事業者側の責任者と調整して柔軟に対処すること。 |
| 2) |
審査項目の確認、評価に際しては客観性を重視して、審査員の誤解や理解不足等による独断に陥らないよう注意すること。 |
| 3) |
確認の証拠となるものは、面談者が口頭で説明した事項(次項参照)、審査員が確認、観察した文書、記録、現物であり、これらを「審査員用チェックリスト」の“客観的証拠”欄に記録する。なお、文書及び記録を閲覧する場合は、あらかじめ事業者側の許可を求める。事業者から拒否された文書や記録の開示を求めることは禁止する。 |
| 4) |
一人の面談者から聴き取りした口頭情報に対しては、客観性を持たせるために他の面談者に再確認するか、もしくは文書、記録、現場実態等によって確認する。 |
| 5) |
審査時の質疑応答が、コンサルティングにならないこと。特に、不適合事項への対応方法を一方的に強制しないこと。 |
| 6) |
審査は尋問形式にならないように、対等の関係で部門責任者、担当者に接すること。 |
| 7) |
事業者の就業ルールを遵守して、所定の休憩時間は出来る限り妨げないよう時間管理を行うこと。 |
| 8) |
予定時間に遅れることが予測される場合は、責任者にあらかじめ了解を得ること。 |
(4)不適合事項
1)不適合事項とは、審査員が認証基準に照らし問題として検出したことで、事業者側の責任者と合意が得られた事項とする。
2)具体的には、認証基準に規定した取組が欠落している、もしくは審査終了までに客観的証拠により確認できない等が該当する。
3)不適合事項については、事業者側が問題点を誤解することなく的確な処置方法が検討できることが重要であり、後から疑義が生じないように、検出された部門での事実確認と、事業者側の責任者に対して十分説明すること。
(5)不適合事項の事業者への報告
| 1) |
審査員は事業者の責任者に不適合事項を報告するに際し、認証基準をクリヤーするために何らかの対応の必要性があることを説明する。 |
| 2) |
不適合事項については、問題の程度に応じた是正処置の方向を、事業者側の責任者に確認する。この際、審査員からの一方的な指摘ではなく、事業者側が理解しやいように是正処置の方向性を示したり、有効な情報をプラスして説明する。 |
| 3) |
審査後会議では、不適合事項の是正処置期限を、事業者側の責任者と確認する。 |
(6)不適合と審査の判定
| 1) |
不適合事項のない場合 |
| |
エコモ財団に合格の旨、報告することになる。 |
| 2) |
不適合事項のある場合 |
| |
(1)不適合事項に対する是正処置が実施され、処置が適切に完了したことを審査員が後日確認した上で合格と判定される。 |
| |
(2)是正処置期限内に是正処置が提示されなければ不登録となる。 |
(7)「不適合報告書兼是正処置報告書」の作成
| 1) |
審査員は、審査後会議までに「不適合報告書兼是正処置報告書」を作成する。 |
| 2) |
「不適合報告書兼是正処置報告書」の左欄“不適合の内容”には、審査員が検出した不適合事項を記入する。 |
| 3) |
事業者には、不適合事項の是正処置を完了(是正計画書などの作成だけでは完了したとはみなさない)した後、「不適合報告書兼是正処置報告書」右側の“是正処置の内容”欄に当該の処置を記入し、審査課へ提出してもらうことを説明する。その際、
| (1) |
所定の欄に記入しきれない場合は、別紙に記入して良いこと |
| (2) |
是正処置を裏づける資料の写しや写真を添付することを説明する。 |
|
| 4) |
審査後会議で、事業者側の責任者に「不適合報告書兼是正処置報告書」を手交し、内容について合意を得た後、双方で署名及び押印を行い、審査員は写しを持ち帰る。 |
(8)エコモ財団への是正報告日程の確認
1)審査後会議で、不適合事項に対する是正処置を記述した「不適合報告書兼是正処置報告書」がいつまでにエコモ財団へ提出出来るか、事業者側の責任者に確認する。
2)それを受けて、審査員として是正処置内容をチェック出来る時期を、事業者側に説明する。
(9)「実地審査報告書」の作成
1)審査員は、審査後会議までに「実地審査報告書」を作成する。
2)「実地審査報告書」の目的は、事業者側に審査概要(不適合の有無及び件数)と登録推薦を公式に報告することである。
3)「実地審査報告書」には事業者側の責任者の署名と、審査員が署名する。
(10)審査後会議
1)審査員は事業者側出席者と審査終了後、会議を実施する。出席者は事業者側の判断に委ねるが、予め責任者の出席は依頼しておく。
2)審査後会議の内容
| (1) |
実地審査の実績
当初の計画から大幅に変更をした場合は、お詫びと協力にお礼を述べる。 |
| (2) |
不適合事項の説明 |
| (3) |
不適合事項の是正処置完了予定の確認 |
| (4) |
「不適合報告書兼是正処置報告書」の取扱い説明 |
| (5) |
審査結果の評価、登録推薦の上申内容 |
| (6) |
謝辞。審査員のコメントがあれば述べる |
| (7) |
審査終了の宣言 |
(11)「実地審査報告書」の確認
| 1) |
審査員は、「実地審査報告書」に署名を行い、事業者側の責任者の確認と承認を求め署名を依頼する。 |
| 2) |
双方が署名した「実地審査報告書」は、公式な文書として写しを事業者におき、原本は審査員が持ち帰る。 |
| 3) |
事業者と審査員の見解が分かれて事業者側の承認が得られない場合は、審査員のみが署名して、事業者側の見解を説明する資料の提出を依頼する。その判定は審査課が行う。 |
|