| (拡大画面:40KB) |
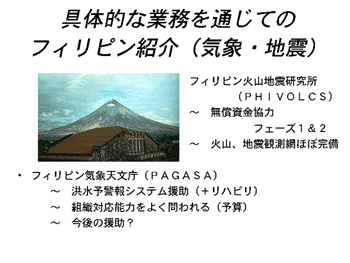 |
それから気象・地震ということですけれども、これが非常にきれいな山なんですが、マヨン火山ということで、つい先ごろまで噴火していましたけれども、富士山のような非常にきれいな山です。あるいはご存じのピナツボ火山というのもありますけれども、こういう火山被害というのがあります。それは地震もあるということで、無償資金協力をやってきて、現在ほぼ完備しつつあるという状況で、もしかしたら日本よりもいいという状況かもしれない。ただし、これはあくまでデータ観測の領域、あるいは警報の域に過ぎませんので、防災という観点はすべてをバランスよくカバーしないといけませんので、ほかの側がついてこないといけない。そういう意味ではほかの側をどういうふうにやっていくかというのは今後の問題だと思います。
それから気象ですね、PAGASAということで、洪水予警報ということで、水位を観測して通信システムを使って送って、危ないよとかいうシステムですけれども、そういうシステムをやったりしているわけなんですが、最も大事な天気のところがまだまだ弱いものですから、これを今何とかしなきゃいけないと言っているんですが、PAGASAというと、過去にやったやつもどうもうまく動かないものですから、組織対応能力を問われてしまうんですが、これは単に方便でありまして、要するに目的はここなんです。カウンターパートファンドをPAGASAが積めないというのが一番大きな問題でして、ここをどういうふうにしていかなきゃいけないか。これは考えていかなきゃいけないと思います。
| (拡大画面:391KB) |
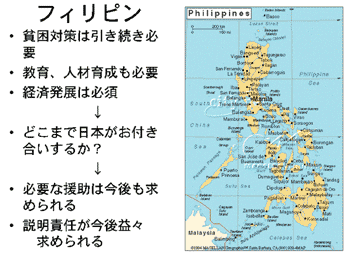 |
ちょっと時間をオーバーしてしまいましたけれども、フィリピンということで、貧困対策といいますか、現地で暮らしている感覚では金持ちもものすごいたくさんいますけれども、貧しい人は貧しいと。本来であれば金持ちがもうちょっと国を考えて、国に投資して、国を整備していかないといけないんですけれども、なかなかそこまでいかない。教育を受けてない人もまだまだいます。従ってこういうところも非常に重要でしょう。持続的経済発展も重要です。どこまでおつき合いするか必ず問われる。
従って、日本としては必要な援助は今後もやっていかざるを得ませんが、一番求められているのはここの説明責任が今後ますます求められてくるということで、これはどの国でも同じだと思いますけれども、勝手な援助をしたり、勝手な調査をしたり、勝手なものをつくっちゃうと後で何を言われるかわからないということだと思います。ただ、そうはいっても予算削減なるも、やっぱり我が国としてはこういう援助というのはやっていくべきだとは思います。
| (拡大画面:19KB) |
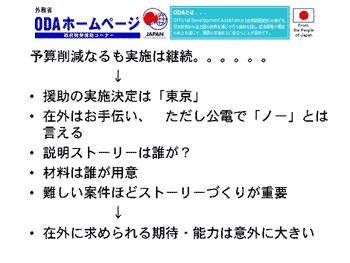 |
援助といえば当然のことながら実施決定は東京、ヘッドウォーターですから東京がやるわけなんです。在外はあくまでお手伝い、メッセンジャーといってしまえばそこまでなんですが、ただし、在外の大きな武器はノーと言える。イエスとは言えないんですね、在外は。ただ、ノーと言っても無理やりやれと言われる命令が上から来る場合もありますので、必ずしもこれは正解ではないですが、基本的にノーと言えるんです。情報公開がこれだけ叫ばれている世の中ですから、ノーと言った公電がもし世の中に出たら大変なことになると思います。そういう意味で東京と在外との関係。
それから例えば東京で援助の実施決定をやるわけなんですけれども、説明ストーリーはだれがつくるんですか。現地のことを一番わかっているのはだれなんですか。こうなるとどうしてもやっぱり現地になってしまうんです。そうすると、材料は現地が用意。じゃあ、どういうふうにやっていくのか。結局ストーリーづくりをやるしかないんですけれども、難しい案件ほどストーリーづくりは重要になってきます。在外に求められる期待・能力というのは意外に大きい。ただ遊んでいるだけではないということであります。
それから、最後ですけれども、大使館業務ということで、大使館というのは外務省の事務所ではなくて、日本政府の在外事務所でありますので、この点をご承知いただければと思います。従いまして利用しない手はないということであります。出張前には連絡先をメモとありますけれども、とにかく頻繁に現地大使館の担当官にコンタクトしていただければ担当官のほうでそれなりに無理はきくと思います。ただ、その前に、例えば何かのプロジェクトで何かの情報が欲しいと急に言われても、ちょっとすぐには対応困難ですので、情報は前広にいただけると、それなりにと思います。
それから最後の手段は公電とありますが、やはり公電というのはこれだけEメールが発達した世の中でも、もしかしたらなくなるのかもしれないけれども、当面は多分なくならないと思います。文章というのはやはり重要なんです。公電を出すか、出さないか。出せるか出せないかのほうが重要かもしれませんけれども、これをやはりもっと考えていかなきやいけない。
例えばプロジェクトを動かそうと思ったら、公電があるというのは絶対条件ですので、そういう意味で日ごろより環境作り。環境作りというのは書記官の大使館内での振舞い方であるとか、そういう環境作り。あるいはJICAの専門家も含めプロジェクトを推進しているグループが普段どういうふうに評価されているか。そういう環境作りというのが全部かかわってくるというふうなところだと思います。
準備時間が短くて、ちょっとはしょった説明で申しわけありませんでしたけれども、これで説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
【男竹理事】 ありがとうございました。予定の時間を大分オーバーして、全分野について詳細なご説明を簡潔にしていただいて、貴重な情報をいただきました。
二、三ご質問があればお受けしたいと思います。手を挙げていただければ、所属とお名前をおっしゃっていただければ。ここにご説明のあったこと、あるいはなかったこと、どうぞ。
【質問1】 トーニチコンサルタントの矢島といいますけれども、バタンガス港のところの説明で、NGOの関与とありましたけれども、このNGOというのは日本のNGOなんですか、それとも現地側のNGOなんですか。
【松永講師】 両方です。現地の住民を代表しているNGOのような方がおられます。この方は現地を代表していろいろ政府に文句を言ったり、具体的に裁判を起こしています。
ただ、それだけでは問題ではなくて、やはり日本のNGOがそこに関与してくるというのが非常に大きな問題になっていまして、すべてを理解して一言言ってくださるんだったらわかるんですけれども、一面しか見ていないところで一言言ってくれるものですから、非常に対応が難しい面がございます。
【男竹理事】 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。
本日は第1回のセミナーでございましたが、今まで毎年何回かセミナーを実施してまいりましたが、本日は参加者が最高でございまして、新記録です。それほどフィリピンにご関心のある方が多いということの表れであり、また松永書記官が現地で大変ご活躍されて、ここにおられる方は多分半数以上の方が書記官にお世話になったんじゃないかなと。この後、懇談会を予定しておりますので、お時間のある方はごゆっくり個人的なご質問、個別の質問などをしていただければと思います。では、これで終わります。拍手をお願いいたします。(拍手)
―了―
|