|
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないよう布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0(電路の布設)
(a)機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1)1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0〈1〉参照)
図258.0〈1〉
(2)束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(ii)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。
(iii)図258.0〈2〉に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては、垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルを設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。
図258.0〈2〉
備考 水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。
(b)(a)に掲げる方法のほか延焼を防止することが、(a)に規定する方法と同等以上の効力を有する方法と認められた場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあっては、この限りでない。
(c)附属書〔3〕耐延焼性試験
1 ケーブルの耐延焼性試験については、本附属書による。
2 試料は、対象ケーブルの種類に応じ、表1の区分による。
表1 試料
区
分 |
試料 |
|
| がい装、防食層の有無 |
ケーブルの種類 |
対象ケーブル |
| I |
がい装無 |
防食層無 |
(a)660V耐延焼性3心EPゴム絶縁
ビニルシースケーブル 14mm |
全線種 |
(b)660V耐延焼性多心EPゴム絶縁
ビニルシースケーブル 7心 |
(c)250V耐延焼性電話用ビニル絶縁
ビニルシースケーブル 7対 |
| II |
がい装有 |
防食層無 |
(a)660V耐延焼性3心EPゴム絶縁
ビニルシースあじろがい装
ケーブル 14mm |
がい装付きの全線種及びがい装の上に防食層を施した全線種 |
(b)660V耐延焼性多心EPゴム絶縁
ビニルシースあじろがい装
ケーブル 7心 |
(c)250V耐延焼性電話用ビニル絶縁
ビニルシースあじろがい装
ケーブル 7対 |
| III |
がい装有 |
防食層有 |
(a)660V耐延焼性3心EPゴム絶縁
ビニルシースあじろがい装
ビニル防食ケーブル 14mm |
がい装の上に防食層を施した全線種 |
(b)660V耐延焼性多心EPゴム絶縁
ビニルシースあじろがい装
ビニル防食ケーブル 7心 |
(c)250V耐延焼性電話用ビニル絶縁
ビニルシースあじろがい装
ビニル防食ケーブル 7対 |
|
3 試験装置
(1)燃焼試験室は、ケーブルの燃焼試験時にケーブルの燃焼を助長させないような自然換気に近い室又は燃焼用バーナーの火炎が不安定にならないような強制換気を行った室とする。
(2)試験は垂直トレイ試験とし、また、垂直トレイは図1に示すような高さ約 2,400mm、幅約 300mm、奥行き約 75mmの金属製オープントレイとする。この場合において、トレイは、燃焼に影響を与えないような適当な支持物で垂直に固定する。
図1 垂直トレイ及びケーブル取付形状(単位:mm)
(3)バーナーは、本試験に適当なリボンガスバーナーとする。この場合において、寸法は図2に示すものとする。
図2 リボンガスバーナーの形状
(4)燃焼ガスは、主組成分であるプロパンとプロピレンの配合量が95%(モル%)以上の液化石油ガス(LPガス)とする。
(5)燃焼ガスは、空気と混合し燃焼させる方式とし、配管の1例を図3に示す(ガスミキサーは、本試験に適当なものであること。)。
(6)図3に示すようにLPガスを燃焼させる場合においては、炎の長さはバーナー口より炎にそって測定したとき約 380mm、炎の温度はバーナー口より約75mm離れた点で約815℃とする。この場合において、燃焼熱量は、燃焼試験中に消費したLPガスの容積(mm3)を既算流量計等で計量し、この値に単位発熱量を乗じ1時間当たりの量に換算した場合17,500kcal(70,000BTU)以上あるものとする。
なお、単位発熱量は、22,000Kcal(88,000BTU)/mm3(20℃) として計算する。
| (拡大画面:8MB) |
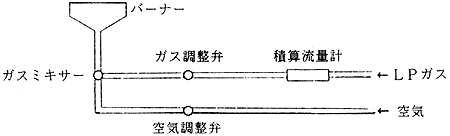 |
図3 燃焼源の配置
(7)バーナーは、バーナー口を試料前面から約75mm離して設置する。
4 試料の取付け
(1)ケーブルを約 2.4mに切断し、ケーブル6条をトレイの中央部にケーブル外径の1/2 の間隔をもって1列に配列する(図1参照)。
(2)ケーブルは、ケーブルトレイに所定の間隔が得られるように適当なバインド線で固定する。
5 試験方法
(1)バーナーの炎を所定の条件に調整した後、ケーブルの所定の位置に当て、20分間燃焼を続ける。
(2)20分経過後バーナーの燃焼を停止し、試料の燃焼が自然に停止するまで放置する。
(3)燃焼によるケーブルの被害が試料の最上端まで達していないかどうか調べる。この場合においては、ケーブルのシース及び各線心について被害状況を調査するものとする。
|