|
5.2.4 ケーブルの結束
がい装又はシースが切り取られたケーブルを結束して盤内の端子盤に導き、端子首部に無理な力がかからないようにケーブル相互又は構造物にビニルバンド又はビニルひもで固縛する。ロック付のナイロンバンドを使用すると作業が容易で効率を上げることができる。
| (拡大画面:42KB) |
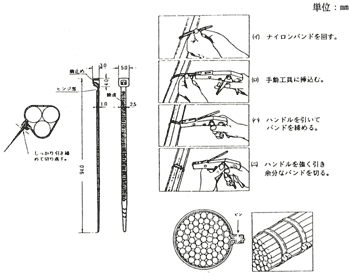 |
図5.28 ロック付の樹脂性バンドによる結束
5.2.5 結線の具体例
結線は、結線図に指示されたとおり正確に行い、端子締付けねじに適合した工具で確実に締付けなければならない。
心線端に圧着端子などを取付けないで、導体をじかに端子に接続する場合には、導体挿入長が不十分で接触不良とならないようにし、複数の心線を同一端子に挿入する場合には、導体締付けが不均等になりやすいので、導体をより合わせて挿入しなければならない。
端子締付ねじは、ばね座金、舌付座金などで緩み止めをする。大形端子では、ダブルナットや緩み止め効果を有する特殊ナットを使用している例もあり、小形端子では、弾性材によって端子が緩み止め機能を有しているものもある。一連の結線を終了したら、接続の誤りがないか結線図と照合チェックし、ねじ部の増締めを行って結線の完壁を期する。以下に各機器における結線の具体例を示す。
(1)配電盤
| (拡大画面:50KB) |
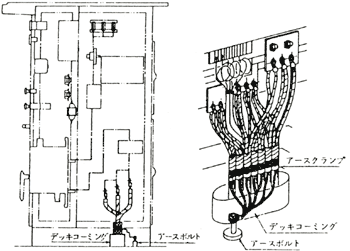 |
図5.29 発電機用ケーブルの結線
| (拡大画面:57KB) |
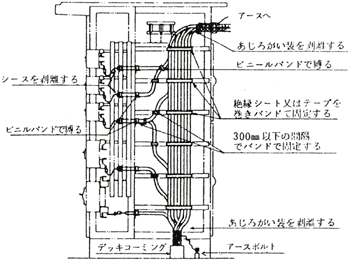 |
図5.30 給電用ケーブルの結線
(2)区分電盤
| (拡大画面:30KB) |
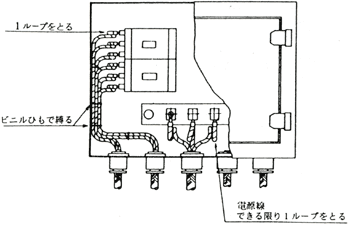 |
図5.31 区分電盤内の結線
(3)制御盤
| (拡大画面:65KB) |
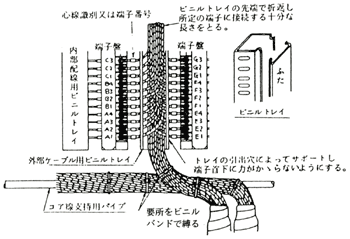 |
図5.32 制御盤内の結線(1)
図5.33 制御盤内の結線(2)
図5.34 多心線の端子への導入の線さばき
制御盤内へシールド線を導入する場合は、他のケーブルの処理と異なり、盤内での静電結合による電気ノイズを低減するため、端子近くまでケーブルをそのまま導入し、導体の裸部分とシールド線はできるだけ短くなるように処理し結線する。
図5.35 シールド線の結線
自動化機器などの計測回路のケーブルは、線端処理後盤内に長く配線されると、盤内の他の電気回路の影響を受けノイズを発生することがあるので、十分により合わせておく。
図5.36 計測用ケーブルの線さばき
|