|
5. 結線
5.1 線端処理の方法
5.1.1 一般
線端処理の方法は、機器の導入口の種別により処理寸法を決定し、ケーブル端のがい装、シース、介在物などを除去し、心線を分離して、色別、心線番号、記号等により心線区別を明確にし、導体先端に端子を付ける。
シールド編組を持つケーブルの場合には、シールド線を引き出して絶縁被覆を施しその先端に端子を取付ける。これらの処理には、ナイフ、ハグラ、ニッパなどを使用するが、絶縁物に切り込みを入れないよう注意深く工事を行う。特殊ケーブルを除き一般に直角に段むきを行う。(図5.1参照)
ビニル防食ケーブルの場合は、図5.2に示すように処理する。
| (拡大画面:36KB) |
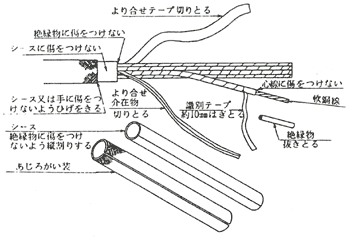 |
図5.1 一般的な線端処理の例
図5.2 ビニル防食ケーブル
5.1.2 動力用ケーブル
動力用ケーブルの線端処理はケーブルの導入口から端子に至るまでの距離を十分に測定し、各機器ごとにケーブル導体に無理が加わらないよう、また、作業が容易なように線端さばき長を決める。
配電盤内導入ケーブルの場合は、盤内導入経路を考慮し、シース部の長さを決定する。絶縁体が導電部又は接地金属部に触れるおそれのある場合は、全長にわたりビニルチューブに入れるか、又は粘着ビニルテープ(色別)で半重ね1回巻きを行い、終端部は2〜3回重ね巻きする。
| (拡大画面:31KB) |
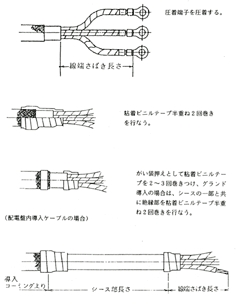 |
図5.3 動力用ケーブルの線端処理
| 導体サイズ(mm2) |
圧着中心のずれ△(mm) |
導体突き出し長さL1(mm) |
端子筒頂部と絶縁被覆との間の裸導体長さL2(mm) |
| 1.5〜6 |
±1.0 |
0.5〜2 |
0〜1 |
| 10〜35 |
±1.5 |
1〜2 |
0〜2 |
| 50〜95 |
±2.0 |
2〜3 |
0〜3 |
| 120〜300 |
±+3.0 |
3〜4 |
0〜4 |
|
| 注1: |
本表は、JEM−TR162−93(圧着端子適用指針)を基準としたものである。 |
| 注2: |
B寸法は、JISC2805−91の付表1及び付表2のE寸法による。 |
| 注3: |
L寸法(L=L1+L2)の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり,圧着後の形状及び寸法を示すものではない。 |
図5.4 動力用ケーブルの端子処理
5.1.3 照明用ケーブル
照明灯及び電路器具などの場合、狭い箱体内での結線作業が容易なように、また、熱による絶縁劣化のため線端処理の修理変更を考え、かつ、箱体に納まるよう余裕のある長さを取るようにする。
先端部に圧着端子を付けるか又は小形端子にそのまま裸締めし、絶縁物の端部には粘着ビニルテープを巻くが、EPケーブルの場合はこれを省略してもよい。
なお、照明用ケーブルのみ作業の効率化を考慮してスプリング式コネクタを使用してもよい。
| (拡大画面:19KB) |
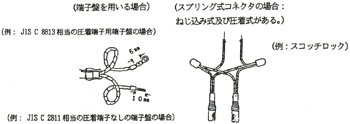 |
図5.5 照明用ケーブルの端子処理
|