|
4. ケーブル布設
4.1 一般
ケーブル布設作業は、船内に装備した多数の電気機器が、すべて完全に動作して、夫々の機能を確実に果たすよう、機器相互間に、規定のケーブルを布設することであり、電気艤装工事の中で、最も大きな比重を占めている。ケーブル布設作業における規則に関連する一般的な注意事項を下記に列挙する。
(1)ケーブルは、できる限り人が近寄りやすい場所に直線的に布設する。
(2)ケーブルは、振動及び衝撃に耐え、かつ、必要以上のたるみを生じないよう、適切な金物を用いて適切な間隔で支持・固定する。(表3.1参照)
(3)ケーブルを、船体構造物の伸縮する部分に、布設することは避ける。これができないときは、伸縮に対して十分な長さのケーブルのたるみを設ける。
(4)ケーブルを機械的損傷を受けるおそれのある場所に布設する場合には、適当な保護をする。
(5)冷蔵庫、電池室及びタンク内部には、特に必要な場合を除き、配線してはならない。
(6)ケーブルを引っ張る場合、ケーブル導体を直接引っ張るときは7kgf/mm2、がい装をグリップで引っ張るときは21kgf/mm2以下の引張力とする。
(7)ケーブルは、所定の屈曲限度以上に曲げたり、ねじったりしない。
(8)ケーブルは、原則として、高温管(蒸気管、排気管など)保温外被から200mm以上離す。
(9)導体最高許容温度が異なる絶縁材料のケーブルは、一緒に束ねない。
(10)2回路の給電線(航海灯制御盤、操舵機用電動機)を必要とするときは、互いにできる限り離れた場所に布設する。
(11)ケーブルは、原則として、防熱材の中を配線しない。
(12)ケーブルの積重ねは、原則として、2層までとし、総積重ね高さは、50mm以下とする。
4.2 ケーブル布設前準備
4.2.1 ケーブル長の計測
ケーブルの長さを計測する方法には、現場で実測する方法と図面上で計測する方法の二つがある。前者は小型船やケーブル長の短い場合に、後者は大型船やケーブル長が長く、しかも本数が多い場合に採用される。精度としては、現場実測の方が高いが、大型船を建造している造船所では、一般に図面上による方法で行なわれている。
ケーブル長を図面上で計測する方法の一例を図4.1に示す。
| (拡大画面:50KB) |
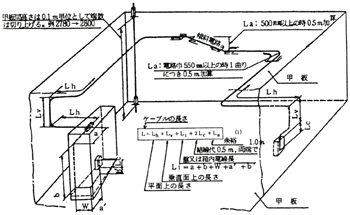 |
図4.1 ケーブル長の計測例
4.2.2 ケーブルの切断
ケーブルは、ドラムに巻かれて納入されるので、これを現場実測により、又はケーブル切断表に従って、所要の長さに切断する。細いケーブルは電工ナイフを、太いケーブルは油圧カッターなどを用いて切断する。
切断したケーブルには、ケーブルの整理や仕分け作業を容易にするとともに、ケーブル布設作業を能率よく行うために、回路符号、ケーブルの種類(略号を一般に用いる)、積込み甲板名(又は色別で標示する。)などを明記したラベルを、図4.2に示すように取付ける。切断端には、ケーブルの絶縁劣化防止と安全性を考慮して、ビニルテープなどで封じておく。
図4.2 ケーブル先端のラベル例
機関室から居住区へ連続して布設されるような長尺ケーブルの場合、機関室必要長さと居住区必要長さとを区別するため、例えば赤テープなどで基準点マークを付けておくと、ケーブル布設時に便利である。
4.2.3 ケーブルの仕分け及び積込み
切断したケーブルは、船内に積込む前に、決められた場所に手際よく積込めるように、表4.1及び図4.3で示すような積込み甲板の色別に仕分けておく。また、ケーブルの仕分け及び積込み作業のときには、下記事項に注意する。
表4.1 積込甲板色別
| 甲板名称 |
甲板符号 |
色別 |
| コンパス甲板 |
C |
黒 |
| 航海船橋甲板 |
N |
白 |
| A甲板 |
B |
赤 |
| B甲板 |
T |
青 |
| 船尾楼甲板 |
P |
緑 |
| 上甲板 |
U |
茶 |
| 暴露上甲板 |
F |
黄 |
| 操舵機室 |
S |
紫(黒) |
| 機関室 |
ケーシング |
E |
橙(白) |
| 第二甲板 |
X |
灰(赤) |
| 発電機甲板 |
Y |
水色(青) |
| 床板甲板 |
L |
銀(緑) |
|
| (注) |
紫、橙、灰色等の色別テープがない時は( )内のように居住区画で使用した色別テープを機関室区画で使用してもよい。 |
| (拡大画面:37KB) |
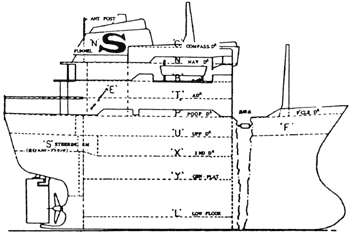 |
図4.3 甲板符号識別例
(1)ケーブルの積込み時は、ナイロンスリングなどケーブルが損傷しない材質のもので吊る。
(2)ケーブルの積込み場所は、他の作業に支障をきたさない場所とする。通路上には、絶対に放置しない。
(3)暴露部に置く場合は、ケーブルが雨ざらしにならないように、適当なカバーをしておく。
(4)船内での保管は、図4.4のようにする。
(a)ワッパ積み
布設順序を考慮して積重ねるか、積重ねた順序を、ボール紙などに記入しておき、布設したケーブルは、チェックしておく。
(b)ドラム積み
長尺ケーブル又は布設順序にドラム巻きにしたものに採用する。
ドラムは倒しておくか歯止めをしておく。
(c)吊下げ
ラベルは、一方向に集め、ケーブルの選び出しを容易にしておく。
吊り下げロープは簡単に外せるよう釣針式の引掛金具を付けておく。
図4.4 船内でのケーブルの保管
4.3 ケーブル布設要領
4.3.1 布設順序
ケーブル布設の順序は、船の大きさ、船の種類及び工作法により異なるが、一般的には、下記のような順序で行う。
(1)区画別
機関室(コントロールルームの下部から)→居住区(上甲板から)→暴露甲板
(2)電路別
主電路→枝電路
(3)線種別
長尺のもの、太いもの→短尺のもの、細いもの。
(4)装置別
大形機器群(主配電盤、集合始動器盤など)→小形機器
4.3.2 布設作業要領
実際の作業における要領を下記に列挙する。
(1)布設場所の整備状況の確認
足場や照明の整備状況の確認、及びガス、溶接、歪とり、塗装など他職種の作業状況を確認する。
(2)ケーブル貫通部の確認
多数のケーブルが貫通し、ケーブル布設時の要所となる部分には図4.5のような、貫通するケーブルを記入した図面を掲げておき、ケーブル布設ごとに本図でチェックする。
図4.5 貫通部ケーブル配置図(例)
(3)ケーブルの引出し.
ケーブルをドラムから引出すときは、ドラム回しなどを使用して大きな張力を加えることなく、ケーブルが引出せる方法を採用する。また、ワッパにしたケーブルを解く場合は、後でケーブルを布設したとき、ケーブルがよじれないよう、8の字に解いて伸ばすこと。
図4.6 ケーブルの引出し
(4)ケーブル行先確認
ケーブルラベルをチェックし、配線図、配線表、系統図などによりその行先を確認する。(図4.2参照)
(5)基準点の確認
基準点マーク(赤テープ)のある長尺ケーブルは、その区間の基準点(甲板又は隔壁などの貫通部に設ける。)に合わせた後、その両端のケーブルを布設する。
図4.7 基準点マーク
(6)電路の分岐
(a)主電路の場合、途中より分岐するケーブルはできる限り電路の上側から分岐し、主電路のランナバーに触れないようにする。
(b)ケーブルはできる限り、交差を避ける。やむを得ず交差する場合は、人目に触れにくい場所で行う。
(c)ケーブル布設後は、速やかに、その布設区域に適応した防水、防火及び防鼠(そ)工事を行う。
図4.8 電路の分岐例
|