|
5. 直流
| (拡大画面:8KB) |
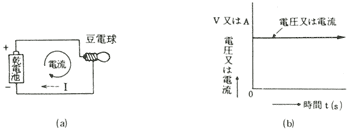 |
図5・1
図5・1(a)のように乾電池を電源として豆電球を点灯すれば図のように流れる電流は時間に対して方向一定でその値が変化しないで図5・1(b)のように一定の値で流れている。これは純粋な直流である。(純粋という意味は電圧、電流ともその波形は一直線であるという意味である。)蓄電池電源の場合も同様である。
直流発電機の電機子コイルに発生する電気は交流であるが、整流子を通って刷子から出てくる電流は直流となる。よって、直流発電機という。(詳細については電気機器編を参照のこと。)
しかし、電機子コイルの数と整流子片の数の多小によって次のように考えられる。
(1)1個のコイルと2個の整流子片の場合の電圧の波形は図5・2のようになる。即ち整流子の整流片によってBの山がCの山に変換され、つづいてB'の山がC'の山に変換され電圧の波形は常に(+)方向にあって一種の直流である。
図5・2
(2)4個のコイルと4個の整流子片にすれば電圧波形は図5・3のようになる。
図5・3のAの波形の中間にBの波形が入ってきて、しかも(−)側の波が(+)側に変換され、しかも、それらの合成をとればMのような波形になる。これを脈流という。
図5・3
(3)以上の理由から、脈流の波を細かくするには、電機子コイルの数と整流子片の数を増やせばよい。しかし、いくら増やしても電池電源のように1直線状にはならないが実用的には差し支えない。
この場合は、交流電源のものを直流に変換する場合に使用する回路であって、これには半導体ダイオート等を使用して直流にするものである。そして次のような方式がある。
(1)単相半波整流方式
| (拡大画面:10KB) |
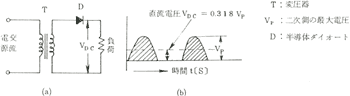 |
図5・4
図5・4(a)の回路を用いて整流された電圧波形は、図5・4(b)のように脈動している。図5・4(a)において出力側即ち抵抗側の電圧の最高値と最低値との差をΔVとするとき、ΔV/VDCを脈動率という。
注:ダイオードとは、電流が(+)方向には通ずるが、(−)方向には通じないような性質を持っているものである。
(2)単相全波整流方式
図5・5(a)は結線図を示し図5・5(b)はその波形を示す。
| (拡大画面:12KB) |
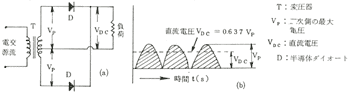 |
図5・5
(3)単相ブリツジ整流方式
| (拡大画面:13KB) |
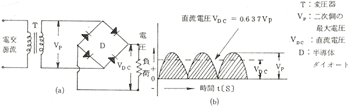 |
図5・6
図5・6(a)は結線図を示し、図5・6(b)はその波形を示す。
(4)三相整流器
| (拡大画面:10KB) |
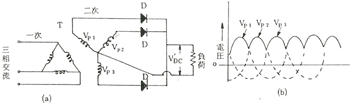 |
図5・7
図5・7(a)は結線図を示し図5・7(b)はその波形を示す。
直流平均電圧、脈動率などは省略する。
(5)平滑回路
以上述べた(1)、(2)、(3)、(4)等の整流回路から得た脈動電圧を完全な直流に近づけるために用いる回路が平滑回路である。この場合周波数の低い波を平滑にする目的があるから低域フィルターを使用する。これを例示すれば次のものがある。その何れかが整流回路に併用される。(図5・8参照のこと。)
| (拡大画面:7KB) |
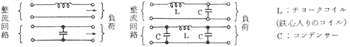
|
図5・8
|