|
5. エンジンの運転と性能評価
現在、高出力、低エミッションディーゼルエンジンの研究が世界各国で行われ、その有力な方法として予混合圧縮着火ディーゼルとエンジンが提案されている。このエンジンでは、吸気管から空気と燃料の混合気を供給し、圧縮着火させるものであるが圧縮比の大きいディーゼル燃焼にとって、過早着火、部分負荷での超希薄燃焼の問題等が有り、その実現が困難とされている。
本プロジェクトでは副燃焼室を設け、主・副室内に制御バルブを置き、その制御バルブを圧縮上死点付近で開弁させ、点火エネルギーとする方式を用いた。一方、主燃料は吸気管より空気と共に導入させ、天然ガスの早い燃焼を制御させる為にEGRを多量に行う事とした。
上記コンセプトに基づいて、エンジン開発を進めた。
5−1. エンジン性能の評価結果
5−1−1. エンジン試験時に発生した諸問題の解決
現在、ディーゼルエンジンの燃焼では圧縮比が大きいために熱効率が良い特性を生かしつつ、混合気を均一予混合気とする研究が進んでいる。この予混合圧縮着火(HCCI)燃焼についてはCNG燃料を用い、かつ遮熱エンジンで燃焼させるための試験を実施した。
この燃焼の実現のために必要な技術検討項目を以下に纏めた。
| (1) |
部分負荷での均一混合気は余りにも希薄に成り過ぎ完全燃焼が困難である。 |
| (2) |
負荷が大きくなるとノッキングが起こり、機関に損傷が発生する。 |
| (3) |
着火のタイミング、手段を選ぶ事が難しい。 |
| (4) |
遮熱エンジンでは燃焼室の壁面温度が高く、着火し易くなり、ノッキングが発生しやすい。 |
| (5) |
部分負荷時に未燃HCの排出が多くなる。 |
| (6) |
CNGは着火温度が高く、始動方法が困難である。 |
以上の問題点に対し、次の対策を実施した。
| (1) |
副燃焼室を設け、副室と主室間には開閉バルブを置き、上死点付近でそのバルブを開放する。副室には全負荷相当燃料の15%程を吸入工程に投入し、バルブの開閉と共に進入した圧縮空気により着火させる。(図5−1参照) |
| (2) |
負荷の増大と共にEGRの量を増加させて混合気中の酸素濃度を希薄にし、燃焼速度を低下させる。 |
| (3) |
着火は圧縮着火とし、着火に必要な火炎の伝播をスムーズにするために、副室に濃混合気を置き、ここに圧縮した高温空気を流入させて着火させる。副室の開弁タイミングをBTDC15度にセットすれば着実に着火させる事が出来る。 |
| (4) |
遮熱エンジンでは壁温が600℃以上になるので吸入空気の温度を130℃以下とするためにEGRガスを熱交換器により、冷却させる。 |
| (5) |
部分負荷時の未燃のHCを完全に燃焼させるためには燃焼室内のガス温度を一旦1100K以上にする必要があるので部分負荷時にはEGRガスの温度を下げずに使用する。更に温度を上昇させるために吸気加熱ヒーターを用いた。 |
| (6) |
初期のエンジンの始動には吸入空気温度を上昇させる必要があるので多孔質金属を用いたヒーターを作製し、吸気温度の加熱をした。 |
以上の対策により、エンジンテストが行われた。
| (拡大画面:24KB) |
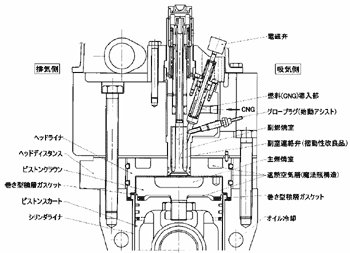 |
図5−1 エンジンの内部構造
5−1−2. 高負荷運転について
エンジン試験の初期にはNA方式でエンジンの試験が行われたがこのエンジンは負荷の増大と共にEGR量を増さないとノッキングが発生するのでEGRを実施した。EGRを実施すると吸気中の酸素が不足するので全負荷相当の7割しか燃料を投入出来ない。そこで過給をする事にしたが2シリンダー用の過給機が存在しないので別置きのエンジンコンプレッサーを用いてターボチャージャーを回すと同時にコンプレッサー空気をターボチャージャーに送り、ブースト圧を上昇させて試験した。図5−2にはコンプレッサーとエンジンの配置状況を示す。以上のように試験条件が整ったので試験を開始した。
| (拡大画面:12KB) |
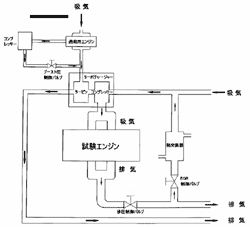 |
図5−2 過給用エンジンを付加した時のエンジン配管図
図5−3にはエンジン負荷を変化させた時、最大の筒内圧力排気ガス温度を示した。全負荷状態で12MPaになり、1/4負荷では7.0MPaになる。この時、副室への燃料流量は1/4負荷で100%、4/4負荷では17%である。この副室燃料流量を増すとノッキングが極めて発生しやすくなる。全負荷時のEGR率は18%である。排気ガス温度は目標値900℃に対し、800℃であった。
次にブースト圧力を徐々に上昇させた。エンジンに吸入される空気量に見合って燃料を増加させる事が出来るのでブースト圧力と燃料を増加させる事で、吸気ガス量が増加し、シリンダー内の最高圧力、平均有効圧力が増加する。図5−4にはブースト圧力を上昇させた場合、上昇するピークシリンダー圧力を示した。ブースト圧力を0.1MPaに増加させると吸入空気は約2倍に増加し、シリンダー内の最高圧力は約12MPaに上昇した。
エンジンの緒言
| 項目 |
単位 |
詳細内容 |
| 燃焼室形式 |
|
制御弁付副室式 |
| 径×行程 |
mm |
132.9×145 |
| 総行程容積 |
CC |
2011(1シリンダー) |
| 最大出力/回転数 |
KW/RPM |
26KW/1500RPM(1シリンダー) |
| 圧縮比 |
|
16 |
| 燃料供給時期(吸気) |
クランク角 |
ATDC60〜130度 |
| 副室制御弁開弁時期 |
クランク角 |
BTDC30度〜排気BTDC40度 |
| 過給機の有無 |
|
無し |
| 機関寸法 |
mm |
全長1390*全幅790*全高1250 |
| 吸気弁開弁時期 |
クランク角 |
上死点前15度 |
| 吸気弁閉弁時期 |
クランク角 |
下死点後40度 |
| 排気弁開弁時期 |
クランク角 |
下死点前35度 |
| 排気弁閉弁時期 |
クランク角 |
上死点後15度 |
| 使用燃料 |
|
天然ガス |
| 予混合燃料割合 |
% |
90〜80% |
| 主燃料供給方式 |
|
吸気管導入方式(0.2〜0.3MPa) |
| 副燃料供給方式 |
|
副室導入方式(0.5〜0.7MPa) |
| 副室容積比 |
% |
15 |
|
図5−3 負荷割合と筒内圧力
図5−4 ブースト圧力と筒内圧力
以上より、エンジンの高負荷運転が出来る事を確かめたが、このCNGエンジンの運転ではEGRを減少させるとノッキングが発生して負荷が減少し、吸気温度が低下するとミスファイヤーが発生するのでこの現象を取り込んだエンジンの制御装置を作製した。
5−1−3. ノッキング性の評価
遮熱エンジンでは燃焼室の壁温が上昇するので高負荷条件では絶えずノッキング発生の可能性がある。ノッキングを抑制するためにはEGRを実施して、酸素濃度を小さくし、CO2 を加え、燃料の燃焼抑制効果を発揮させる必要がある。図5−5にはエンジン負荷に対するノッキングの発生状況を調査した結果を示す。
ブースト圧力を増加させ、吸入空気量を変化させてEGRを実施し、徐々にEGR量を減少させ、ノッキングを発生させた条件でエンジン運転を中止させる事により、ノッキング限界を調査した。
試験条件は燃料を200cc/1cycl・1 気筒とし、ブースト圧力を0、0.2MPa(ゲージ圧力)とし、EGR量は全吸入空気量に対してのパーセンテージとし、吸入ガス温度は絶えず130℃以下になるようにした。
図によると全負荷、ブースト0.2MPaでは50%EGRしないとノッキングが発生し、1/4負荷でも18%程度のEGRを実施しないとノッキングが発生する。また、ブーストを0 にすると1/4負荷ではノッキングとミスファイヤーが区別しにくい燃焼条件であるが高負荷になり、燃焼室の温度条件が整ってくるとノッキングが発生し、EGR量を加えないと安定した燃焼状態にならない。従って、エンジンの運転ではこの条件を満たすような試験条件を絶えず作って試験した。
EGR量を増加させると酸素濃度が減少する事は間違いないがその他、燃焼ガス中に含まれているCO2、H2Oによる燃焼抑制効果が期待出来る。本エンジンの試験では主室燃量の空気過剰率は部分不可では大きく、負荷が大きい時には1.1〜1.3ほどと小さいため、全負荷領域では燃焼に必要な酸素を確保するため、ブースト圧力を上昇させ、EGRを増加させる必要がある。
図5−5 エンジン負荷に対するノッキングの発生状況
|