|
橋梁による制限では図−3.1.3に示すように、橋梁の桁下高さと船舶のマスト高さ(船高)による比較を行い、船舶の航行を制限する橋梁を抽出した。各橋梁の桁下高さは、表−3.1.3に示すとおりである。
橋梁の桁下高さが船舶の航行の妨げとなる箇所は表−3.1.4に示すとおりであり、常磐線の橋梁において貨物船(1000t積)が航行することができない。その他の橋梁においては代表的な船舶としてあげた15パターンは全て橋梁を通過し航行することができる。
橋梁によって船舶の航行を制限する箇所は荒川では常磐線の橋梁1箇所のみであり、制限される船種も貨物船(1000t積)の1種類のみであった。
 |
| 図−3.1.3 橋梁の桁下高さと船舶のマスト高さ(船高)による航行の制限 |
| No |
橋梁名称 |
線名 |
No |
橋梁名称 |
線名 |
| 1 |
高速湾岸線 |
高速湾岸線 |
20 |
地下鉄千代田線鉄橋 |
営団千代田線 |
| 2 |
荒川河口橋 |
国道357号 |
21 |
千住新橋 |
国道4号 |
| 3 |
地下鉄東西線鉄橋 |
営団東西線 |
22 |
西新井橋 |
尾竹橋通り |
| 4 |
葛西橋 |
葛西橋通り |
23 |
扇大橋 |
尾久橋通り |
| 5 |
地下鉄新宿線鉄橋 |
都営新宿線 |
24 |
江北橋 |
|
| 6 |
船堀橋 |
|
25 |
荒川アーチ橋 |
高速中央環状線 |
| 7 |
荒川大橋 |
高速7号小松川線 |
26 |
鹿浜橋 |
環状7号 |
| 8 |
新小松川橋 |
国道14号 |
27 |
新荒川大橋 |
国道122号 |
| 9 |
総武線鉄橋 |
JR総武線 |
28 |
高崎線・京浜東北線鉄橋 |
JR高崎線・京浜東北線 |
| 10 |
平井大橋 |
蔵前橋通り |
29 |
埼京線・東北新幹線鉄橋 |
JR埼京線・東北新幹線 |
| 11 |
木根川橋 |
|
30 |
戸田橋 |
国道17号 |
| 12 |
京成押上線鉄橋 |
京成押上線 |
31 |
笹目橋 |
国道17号 |
| 13 |
新四ツ木橋 |
国道6号 |
32 |
幸魂大橋 |
東京外環自動車道 |
| 14 |
四ツ木橋 |
国道6号 |
33 |
武蔵野線鉄橋 |
JR武蔵野線 |
| 15 |
荒川橋 |
高速6号向島線 |
34 |
秋ヶ瀬橋 |
|
| 16 |
堀切橋 |
|
|
|
|
| 17 |
京成成田線鉄橋 |
京成成田線 |
|
|
|
| 18 |
東武伊勢崎線鉄橋 |
東武伊勢崎線 |
|
|
|
| 19 |
常磐線鉄橋 |
JR常盤線 |
|
|
|
|
| 注): |
クリアランスについては船種経験度等により巾があるためここでは単に桁下高さとマスト高の対比を行ったので実際の河川内航行に当たっては所要のクリアランスの確保が必要である。 |
| 表−3.1.4 橋梁の桁下高さが船舶の航行の妨げとなる橋梁 |
| (拡大画面:67KB) |
 |
水深による制限では図−3.1.4に示すように、水深と船舶の満載喫水による比較を行い、船舶の航行を制限する橋梁を抽出した。河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水を比較した結果は図−3.1.5及び 表−3.1.5に示すとおりである。 河口から10km付近までで、水深が3mを下回る部分があるため、台船以外は全てこの部分で通航することができない。
また、河口から20km付近、25km付近においては水深が2m程度となり、台船も通航することができない部分もある。
なお、比較に用いた水深は塑望平均干潮位における場合であるため、常に水深と満載喫水の関係が本検討の状況となる訳ではない。
船舶の通航に関しては、桁下高さよりも水深による物理的制限の方が大きく、通常時も緊急時も水深に配慮して通航する船舶を選択しなくてはならない。
 |
| 図−3.1.4 河川の水深と船舶の喫水による航行の制限 |
| (拡大画面:31KB) |
 |
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[台船] |
| (拡大画面:30KB) |
 |
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[バージ] |
| (拡大画面:31KB) |
 |
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[土砂運搬船] |
| (拡大画面:32KB) |
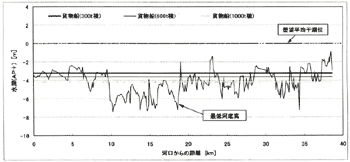 |
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[貨物船] |
| (拡大画面:31KB) |

|
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[タンカー] |
| (拡大画面:31KB) |

|
| 図−3.1.5 河川の水深(最低河底高)と船舶の満載喫水の比較[内航コンテナ] |
|