また、代用水と通船堀の交わる近くには、仮の締切りがあり、ここには木材などがおかれていた。パナマ運河なども基本的には同じ構造であり、パナマ運河の建設(1914年)よりも183年も前に造られたことから、技術的にも高く評価されている。(写真1参照)
江戸へ運航する舟が、隅田川から荒川を経由して芝川に帰ってくると、船頭は八丁河岸に舟を繋いで、近所の人に声をかけ、土手から綱で舟を曳いて一の関まで舟を引き上げる。次いで、人々に手伝ってもらって堰板を入れて水位を調整しながら上流に舟を進めていくわけである。その舟の移動の手順は、図2の通りである。舟が下る時は、この反対の作業が行われる。
(2) 見沼干拓と水運
この見沼通船堀が開通した後は、江戸と見沼用水路近くの村々は水運で結ばれることとなり、年貢米の輸送のみならず、各種の物資輸送が盛んになっていった。その結果、この水路は大正末年まで使われることとなる。
見沼近くの村々からは、年貢米を中心として、野菜、薪炭などの農産物が江戸に積み出され、帰りには肥料や、塩、酒などの商品が運ばれてきた。このような荷物の揚げ下ろしをする河岸場が芝川と代用水の東西両縁水路沿いに59ケ所もあったといわれている。八丁の河岸場もその一つであり、この付近には河川輸送にたずさわる人たちが住んでいた。現在でも、芝川に架かる八丁橋のたもとには水神社が祭られているが、この神社は、かつて舟運の仕事に関係した人たちが水難防止を祈願して祀ったものである。このことは、この周辺に通船で働いていた人達が多数住んでいたなによりの証拠である。また、見沼代用水西縁にも、北袋河岸跡の説明板が立てられている。
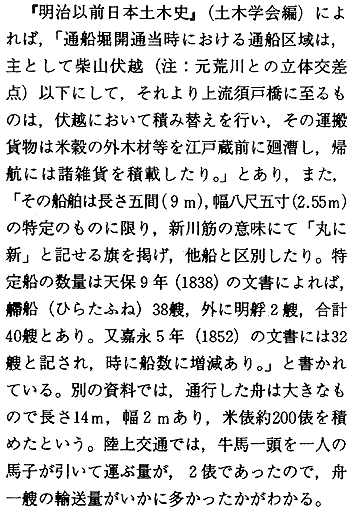
幕府勘定方井沢弥惣兵衛為永に従って、見沼の干拓に従事した家が鈴木家と高田家である。享保16年(1731)の見沼通船堀の完成と同時に両家は、幕府から差配役に任じられ、江戸の通船屋敷で通船業務を司り、八丁堤などには通船会所をもっていた。