時代と共に技術面や物理上の制約が変化してきているために、標準的な船型も部分的に変化してきている。例えば、より経済的で大馬力のエンジンが開発され、かつ、船腹における船種構成も変化してきているために、コンテナ船はより大型になってきている。ウォータージェット推進の高速フェリーや、新造・中古タンカーの洋上生産・備蓄・積出し施設(FPSO)への転用などは、ここ何年かの間に、部分的に船種の様相を変化させた技術的進展であるが、海運業の中心的な船種に影響を及ぼすような技術面の大きな変化は予測されていない。
現存船腹と手持ち工事の平均船型を比較することにより、船舶の大型化の傾向がよくわかる。これを表2.Bに示す。
表2.B:船舶(現存船及び手持ち工事)の平均船型(単位:DWT)
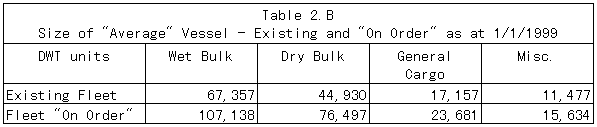
この表は、また、それぞれの船種の特性の違いを示すものともなっている。ウェットバルクや(これほどではないが)ドライバルク船隊は、非常に大型の船舶が多く、平均サイズが大きくなっている。一般貨物やその他では、小型の一般貨物船やその他の船舶が中心となっているので、平均サイズが小さくなっている。こうした特徴は、手持ち工事の平均サイズにも現れており、平均増加量は、ウェットやドライバルクよりずっと小さくなっている。
2.3 資本価値
2.1項で述べた手法を用いて世界の船腹の価値を算定した。1999年初における、世界の現存船腹の価値は2,221億ドルと推定される。図2.Aの右側の円グラフに船種別の構成比率を、表2.Cに算定値を示す。
表2.C:世界の現存船腹の価値評価(単位:百万ドル)
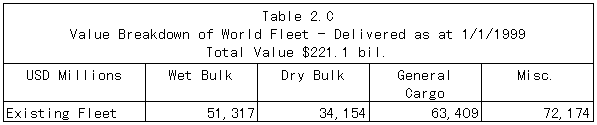
図2.Aの2つの円グラフを比較すると、ウェット及びドライ部門と一般貨物及びその他の部門との間に、著しい相違があることがわかる。ウェット及びドライ部門は、DWTの75%以上を占めているのに、資本価値では38%にしかならない。この理由は、一般貨物・その他の部門の船腹が相対的に高価値であることにある(クルーズ船、乗客フェリー、LPG/LNG船、リグなど。それほどではないが、コンテナ船もそうである。)
前ページ 目次へ 次ページ