平成11年秋季講演論文概要
1]遺伝的アルゴリズムによる船首形状改良
安川宏紀(三菱重工)
船型を微少に変更したときの造波抵抗理論式に基づくランキンソース法に遺伝的アルゴリズム(GA)を組み合わせた船型改良法を提案し、Series 60(Cb=0.6)船型を対象として船首形状の改良を行った。その結果、船長に基づくフルード数O.3において、理論上約25%の造波抵抗軽減が可能となるバルブ型最適船首形状を得ることができた。本手法は、船型設計ツールとして有効であることが分かった。
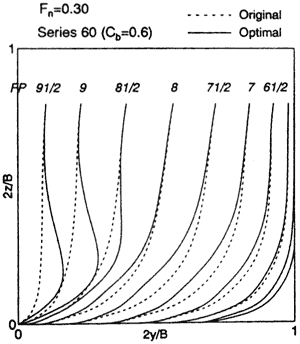
母船型とGAを用いた最適船型の比較
2]動揺しながら平水中を進行する船の波の水面透過光分布を用いた解析(英文)
Erwandi(大阪大学大学院)、鈴木敏夫(大阪大学)
動揺しながら進行する船の周りの非定常波紋は、縦切り法、横切り法等により解析されているが、位相をずらした複数回または複数点の計測が必要である。本論文は、水面透過光により可視化された波紋のデータ(図1)を用いることにより平面的な情報が利用できる解析法について述べている。今回は縦切り法、横切り法との比較(図2)を行い、組成波の角度が小さい範囲で定性的に一致する結果が得られた。
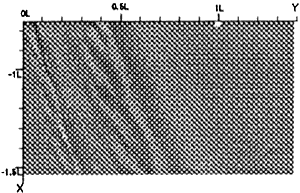
図1 Cos term of Unsteady Brightness
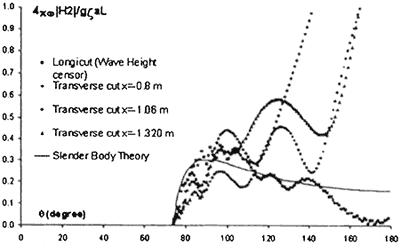
図2 Kochin Function of Radiation Waves
3]簡便なパネル法による3次元定常キャビテーションの計算
安東潤(九大)、松本大輔(MHI)、毎田進(FEL)、大橋訓英、中武一明(九大)
Kutta条件を繰り返し計算なしに満足できる簡便なパネル法(SQCM)を用いて、3次元直進水中翼に発生する定常キャビテーションの計算を行い、キャビティ形状や圧力分布、揚力や抗力などの計算値を実験値と比較して、本計算法の有用性を確かめた。
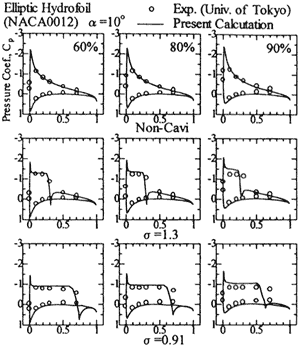
楕円水中翼の圧力分布
(%は半幅に対する割合)
4]プロペラサーフェスフォースに影響する諸因子について
佐藤和範(日本造船技術センター)
キャビテーション水槽における模型試験結果をニューラルネットワークの再構築学習法、線形回帰分析等の手法で統計的に分析することにより、プロペラ形状、伴流分布、迎角変動、キャビテーション数、チップクリアランス等の諸因子がどの程度プロペラサーフェスフォースに影響しているかを調査した。
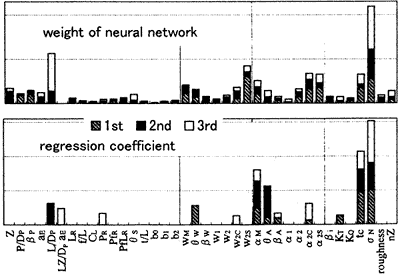
プロペラチップ直上の圧力変動に対する再構築学習法、線形回帰分析の結果
目次へ 次ページ