スポーツクラブの夢と課題
田尻稲雄氏

田尻稲雄
北海道バーバリアンズ ラクビーフットボールクラブ ジェネラルマネージャー
1948年小樽市生まれ。小樽湖陵高校時代の同級生や後輩達とともにボーミッツラグビーフットボールクラブを設立。初代キャプテンを務めた。87年に活動の拠点を小樽から札幌へ移し、クラブ名を北海道バーバリアンズラグビーフットボールクラブに変更。89年初代ジェネラルマネージャー、91年二代目クラブキャプテンを務める。
実際にクラブを運営している立場として、苦労話は山ほどあります。ただ、うちの理念というか、追求していこうとしているのは、セルジオさんがおっしゃっていた強化の部分で1つのクラブに1つのチームというのではなく、1つのクラブに何チームもあっていいじゃないか、みんなでラグビーを楽しめる場としてのクラブでありたいというのが最初からありました。今、大体常時40〜50人は集まって、3チームの試合ができるという状態になっています。
この状態を継続していくためにも、当然、専用グラウンドが欲しいし、クラブヘのロイヤリティ(帰属意識)を高める意味でもクラブハウスを持ちたいというのが当面の夢になります。NPO法人格を取ったのも実はそのあたりの事情です。
市民社会の中で、たとえばグラブハウスを持つ、あるいは土地を持ったり建物を建てる場合に、個人で登録することはできても「クラブのもの=みんなのもの」にはなりませんよね。法人でなければ、団体としての契約行為ができないわけです。クラブハウスを持てば、いろんな形でアフターイベントといいますかゲームや練習が終わった後、そこに集まってお酒を飲んで、今日のおまえのプレーはどうだったとか、1億総監督ってよく言われますけれども、プレーに参加しなかった人たちでもみんなでわいわい話し合える。そういう場がクラブライフの楽しさをつくる一番最初のきっかけになるんじゃないかと。それでどうしても法人格が欲しかったんですね。
クラブを維持していくには、そのクラブがやっぱり、本当に自分のものであったり、あるいは自分の家族のものであったり、自分の地域のものであるという意識をたえず持ってもらう仕掛けが必要です。その中心になるのがクラブハウスだと思います。
そして、グラウンドをもし持てたらですが、毎朝、そこへ行って水をまき、種をまく「花咲かじいさん」になりたい、というのが僕の夢です。つまり、外野席で応援するだけがサポーターではなくて、選手を育ててあげる、あるいは育てるためにサポートするサポーターになりたい。ある時はプレイヤー、ある時はサポーター、そういう人たちの集まりがスポーツクラブなのだというのが僕の結論です。
クラブライフの要は女性、そして社会に貢献できるスポーツクラブの青写真
松本富士也氏

松本富士也
(社)江ノ島ヨットクラブ副会長 1932年沼津市生まれ。スナイブ級全日本個人選手権優勝、国体・全日本実業団選手権優勝、スナイブ級世界選手権出場など、優秀な成績をおさめた。64年東京五輪にも5.5m級の代表選手として出場している。また、日本ヨット協会理事、同オリンピック強化委員長、モスクワ五輪(不参加)とロサンゼルス五輪の監督、スナイブ級国際競技連盟会長を務めた。
江ノ島ヨットクラブは恵まれたスタートを切りました。というのは、東京オリンピックのときに国がヨットハーバーを作ってくれ、県が世界のヨットクラブに負けないクラブハウスを建ててくれたのです。それから35年、お上に頼ったツケが回ってきています。
ここ4〜5年、若手を中心に、といっても67歳の私が若手の一員なのですが、自分たちでとにかくクラブを楽しいものにしなければと動き始めたところ、さまざまな壁にぶち当たっています。壁の一つは、お上のおんぶにだっこに慣れて、何かメリットがなければクラブに入らないという人達がいることです。
突破口になるかと思っているのが、江ノ島ジュニアヨットクラブ。従来は、「親は金を出しても口は出すな、手は出すな」という形でやってきましたが、ここ数年、親も手伝え、ヨットを知っていようがいまいが、このジュニアクラブを存続させるために手を貸してくれ、という形に変えました。最初はとまどいもあったのですが、競技スポーツとしてチャンピオンシップに挑戦するグループと、純粋にヨットを楽しむグループの2つができ、そのうちにヨットを知らないお母さんたちが、子どもたちと一緒にヨットに乗り始めたんです。クラブの中心は、コーチでもない、監督でもない、最終的にはそのクラブの楽しさを決定づけるのは女性だと私は思いました。
お母さんがヨット好きになれば、お父さんも必ずついてきます。そんな格好で親御さんたちも含めたヨット家族が増えてきて、土日に集まるのが楽しいという雰囲気が生まれてきたんですね。これが、どんどん続いていくと、お上に作っていただいたヨットクラブとは違う、本来のスポーツクラブとして存続していく価値が出てくるだろうな、と思っています。
もう一つの壁が社団法人の定款変更でした。社団法人というのは社会に対してのみ奉仕するのが使命だそうです。ヨットの大好きな人達が親睦を図るのを目的にしてはいけないとのこと。ヨットというスポーツは、レースの後でワイワイ話をするのが楽しい。だから、これをほかの人たちにも勧めたい。たとえば湘南地区の学校と協力して、小学生、中学生、高校生にヨットを体験させてあげよう、と思っても、まず人の和を作る、楽しい雰囲気を作ることは「社団法人」ではルール違反なのです。「人の和」と「楽しさ」が原動力となってこそ、社会貢献活動が展開出来ると思うのですが……。自分たちが愛しているスポーツを地域に還元する。そういう活動を通じて、地域社会に貢献できるスポーツクラブができていくのではないですか? この国におけるスポーツクラブとは何か、真剣に考える時期にきていると思います。
クラブハウスという「核」から、クラブづくりはスタートする
小林章夫氏

小林章夫
上智大学文学部英文学科教授 1949年東京生まれ。上智大学大学院文学研究科修士課程修了。専攻はイギリス文学・文化。大のイギリス好きであり、年に数回イギリスへ行き、イギリス文化に親しんでいる。サッカーとラグビーにも興味があり、しばしば観戦に行く。「イギリス紳士のユーモア」「イギリス王室物語」「イギリス貴族」(以上講談社現代新書)「ロンドンのコーヒーハウス」(PHP文庫)、「賭けとイギリス人」(ちくま新書)など著書多数。
スポーツクラブができるか、できないか、を考えるのではなく、僕は今の時代こそ、スポーツクラブをつくる時期だと思います。というのは、ついこのあいだまで夜中まで働いていた人たちの仕事が減ってきた。週に2日、3日は休みになる時代になっています。この現象を、人生二毛作時代になったと僕は言ってるんです。つまり、今まで仕事だけだったのに、やむを得ず、もう1つ新しい自分の生活の場を探さなくちゃならない時代。そこでスポーツとどう向き合うかということが浮上してきたように思うのです。
また、おそらく10年前には予想できなかった情報化社会の進展度です。つまり、セルジオさんがおっしゃってた、手触りとか生身の人間との接触がほとんどなく、機械だけでモノが動いていく、そういう時代になった。そういう時代だからこそ、逆に肉体といいますか、スポーツにかける部分、あるいは本物の手触りを求める部分というのが出てくると思う。スポーツクラブの存在意義もそのあたりに置かれるのではないですか。
スポーツクラブが成立するには、スポーツにお金をかけるのは何となく無駄だ、という意識が変わってこなくちゃいけない。手っ取り早い方法は、学校でスポーツをやめることです。体育の先生には申しわけないけれど、今まで学校あるいは企業がスポーツを担う一機関だと思われていた。でも、もうそうじゃない。スポーツがしたければ、自分の意思でお金を出す、というくらいに追いつめないと。その代わり、彼らを満足させるクラブ・サービスが必要になってきます。その原点になるのが、僕はクラブハウスだと思っています。クラブハウスがあるか、ないかというのは、大変大きな問題で、じゃあ、そのクラブハウスをどうやってつくるか。これは僕には何とも言えませんが、会員がみんなでお金を出し合って作る小さなクラブハウスでもいい。そこが核となって、さまざまな人間の広がりができてくるだろう、と思います。
コーディネーターの立場からひとこと
土川由加氏
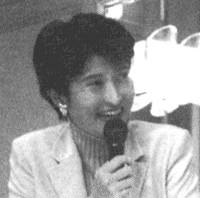
土川由加
1966年生まれ。国際基督教大学卒業。88年テレビ東京へアナウンサーとして入社。92-96年に「スポーツTODAY」キャスターとして活躍。バルセロナ五輪とアトランタ五輪の現地キャスターを務めた他、全仏オープンテニス、全豪オープンテニスの実況リポートも担当した。99年1月にテレビ東京を退社し、現在ではフリーとして活動しているかたわら、ゴルフ、エアロビクス、キャンプなども趣味として楽しんでいる。
セルジオ越後さんのお話、パネリストの皆さんのお話を大変楽しく拝聴しました。特に、田尻さんや松本さんのお話からは、クラブライフというものがいかに大事か、ということを教えていただきました。極端にいえば、そのクラブライフを充実させるために、みなさんスポーツクラブをつくっているんじゃないか、と思えるほどです。
マイ・クラブという「誇り」とクラブへの忠誠心は表裏一体のものだと思いますが、そのの「熱意」はどこからくるのか、ということでちょっと思い出したことがあります。テレビ東京のアナウンサー時代、日本一のスポーツ番組と言われていた「スポーツTODAY」でキャスターを務めていたのですが、そこでちょっとお話を伺ったら、巨人ファンの方というのは巨人が勝った日には、全チャンネルのスポーツニュースを見るんですって。何度も何度も反芻するように。逆に、負けた日はまったく見ないというんですよ。小林さんによると、熱烈な阪神ファンも同じ行動をとるようで、このファンの心意気というのはすごいエネルギーだな、と気づきました。
日本人が現実に持っている、野球やサッカーの贔屓チームに対する熱意という部分をスポーツクラブに反映できたら、まったく違う展開ができるような気がしてなりません。その「クラブ」を理屈抜きに好きになる、そんな魅力づくりが総体としての「クラブライフ」を充実させていく秘訣になるのではないでしょうか。
1日も早く、日本にさまざまなスポーツクラブが根づいて、心から感動できるスポーツシーンをたくさん見たい、そして多くの人に伝えていきたいと思っています。
前ページ 目次へ 次ページ