当時のアルミニウム構造に関する英国規格CP 11839)は、塑性域には直線式を採用していた。しかし、1991年制定の後継規格BS 81185)における計算式は、その詳細を略すが、形態からみると式(7)を発展させたもののようである。
(3) ジョンソン(Johnson)の式
この式は鋼構造で用いられ、σ'k=σs-Cλ'2で表される。ここに、σsは降伏点、Cは材料定数、λ'は相当細長比である。オイラー式との境界を決める比例限度σpは、経験的に材料の比例限度より低くとるのが普通であり、米国のSSRC(Structural Stability Research Council)はσp=0.5σsとすることを提案した。この場合、ジョンソンの式は、λ'<Λで次のように表される40)。
σk=σs-{σs2/(4π2E)}λ'2 (8)
オイラー式との境界に当たる細長比Λは、次のようになる。

式(8)において、降伏点σsを圧縮耐力σyに置換して検討すると、5083-H112(前出のFig.16参照)や5052-O合金の場合には実験値とほぼ合致するが、5052-H112合金ではλ'=55〜80の範囲で危険側となる例もある41)。「アルミニウム合金製漁船構造規準(案)」及び「高速船構造基準」におけるアルミニウム合金梁柱の計算式は、同様な置換に基づいている。
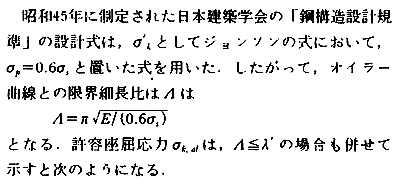
Λ≧λ':σk,al={1-0.4(λ'/Λ)2}σs/S (9)
Λ≦λ':σk,al=(π2E/λ'2)/S
={0.6σs/(λ'/Λ)2}/S
ここに、Sは安全率で、次式による。
S=1.5+1.5(λ'/Λ)2≦2.17
3年後に制定された同学会の「アルミニウム合金建築構造設計施工規準案」の設計式は、上述の鋼構造の場合とほぼ同じ取扱いである。ただし、計算上の比例限度はσr(規格の最小値)に比例するものとし、σp=(1-α)σr、として、αの値を次のように仮定した*4。
質別T6の場合 α=0.5
質別T5の場合 α=0.6
質別T4及び非熱処理材 α=0.7
これより、オイラー曲線との限界細長比Λは式(10)から求められる。

許容座屈応力は、Λ<λ'の場合も併せて以下に示す。
20<λ'≦Λ:σk,al={1-α(λ'/Λ)2}σy/S (11)
ここに、S=1.5(0.9+0.6λ'/Λ)、ただし、
S≧1.5
Λ<λ':σk,al=(1-α)σy/2.25(λ'/Λ)2
なお、λ≦20では座屈の影響を無視して取扱い、σk,al=σy/1.5とした。また、式(11)の分母の安全率Sは、計算に便利なように直線式に直したものである。
式(11)は、その後「アルミニウム利用技術指針」の設計式にα=0.5として引き継がれており、この場合、S=1とした式(11)は、6063-T5合金押出形材5種類についての実験結果42)のばらつきのほぼ中央に位置することを解説で述べている。また、JlS B 8502「アルミニウム製貯槽の構造」における設計式も式(11)に基づいている。その解説によると、αの値として指定された0.5、0.6又は0.7を使用すると、小さなσyに対するσk,alが大きなσyに対するσk,alより大きくなる部分が出てくるので、これを避けるためにα=0.4を採用したという。
以上の各式は、いずれも軸心に圧縮荷重を受ける場合である。圧縮力と曲げモーメントを受ける場合、局部座屈、ねじり座屈その他*5については省略するので、関連する規準又は規格等を参照されたい。
2.4 安全率及び強度低下係数
2.4.1 安全率と静的許容応力
我が国におけるアルミニウム構造物の設計には、鋼構造の場合と同様に許容応力設計方式が採用されている。
静的許容応力を考える場合、降伏応力の目安としての耐力と、終局強度としての引張強さの二つが基準となる。
*4 σp=(1-α)σyとしてジョンソンの式に代入すると、
σ`k=[1-{1/4(1-α)}(λ'/Λ)2]σy
となる。したがって、式(11)のαは{1/4(1-α)}と置くのが本来の姿のようである。式(9)の場合はσp=0.6σy、すなわちα=0.4であるから
σ'k=[1-{1/4×0.6}(λ'/Λ)2]σy
≒[1-0.42(λ'/Λ)2]σy
となり、近似的に0.4(=α)である。α=0.5の場合は{ }内も0.5であるが、α=0.7では{1/1.2}≒0.83となる。実害が恐らくないとみなして{1/4(1-α)}=αと近似したものであろう。
*5 これらについて、比較的分かりやすく1960年前後における実験結果を紹介しているのは文献23)である。