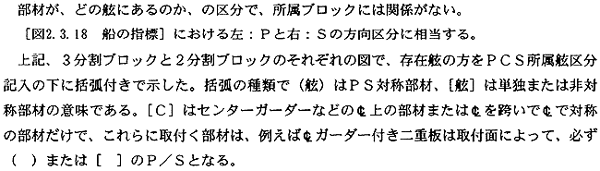曲り外板は、船体線図で示されるモールドラインで曲げ加工される。板は外逃げであり、船体内面=骨付き面をマーキン面とする。したがって:-
[図2.3.23 逆反り外板の曲げ]に示すような場合、下曲げとなる。そこで実際の曲げ加工は、最初にマーキンを裏回しして、裏からプレス押し/線状加熱するのである。このために凹面当ての粗曲型を別途作成している。粗曲型は線図から板厚分差し引いて作ることもなければ、見透しも要らない。仕上げが、マーキン面当て曲型で見透して行われるからである。この場合の凸面当て(仕上)曲型の方が、正規の曲型なのである。ここでも主眼は、精度である。
同じく下曲になるものにFc.PLがある。[図2.2.3 曲加工記号の表示位置]の●Fc.PLのR曲げ、[図2.2.11 S曲りFc.PL]、[図2.2.12 斜行Fc.PLの曲げ]に見るように、取付線マーキン優先であるが、この場合は、プレスが横押しで、曲型も当て位置指定はないか、あっても凹面当て曲型が使えることが、下曲を問題なくしている。
2.4.2 舷区分
構造部材は、一般に両舷対象で、型定規も片舷を作成すれば、両舷に使える。そのことは簡単なのだが、部材のまとめ(物流)、組立分類、など目的の異なる仕分からは、舷の取扱いには、区分が必要となる。
●所属舷
部材が、どちらのブロックに所属するか、の区分である。
幅方向が、中央と両舷に3分割なら[図2.3.24 3分割ブロックの舷区分]に示すように、左舷:P、センター:C、右舷:Sの所属になり、一般にPSは対称。
幅2分割なら[図2.3.25 2分割ブロックの舷区分]に示すように、左舷:Pまたは右舷:Sへの所属で、センターはどちらかに含まれる。したがってPS非対称となる。
●存在舷