
(B)海運事情と保有船主の実態
他の南米諸国と同じく、アルゼンチンも植民地であったため、スペインとの交易を通じてその海運業が発達した。
1810年にアルゼンチンがスペインから独立後は、軍事的な見地からも自国の海運業の発展は重要であったといえる。
1960年以降には、自国船優先主義など海運業を保護する政策が次々と打ち出されて、自国船舶による貿易の拡大とそれによるアルゼンチンの経済発展が図られてきた。
強い海運業が経済発展の基盤となるとの観点から推進された政府の保護政策により、海運業はかなりの成長を遂げたこともあったが、現在は厳しい自由競争の中であまり動きが活発でない。
1960年代に自国船保護のために、輸出入貨物の50%は自国船で輸送する方針を打ち出したが、第二次世界大戦後のアルゼンチンの海運政策は、この自国船優先主義政策以外には余り採られていない。
この自国船優先主義政策はあまり効果が上がらず、この30年間に形骸化し、実情に合わなくなり、1991年に内航沿岸、内水路全ての分野にわたって、自国船優先主義政策は撤廃されている。
自国船優先主義による国益の保護よりも、近年、貿易量の拡大による経済発展の方が重要との認識が高まり、アルゼンチンでは港湾局の民営化、港湾修復に重点がおかれている。
また、貨物輸送量の拡大を図るため、貨物のコンテナ化を促進する政策が出されており、パナマックス型コンテナ船の需要が近年高まっている。
自国船優先主義の撤廃により、海運界の流れは急転換し、自由化政策の下で競争力の無いアルゼンチン国営海運会社(ELMA社など)は、業績が悪化し民営化を余儀なくされている。
今後とも政府が再びアルゼンチン海運業を保護するような政策をとることは期待できず、アルゼンチン海運会社の国際海運市場での成長は、厳しい状況におかれている。
アルゼンチンが、今後国際海運市場で成長することは難しいと思われるが、国内、特に南部パタゴニアとの輸送、ラプラタ〜パラナ川水域の河川輸送、メルコスールとの貨物輸送など、今後とも必要である。
特に、アルゼンチン〜ブラジル間の海上輸送は二国間協定により、両国籍船社のみに限定されており、外国海運会社による輸送は許可されていないため、この分野でアルゼンチン海運会社が生き残っていける可能性はある。
そのためにも、アルゼンチン主要港の効率化、設備の近代化が極めて重要になってきている。
一方、ラプラタ〜パラナ川、また近年はパラナ川およびパラグアイ川の活用について注目されており、規模は小さいが今後の河川域の開発、設備の整備が整えば、アルゼンチン海運業界の今後の主要ビジネスとなりうる可能性はある。
アルゼンチンの主な港としては、ブエノス・アイレス、バイア・プランカ、ラ・プラタ、ロサリオのほか約10港あるが、近年各港の民営化が進行中である。
その主要港の貨物取扱い状況は、次の通りである。
(1)ブエノス・アイレス港
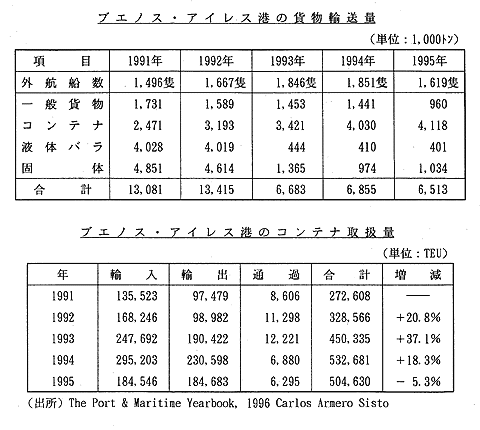
なお、1996年のコンテナ取扱量は、530,346TEUであった。
(2)バイア・ブランカ港
1995年の貨物取扱量は、穀物バルク430万7,686トン、液体バルク157万9,991トン、一般貨物70万4,104トンであった。
穀物バルクのうち、麦の輸出が232万3,506トン、とうもろこしの輸出が64万7,124トンを占めており、液体バルクのうち、125万8,562トンが液体燃料、21万6,864トンが液化天然ガス、6万7,210トンがエチレン、5万1,752トンが原油、3,128トンがナトリウム化合物であった。
一般貨物については3万258トンの貨物が魚類の積み下ろし、2万3、650トンがポリェチレンの輸出であった。
(3)ラ・プランタ港
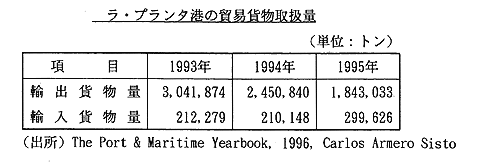
1995年の総貨物取扱い量は、461万9,837トンで、うち、53.6%(247万7,178トン)が液体燃料などのトランジット貨物、40%(184万3,033トン)が輸出貨物、残り6.4%(29万9,626トン)が輸入貨物であった。
(4)ロサリオ港
1995年の貨物取扱い量は、196万6,506トンで、うち73.26%(144万815トン)は輸出貨物、17.96%(35万3,180トン)は輸入貨物、8.77%(17万2,511トン)はトランジット貨物であった。
出入港船舶数は219隻、バージは103隻であった。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|