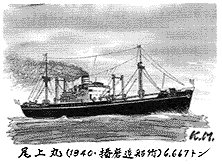絵で見る日本船史
尾上丸(おのえまる)
我が国の日印航路は、古く明治26年11月7日に、神戸出帆の広島丸を第1船として日本郵船ボンベイが孟買(ボンベイ)航路を開設し、印度棉花の輸送を手がけたのが最初で我が国遠洋定期航路の嚆矢(こうし)と云われる。
日本郵船ではかねて当時の印度首府カルカッタにも航路の開設を計画したが、続く日清日露の戦役で実現の運びには至らなかった。
日露戦争後の明治44年9月漸く(ようやく)カルカッタ航路の開設となり16日神戸出帆の仁川丸(じんせんまる)が第1船で、続く広島丸等5隻が就航し月2回配船、途中門司、上海(シャンハイ)、星港(シンガポール)、彼南(ペナン)と蘭貢(ラングーン)にも寄港した。
当時同航路は英印(ピーアイ)社、印支(インドチャイナ)社及びアプカー社等が同盟を結成し、強固な地盤を誇り激しい競合を余儀なくされ、更に同盟側の色々な妨害を受け乍らも日本郵船は起点を横浜に延長、就航船も6隻に増すなど厳しい経営に堪えていた。
しかし大正3年第1次世界大戦の勃発で形成が著しく好転、逆に同盟各社の経営不振が目立ち始め、大正7年英印社は遂に日本郵船に妥協を申し入れ、同年3月新同盟規約の締結に至り、6年有余の烈しい争いに終止符を打ち日本郵船の目印航路は、安定した運航と順調な経営を確立したのである。
昭和12年当時の就航路は何れも船齢20年以上の鳥取丸、対馬丸等老齢船8隻で、早期代替船の建造要望が各方面から叫ばれた。
昭和14年半ば、日本郵船では相生(あいおい)の播磨造船所で建造中の鏑木(かぶらぎ)汽船発注の貨物船12隻に着目し、交渉の結果現役就航巾の豊岡丸(とよおかまる)と常盤丸(ときわまる)の2隻を、見返り船として即刻譲渡する事を条件で買収し、興津丸(おきつまる)、尾上丸(おのえまる)と命名した。
尾上丸は総屯数6,667、主機は石川島製2段減速タービン1機5,429馬力で最高速力17.7節、全長123.5米、幅17.9、深10.6船倉には前後檣と2組の門型揚貨柱(キングポスト)があり6紺の載貨装置(カーゴーギア)と重量物25屯吊1組、郵便庫(メールルーム)と冷凍貨槍完備(リーファカーゴスペース)の船であった。
昭和15年4月横浜カルカッタ航路に就航以来好成績で活躍したが、翌16年8月27日太平洋戦争の開戦3ヶ月前海軍に徴傭され、三菱神戸造船所で海軍監督官指示の下、軍用船への改造が施工され船胎内に木製内張(ウッドウンシーリング)と冷却装置(クーリング)装備等で3ヶ月を費やし完成した。
12月5日呉に回航し開戦前日の七日、呉鎮守府所属連合艦隊付の給兵船に任命されたのである。
因に(ちなみに)太平洋戦争に際し大型貨客船、貨物船、漁船等450隻余の民間商船が海軍に徴傭され、特設空母、巡洋艦、砲艦、駆潜艇、哨戒艇等として活躍し、緒戦時各地の華々しい戦果を陰で支えていた。
その中特設運送船は7種類あり給油船、給糧船、給兵船、給水船、雑用船等と海軍艦艇への種々補給任務に当ったが、戦時に最も必要な砲弾や爆薬類を運ぶ船を給兵船と称し尾上丸もその指名を受けた。
乗組員の間では給兵船を移動火薬庫と渾名し(あだなし)、徴傭商船中全部で13隻指名され、日本郵船は尾上丸と鳴門丸の2隻で、各船其他の想像も及ばない辛労辛苦を体験、終戦迄に12隻全船が撃沈された。
翌17年2月のバタビア沖海戦には連合艦隊に随伴し、セレベス島ケンダリーに、同6月のミッドウェイ海戦はトラック基地に出動、更に8月からのガダルカナル作戦ではラバウル基地に出撃した。
同年10月22日ニューアイルランド島附近で米潜の魚雷を受け中破、ラバウルで応急修理後、呉に帰還し本格的修理が行われた。翌18年3月給兵船任務が解除され徴傭船から裸傭船に変更となり、乗組員は海軍々人と交替した。
その後海軍輸送艦となり呉からトラックやラバウル方面で活躍中、同年11月26円夜半ラバウル北西370浬の洋上で機関室に米潜ラトン号の魚雷を受けて沈没、3年8ヶ月の短い生涯を終った。
松井 邦夫(関東マリンサービス(株)相談役)