プレジャーボート等の安全対策について
レジャー活動は、愛好家自身が自らの自覚と努力によって必要な海事知識や技術を習得し、安全に対する認識を十分に持って行うべきものでありますが、前記のとおり、事故の原因は初歩的な知識・技術の不足等基本的事項の欠如によるものが依然として多くなっています。
海上保安庁では次のような海難防止対策を実施しています。
(1)愛好者に対する安全指導海上保安庁では、愛好者の安全意識の高揚を図るため、従来から海難防止強調運動を展開しているほか、ビデオ、スライド等の教材を使用した海難防止講習会、海上安全教室、訪船指導等を実施し、海事関係者のみならず広く国民に対し海難防止思想の普及、高揚を
図っています。
また、プレジャーボート、水上オートバイおよび遊漁船については、その種類ごとに海難防止のた.めの順守事項を取りまとめた。パンフレットを作成し、訪船指導等の際や関係団体を通じて配布する等きめ細かな安全指導を実施しています。
(2)ボート天国の実施および海上行事への協力
海洋レジャーの安全思想の普及および高揚ならびに技術およびマナーの向上を図るため、都市部港湾等において小型舟艇等が遊走できるよう休日等の一定時間、一般の船舶の航行や停泊を制限する海域を設け一時的に海域の開放を行う、いわゆる「ボート天国」を実施しています。
また、海洋レジャー行事に関する一般市民への窓口として、全国の各海上保安部署等に「海洋レジャー行事相談室」を開設し、一般市民からの海洋レジャー行事に関する問い合わせ・相談への対応や海洋レジャー行事の安全な実施に関する助言等を実施しています。
(3)関係団体の充実強化
初心者をはじめとするすべての愛好者にまで幅広く安全意識を浸透させるためには、民間団体による自主的な安全活動の推進が不可欠であり、このため、全国各地に五つの社団法人を含む四七の小型船安全協会等の団体が設立されています。
また、海上保安庁では、海上の安全パトロールなどのボランティア活動を行う人々として、海上安全指導員制度を推進しています。
<海難事例>
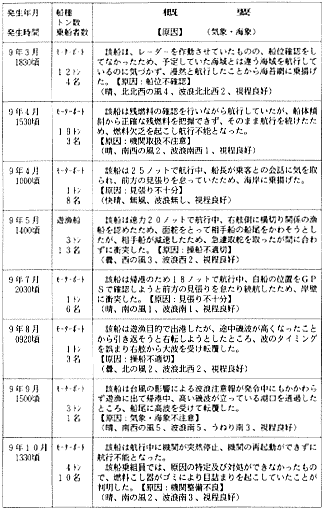
おわりに
プレジャーボート関係の新たな動きとして、海技免状において本年度から「五級小型船舶操縦士」の資格が新たに創設されることから、今後、小型船舶操縦士免許の取得者がますます増加することが予想されます。
また、現在プレジャーボート等の健全な普及・振興の妨げとなっている保管場所の不足に起因する「放置艇問題」についても、関係省庁における抜本的問題解決に向けた施策の実施により、将来的には保管場所の確保が図られることとなるものと予想されます。
こうした状況から、今後ますますプレジャーボート等の数が増加する環境が整い、またプレジャーボート等の活動がより活発化することが予想されますので、当庁としては「海難ゼロヘの願い」をスローガンに、安全思想の普及・啓蒙等の施策を中心にプレジャーボート等の安全対策を充実・強化していくこととしております。