絵で見る日本船史
白海丸(はっかいまる)
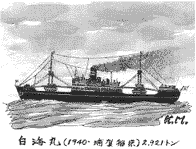
昭和14年3月末、北日本汽船は創業25周年を迎え、所有船38隻、約8万8千総屯に達し、航路も樺太、北海道から京浜、阪神、日本海方面のみならず、北鮮やウラジオにも航路網を拡張し、わが国の大手汽船会社10社に列するまでに至ったのである。
これより先政府の船舶改善助成法の第2次適用を受け昭和11年6月に耐氷型貨客船北洋丸を、更に第3次適用で翌12年6月に同型対氷姉妹船北昭丸を建造した。
昭和4年2月に第3代目社長に就任して世界的金融恐慌の最悪な海運不況期を克服し、太平洋戦争中に大阪商船と合併する迄の14年間在任された野村治一良社長の著書『わが海運60年』によれば、「北日本汽船としては樺太の開発による樺太と裏日本諸港間の活発化と共に、裏日本諸港と北鮮を結び、北満州と裏日本の最短距離を直結し、いわゆる日本海の湖水化を計画したのであった。(中略)
昭和7年の満州事変、それに続く関東軍の満州開発の積極化、さらに昭和12年の日華事変の勃発となり、日本海航路、特に北鮮を通ずる北満と日本諸港との関係は改めて見直されるに至った。かゝる情勢下に、軍は日本海航路を、満鉄の事業の延長として経営したい意向を示してきたが、海運業者としての私は勿論、主務官庁たる逓信当局も無論反対して対立した。
種々なる曲折を経て昭和14年10月北日本汽船の日満航路を根幹とし、それに満鉄と朝鮮郵船の2社が加わり3社連合して国策会社日本海汽船を設立することゝなり10月30日に創立、翌15年2月1日に営業を開始した」とある。
この企画に即応し昭和13年と14年に、新潟と敦賀から北鮮向けの定期船で、砕氷設備を持つ大型貨客船2隻を浦賀船渠で建造、夫々月山丸、気比丸と命名した。
さらに同13年秋、中型貨客船2隻の建造を決定し浦賀船渠に発注となったが、海軍側の注文で1番船の起工が大幅に遅れ、2番船が同年末に先に起工し、進水式も1番船より1ヵ月早く行なわれて射水丸が誕生した。4ヵ月遅れて起工の1番船は、翌年8月25日に進水し白海丸と命名された。
この白海丸は海軍が有事の際に北洋方面の特設砲艦として、使用する目的で砕氷型に変更を要請しその為起工が遅れたが、射水丸より逆に3ヵ月早く竣工した。
昭和15年1月26日に完成した砕氷型貨客船白海丸は、総屯数2,921、主機はレシプロ3連成2基で3,685馬力、速力最高17節、全長94.2米、幅13.7、深7.5、船客設備は1等12名、2等30、特3等68、3等468で計578であった。
完成後小樽に回航され、同地と樺太西岸の真岡と恵須取間の定期船として就航し、冬季結氷期にも砕氷の成果をあげて活躍した。
翌16年8月6日太平洋戦争の開戦4ヶ月前に海運徴傭船となり、佐世保鎮守府所属の砕氷船として冬季凍結の北鮮羅津根拠地に配置され、開戦1週間前の11月29日羅津沖で訓練中にソ連機2機の機銃掃討挑発を受け、3週間前の浮遊機雷による気比丸遭難事件と共に、新聞報道などで国際緊張を高めたが、8日後の太平洋戦争開戦でうやむやに葬り去られた。
翌17年1月にラバウル基地へ転属となり、南太平洋一円の前進基地巡回補給船として活躍した。
昭和18年3月横須賀鎮守府の運送船となり内地に帰還し、南海守備隊増強輸送の命を受け、4月26日鹿児島港からギルバート諸島行の南海第2守備隊600名を搭載し宇品経由、呉港を5月4日出撃したが、翌5月5日18時25分志摩半島大王埼の東南東43浬の地点で、米潜ソーフィツユ号の雷撃を受け、犠牲者124名を道連れに30分後に沈没した。
松井 邦夫(関東マリンサービス(株) 相談役)
前ページ 目次へ 次ページ