見学のできる灯台(4)
観 音 埼 灯 台
(社)燈光会
ハイキングに絶好の岬
観音崎は三浦半島の東端に位置し、対岸の房総半島の富津岬とともに東京湾の入口を形作っています。その間の浦賀水道は、わずか3.5??の峡水道で世界でも有数の船舶の輻輳する海上交通路の大動脈です。
バスの終点観音崎から海岸沿い、灯台への道は、自然の原生林のトンネルで、登りつめると視界が開け、東京湾口と太平洋が飛び込んできます。そこに白亜の八角形の灯台がそびえ、眼下の浦賀水道航路には灯台を指針にして東京湾に出入りするあらゆる種類の船を見ることができます。
灯台は悪天候以外は、いつも見学することができ、灯台資料館や備え付けの大型望遠鏡が楽しめます。
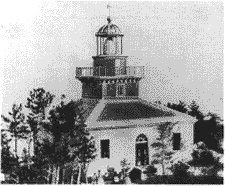
初の洋式灯台だった観音埼灯台、
関東大震災で倒壊した
日本で最初の洋式灯台
観音埼灯台は西洋文化のさきがけです。開国のとき、日本周辺はまさにダークシーで危険な海でした。灯台の建設がなによりも優先されたのです。幕府が米英仏蘭の4ヶ国と結んだ「江戸条約」でこのことが義務付けられました。
観音埼灯台は、この条約で建設を約束された八つの歴史的灯台のうちもっとも有名な記念的灯台です。
当時、灯台の技術がないので、フランスと英国に灯台建設の技術とレンズや機械の購入を依頼しましたが、徳川幕府の崩壊により明治政府がこの仕事を引き継ぎ、横須賀製鉄所(造船所)お雇いのフランス人首長フランソワ・レオン・ヴェルニーの手によって、明治2年1月1日、わが国最初の洋式灯台として誕生しました。
当時の建物はレンガ造りの四角い洋館建で、屋上に灯塔を設けたフランス風の優雅なものでした。
灯台の管理は、横須賀製鉄所があたり、万蔵、安次郎の2人の灯明番をおいたと記録されています。
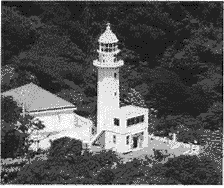
現在の観音埼灯台
関東大震災と太平洋戦争
使用されたレンガは6万4千6百枚、ヴェルニーの伝授で横須賀製鉄所で焼き上げられました。しかし大正11年の地震で倒壊し、翌12年コンクリート灯台に生まれ変わりましたが、同年9月1日の関東大震災で被災し、再度大正14年6月1日建て替えられました。これが現在の灯台で3代目に当たります。
灯台の光は、14万カンデラで約37??届きます。
太平洋戦争では、関東の太平洋岸の大型灯台は軒並み攻撃され被災しました。しかし、この三代目の灯台だけは東京湾口で最も重要なところにありながら不思議なことに全く無傷だったのです。何か特別の意図があったのかもと考える人もあるとか。
灯台へのアクセス
○ JR横須賀線横須賀駅からバス35分、観音崎下車、徒歩10分
○ 京浜急行浦賀駅からバス15分観音崎下車、徒歩10分
(はとバス=東京駅南口発)
照会=燈光会観音埼支所
電話0468-41-0311
前ページ 目次へ 次ページ