
表5には、歩行能の指標として加齢変化の認められた歩行速度、歩幅を目的変数に、年齢、身長、および平衡性指標としての開眼片
足立ち、A-P%、他の体力指標としてのステッピング、体前屈、垂直とび、握力、息こらえを説明変数とした重回帰式をstepwise法で求
めた結果を示す。垂直とびは、男性においてはすべての回帰式において投入された唯一有意な説明変数であり、その寄与率(R2)は
自由歩行の歩行速度で19.1%、歩幅22.3%、最速歩行の歩行速度35.0%、歩幅42.8%であった。また、女性においても、垂直とびは自由
歩行の歩幅以外の回帰式で最初に取り込まれた。女性の場合、他の有意な標準偏回帰係数(β)は、最速歩行では速度、歩幅ともに、
身長、ステッピング、A-P%であり、自由歩行の速度では身長、年齢、ステッピングである。しかし、自由歩行歩幅では、垂直とびは有意
な説明変数ではなく、式に投入されたのは身長、年齢、ステッピング、A-P%、息こらえの順であった。女性での各重回帰式の寄与率
は36.1〜47.1%であった。
表5 重回帰分析の結果
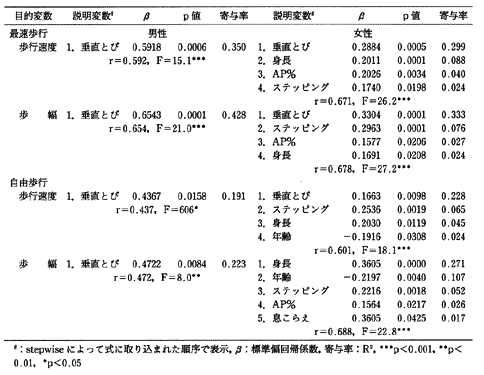
論 議
1.標本集団としての本対象者の特徴
研究では、母集団と偏りのない標本抽出が望まれるが、体力測定を伴う調査には、もともと健康や体力に関心の高い者が参加
する傾向が強い。健康づくり事業(健康教室やスポーツ教室など)への参加者を約半数含む本研究において、このような傾向のあ
ることを否定するものではない。実際、同時に測定した体力診断バッテリーテストの結果をこれまでに報告されている地域の
一般高齢者のもの16)と比較すると、男女ともに各項目において年代別平均値を上回っている。ただし、その差(絶対値)は比較的
小さく、標準値(1:低い、2:やや低い、3:普通、4:やや高い、5:高い)に照らすと、本対象者の値は3(上限値に近い)〜4(下限値に近い)に
区分される。したがって、散歩や体操、あるいは高齢期になって始めたスポーツなど、何らかの運動習慣を持つ者が多い本対象者
で示された体力は、この年代で無理なく目標にできる値でもあり、研究結果は高齢者の体力づくりの見地から興味深い。
一方、老化研究では、生理的な老化と病的な老化をできるだけ分離し解析することが求められる。しかし、高齢者を対象にした
フィールド調査で厳密にこれを判定区別することは困難である。今回は、事前に行った面接調査より中枢神経系および運動器
系に特別な支障を有しない者を分析対象にした。分析から除外されたのは、脳卒中既往や明らかな耳科的疾患、目眩の既往、パー
キンソン、人工関節の装着などであった。ただ、中には膝や足腰の痛みを訴える者もあったが、そのために測定に支障を及ぼすこ
とはなかった。したがって、本研究では、健康状態がほぼ良好で、体力が歳相応かそれ以上の高齢者を対象にしており、平衡機能や
歩行能の生理的老化を論ずる資料として十分耐えうるものと考える。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|

|