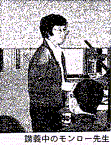
モンロー先生の講義から
1.悲嘆について
日常生活に何か変化が起こると私たちはストレスや喪失感を体験する。それが結婚や妊娠,あるいは試験に合格するといったよい体験であってもストレスを感じる。また離婚や子供の独立など,生きていく過程でさまざまな変化を体験し,それらが重なると身体面,精神面に影響を与える。なかでも愛する者の死は大きな変化,喪失の体験であるが,緩和ケアに携わる者は,死だけが喪失ではないことを覚えておくべきであるというお話から悲嘆についての講義が始まった。
悲嘆(Grief)とは,個人的な喪失の体験であり,感情的なものあるいは身体的なものとして表現される。そして哀悼や服喪(Mourning)とは喪失の社会的な表現で,社会や文化によって表現のされ方が異なる。ほほえみで,逆に自己を傷つけることで哀悼を表現するなど,各文化に特有の表現の仕方があるが,悲嘆の研究者によれば死別を体験したものにはある種の苦悩があることは共通するようである。
悲嘆については欧米の文化を基礎として理論化されたものがある。その一つとして,J.Bowlbyの「愛着の理論」がある。すなわち子供が親から離され,泣き叫び,混乱し,そして新しい対象を探し,成長していく。その過程を悲嘆と関連づけて理論化したのがC.M.Parkesで,彼は喪失の苦しみを表現することは健全なことであり,それを抑制し,表現しないのは不健全であり,後の人生にマイナスの影響を与えると述べている。
Parkes,またW.Wordenは,悲嘆の段階モデルを作って,感情的な痛みが大きい段階から小さな段階へと移行するとし,愛する人の死に出会うショック,悲しみ,罪悪感や後悔,そして新しい関係を樹立できずに無力感や自信喪失,うつ状態などを体験しながら,最終的には痛みの低い状態へと到達する。前進したり後退したりしながら自分の人生を再構築し,新しい人間関係を作り始める段階へと進んでいくと述べている。WortmanとSilverは,Parkesらのいうように高いレベルから低いレベルヘと移っていく場合もあるが,もともとそれほど高くない人,逆に高いまま続いている人もいるというように三つのグループで理解している。
いくつかの悲嘆についての考え方を紹介した後.先生は,悲嘆はいつも表現されるものだろうか,必ずしもそうではないのではないか。悲嘆の表現は人それぞれで,死別の前にすでに悲嘆を体験している人,時間やサポートがなくて表現できない人,周囲からの評価を得る形で行動する人等々,悲嘆とは非常に個人的なものである。したがって悲嘆へのケアにおいては,亡くなった人との関係,これまでの死の体験,サポート体制,文化的背景など,まずその人をよく理解することが重要であると述べられた。
次に最近の研究としてStroebeらの調査報告を示された。彼女によれば人は悲嘆に直面するとともに避けることも重要であるとしている。亡くなった人のことを考える時間も必要であるが,考えないで過ごしたいと思う時もある。両者をいったりきたりするのが自然であり,どちらかに片寄るのが問題である。また,KlassとSilvermanの理論でも,亡くなった人を忘れようとするのではなく覚えておくことの重要性が指摘されている。その意味で日本の祖先をまつるという文化はよい対処の仕方ではないか。悲嘆はずっと続くものではないが,なくなるものでもない。思い出すことの大切さを述べているのがT.Walterで,亡くなった人にまつわる物語を語ってもらう方法も有効で,その語りの中から新しい人生に必要なものも発見できる。
ところで,悲嘆のケアは死別後から始まるように思われるが,亡くなる前のサポートが重要で,死別後の悲嘆に影響する。最近の研究によると,死別前によい関係を持てた場合には悲嘆は健全なものとなる。その意味でも死別前にリスク評価をし,心理・社会的介入をしていくことが重要となる。われわれは専門家として情報を提供したり,ケアに介入できるよう指導したり,一緒にいられるようアドバイスするなど,死別前の援助の必要性にも触れられた。
前ページ 目次へ 次ページ