(1)「松泉学院」(知的障害者更生施設) 説明:光増昌久施設長
最近は、重症心身障害の人の入所の増加や精神障害を併せ持つ人が多くみられるようになってきており、以前と比べて更生施設の利用者の傾向にも変化が生じている。障害の程度としては、重度の人が7割程度を占める構成である。124人の利用者のうち、軽度の人は18人程度である。
そのような中、松泉学院では、現在毎年4人ずつが松泉学院からグループホームへ移行している。
現在、松泉学院がバックアップ施設となっているグループホームは8ヵ所。今年あらたに2ヵ所の申請を行っている。
地域で生活している人の中には30年来の施設入所者である40代、50代の人もいる。
松泉学院では、地域生活を希望する人をなるべく尊重して、地域への移行が行われている。
北海道は、障害者年金だけでも何とか生活できるだけの物価水準にある。しかしその一方では、地域生活展開の歴史もそう長くはなく、現在、松泉学院にも地域で暮らすことができる人はたくさんいるが、すぐには進んでいかないの実状である。
光増施設長のお話の中に、施設で暮らす人の中には、「親にだまされた」と思っている人がいるという言は印象的であった。
松泉学院では、施設内の限られた資源の中で、生活の質を高めるために、様々な取り組みを行っており、施設の生活環境は4人から2人へ移行している。
地域で生活するに際しては、松泉学院のある銭函の街は工場等がたくさんあり、その意味では恵まれているということである。
松泉学院では、地域への移行の一つのステップとして、参加希望者が職場実習を行っているが、中には午前中に掃除だけして帰ってくる人もいる。
■松泉学院がバックアップしているグループホーム
◎グループホーム「泉寮」国認可 平成7年開設
アパートの2階部分を利用。1階には松泉学院が運営する福祉ショップがある。
入居者は女性3名。
◎グループホーム「陸寮」無認可 平成9年5月開設
一戸建て型。入居者は3名。
松泉学院を通所利用している人、一般就労している人がいる。
◎グループホーム「翼寮」現在認可申請中
一戸建て(築20年)型。
◎グループホーム「桂岡寮」国認可 平成6年開設
一戸建て型。
◎グループホーム「ひまわり寮」
入居者は男性4名。唯一の世話人同居型である。ただし、世話人は土日休みで、その日は、コンビニエンスストアの弁当やレストランを利用している。
◎グループホーム「桜海寮」
入居者は男性4名。
◎グループホーム「ツグミ寮」
一戸建て型。男性4名。2階に3部屋あるが、広さが違うため(8畳が2部屋、4.5畳が1部屋ある。家賃で5,000円の差をつけている。)、1階は1名。
◎GH「松海寮」
一戸建て型。入居者は男性2名。世話人はいない。食事は松泉学院のものを利用している。
◎施設敷地内生活寮
前の職員住居。1階は男性、2階は女性が利用している。
(2)「大倉山学院」(重症心身障害児施設) 説明:高谷直秀看護部長
大倉山学院は、道内では初めての重症心身障害児施設として、昭和40年に設置された。利用者の多くは、重い知的障害や運動機能障害とともに精神医学的症状(てんかん・情緒障害・精神運動性興奮・最強度の行動障害等)を併せ持つ重症心身障害者が多く、医学的な支援のもとで生活している。
現在、入所者は160名。状況として退所していく人はきわめて少なく、「終身入所」の感がある。また、このことから、制度上は児童施設の位置づけであるが、利用者の年齢はどんどん加齢しており、男性の平均年齢は40.3歳、女性は37.2歳という構成である(全体の平均年齢は38.9歳)。
職員体制は、利用者160名に対し、職員143名で、職員比率は1.12と国の基準を上回る配置となっている。
第一療育棟から第三療育棟まであり、それぞれの障害の状況に合わせて、利用者の編成が行われている。
[第一療育棟]
(Aホーム)健康面で比較的安定している男女の混合、障害の程度も混合の編成となっている。
(Bホーム)比較的生活面での自立傾向が高い男性利用者。
[第二療育棟]
(Aホーム)比較的生活面での自立傾向が高い女性利用者。
(Bホーム)健康面で比較的安定している男女の混合、障害の程度も混合の編成。
[第三療育棟]
(Aホーム)重症の運動機能障害を持ち、医療的な援助を必要とする。
(Bホーム)健康面で比較的安定している男女の混合、障害の程度も混合の編成。 |
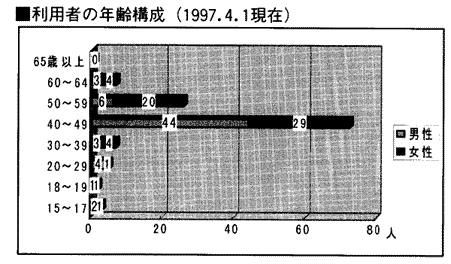 |