2) DN値の2値化による氷域の自動抽出
i) DN値による疑似カラー画像
SARの画像を構成する各ピクセルには輝度を表す数値が対応づけられており、RADARSATの場合は16-bit unsigned shortと表現される整数値(0〜65,5355)が割り当てられている。
もし、流氷と海面とで輝度分布が異なる(DN値の分布が異なる)ならば、ある特定のDN値(これを閾値という)を境にしてそれ以上のDN値を持つ領域とそれ未満のDN値を持つ領域とに分類することにより、流氷と海面を分離することが可能である(図17)。
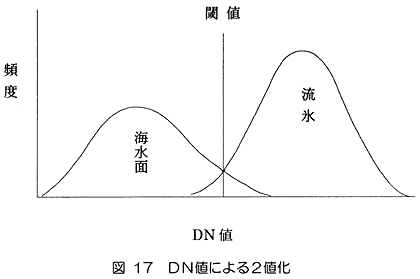
ここでは視覚的に判断できるように、閾値を境に2値化して白黒画像とする代わりに、DN値の大小に応じて小さい値(黒)から大きい値(赤)まで連続的に色を変化させてシュード(疑似)カラー画像として図18に示した。なお、原画像としては9×9ピクセルの平均フィルターをかけたものを使用した。これはスペックルノイズによって色調が乱れる影響を低減することを目的としたものである。
海面は黒、緑、黄、赤等に表現され、流氷は黒、青、緑、黄色、赤で表現された。原画像にみられた網走沖一帯の海面の白い模様は一面に赤く表現され、大きな氷盤と同じ色調となった。また、流氷についても原画像で黒く表現された部分は、シュードカラー画像では黒から青として表現され、ウトロ沖や知床半島東側に見られる海面と同様な色調となった。
この結果、どの様な閾値を設定しても必ず海面の一部と流氷の一部が同じに分類されてしまうことが判明した。