域人らの当時の風俗を反映した供養人群が描かれている。ウイグル文化芸術の宝庫と言われてるが、14世紀のイスラム侵入時の偶像破壊により、仏の顔面はつぶされ、20世紀初頭には外国探検隊により壁画が剥ぎ取られ完全な窟は一つもない。
主な窟と図のポイント: 第9窟「菩薩像」、第27窟「千仏」、第29窟「高昌国の楽器」、第31窟「誓願図」、第33窟「涅槃図・*各国王子挙哀図」、第39窟「涅槃経」、第54窟「佛頭部」
* 釈迦の涅槃を悲しむ西域諸国の国王や王子の顔が描かれている。
5) 交河故城(ヤールホト)
ウイグル族の言葉で、「ヤールホト」は「崖の城」を意味する。トルファンの西11?にある、その名の通り崖裾に二つの河が交わり、高さ30mの巨大な黄土の断崖の上に築かれた孤島状(木の葉型、空母の甲板型)の城(南北約1?、東西約300m)。天山北路と南路が分枝する地理的に重要なこの地に前漢時代に車師前国の都として城郭都市を築いた。7世紀に高昌国が滅びた唐の西州時代にはその5県の一つ、交河県となった。ウイグル高昌国時代の繁栄期をへて元代に衰退した。
城の中心に巾 3mの大道が南北に350mつづき、南側が住居地区、中央が官庁地区、北側が寺院地区となっている。城内の建物は硬い台地をくり抜いて造られており、その上に日干しレンガを補足的に使用してある。トルファンには仏教が1000年余り栄えていたため交河故城の中にも大小50余の寺院遺跡がある。大道の突き当たりに、かつての大仏寺がある。仏塔には多くの仏龕があり、その中に頭の欠けた座仏がある。地下の官庁街の遺構もある。
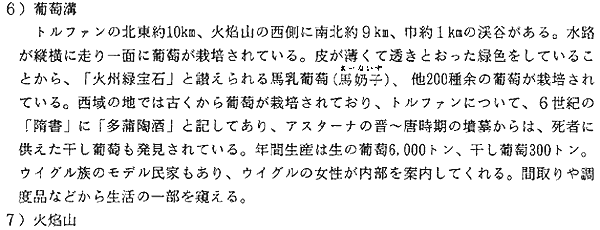
トルファン盆地の北側に東西に連なる全長100?余、巾9?の大山塊で、最高峰は海抜581m。露出層は地質年代の中生ジュラ紀と白亜紀、第三紀の赤色砂岩、砂岩礫と泥岩で、地殻の褶曲運動によって形成されたもの。ウイグル族は「キジルタグ」(赤い山)と呼ぶ。真夏の強烈な日光や夕日を受けて、全山が炎を出して燃えている様に見えるので、この名がある。「西遊記」で孫悟空が鉄扇公主と戦い、芭蕉扇で火炎を消して一帯を緑の沃野にかえた話は、この山に題材を求めたもの。
? 庫爾勒
コルラは巴音郭楊楞(バインゴル)モンゴル自治州の首府で、州の人口約95万人、市内周辺を含めた人口は、35万人、市内のみは約20万人。市内を孔雀河が流れる。近年に石油が出たために関連産業を始め工業化が進んでいる。町中心部に低・中層の近代的ビルが並ぶ。トマト、米、小麦、綿花などの農産物生産も盛んである。バインゴルは、蒙古語で「豊かな水のあるところ」