5/25(日)地域伝統芸能公演 松江市 くにびきメッセ 大ホール
●有福神楽(島根)●西中之条獅子舞(群馬) ●今治の継ぎ獅子(愛媛)
●綾子舞(新潟) ●チャンココ・五島ハイヤ節(長崎)●晋州劔舞・鼓舞(韓国)
15:00〜18:00
●有福神楽
島根県浜田市 出演/有福神楽保持者会
島根県指定民俗無形文化財
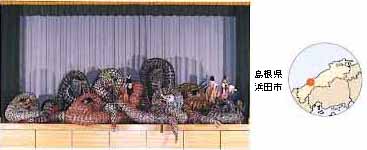
有福神楽は一月の八幡神社の祭りに演じられる石見地方の代表的な神楽です。江戸初期からのものと思われますが、かつては神職神楽だったのが明治以降は農民だけの娯楽性の強い華麗な奉納芸能になりました。舞台は神社の拝殿を常舞台として中央に天蓋を吊り、五色の切紙を飾ります。演目は三十二番。神楽・塩祓・神迎・帯舞・四神などの採物舞のほか、日本武尊・岩戸・大蛇・塵輪・鐘馗などの仮面による劇的な能を演じます。わが国の神楽でも最もテンポの早い人調子の囃子にのって激しく華やかに舞うのを特色とし、衣装も金銀の刺繍あり玉飾ありと豪華です。
●西中之条獅子舞
群馬県吾妻郡中之条町 出演/柴宮神社芸能保存会
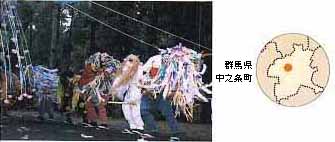
関東地方の代表的な獅子舞の形式である一人立ち・三頭獅子で、二匹の雄獅子と一匹の雌獅子が花の香りに誘われて集まり、花の香りをかぎ、花に酔って悦び戯れる様子を演じます。代表曲「女獅子かくし」では、笛、太鼓、鉦の囃子にのって、三頭の獅子の愛の葛藤となります。頭には五色の房をつけて威厳を保ち、腰には太鼓をつけての道中には、狐、猿、鬼などがからんでとても賑やかです。年々少なくなる獅子舞ですが、当地名物の空っ風の中、この祭りは今も健在です。毎年二月のこの祭りが終わると、上州にも春がやってきます。
●今治の継ぎ獅子
愛媛県今治市 出演/延喜獅子舞保存会
今治市指定無形民俗文化財

継ぎ獅子は、獅子舞の変形として今治市を中心に独特の姿で伝承されているものです。小太鼓、大太鼓、ところによっては鉦、笛も加わった囃子の響きにのって次々に肩に上がり、最上段では八、九歳の少年が獅子頭を冠ってシシノコをつとめます。獅子頭には雌雄があって、黒毛がオス、白毛がメス。華麗な衣装で、一肩上高く扇をかざして勇ましく獅子頭を振る少年の所作は「立芸の華」として観客の声援を一身に集めます。二百年近くの歴史を持つこの獅子舞は、伊勢神楽の流れを汲むといわれる勇壮な芸能で、演目も、悪魔払い。立芸・餅つきなど多彩です。
●綾子舞
新潟県柏崎市 出演/柏崎市綾子舞保存振興会
国指定重要無形民俗文化財
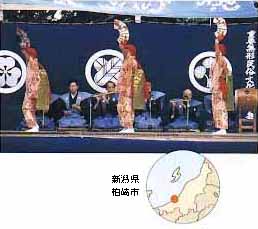
毎年九月十五日に、鎮守黒姫神社の秋祭の舞台で奉納されます。かつて京都の四条河原で出雲阿国が始めたといわれる歌舞伎踊りのスタイルによる歌舞伎狂言です。踊り手は少女で、頭にユライという赤い布をかぶり、振り袖又は緋色の袴姿に扇を持って、小唄に合わせて踊ります。踊り唄はすべて、さし・本歌・終の歌とに分かれ、終の歌では決まって「あれ出て見さい」と歌います。綾子舞は一人舞で、松の舞・かに舞・うずら舞など、天正狂言本と同じ曲名のものが多いのも興味深く、華やかな桃山文化の面影を残す貴重な伝統芸能です。
●チャンココ・五島ハイヤ節
長崎県福江市 出演/吉田チャンココ保存会・長手民謡保存会
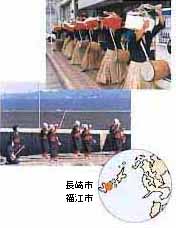
チャンココとは、盆の供養の太鼓踊の鉦の音からきたものと思われます。起源は古く、歌詞や衣装からは中国南部地方からの影響があるといわれます。五島列島最大の島である福江島では人月の盆には、チャンココのほか、かけ踊、オーモンデなどの大鼓踊が各地で踊られます。花笠をかぶり、半袖、長襦絆姿で腰にはビンロウやガマの葉でつくったみのをつけて踊る姿はどこか哀愁を帯びています。舞台では併せて、当地長崎に生まれ全国に広まったお座敷唄、五島ハイヤ節の陽気な踊りで島の生活が再現されます。
●晋州劔舞・鼓舞
記念公演(5月23日)をご参照ください。
●全国船のまつり写真展
会 場■くにぴさメッセ多目的ホール
協 力■(社)全日本郷土芸能協会
☆日本三大船神事コーナー
☆全国「船のまつり」コーナー