高齢社会の現在、元気なお年寄りが増たていますが、反面、若い人の間にも半健康人が多くなったと言われています。半健康人とは、健康診断や成人病検診では異常がないのに、肩こり、頭痛、不眠、冷え性など自律神経失調症に悩んでいる人のことです。ストレスの多い現代社会で失われていくあなたの健康をいま―度、自分の力で高めてみませんか。東洋の養生術で、体を動かして、病気にならないための自己管理をしていきましょう。

私たちの体の骨盤を中心とした腰部は、扇に例えれば要となる大事な“接合ポイント”で、体の中では一番負担のかかるところです。
「要の体操」はこの負担のかかっている「要」である腰部の諸関節や筋肉の“コリの鎧”を取り払い、柔軟でしなやかな腰を取り戻す体操です。体操は五動作からなり、 いつでも、どこでも行えるものとして、考案されています。
動作はできる範囲で無理をせず「丹田呼吸法(丹田とは、へその下の辺りを指す。東洋医学の考え方で、古くから養生術として伝わる呼吸法)を使って、のびのびと行うことが大切です。
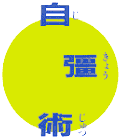
自らを彊(つよく)し、病気を治す「自彊術」は三十一の動作からなり、すべてを行うと、体の関節を延べ一万数千回も動かすことになります。全身を動かすことで「体力づくり」「成人病予防」「機能回復」に大きな効果を発揮します。
「自彊術」は大正後期に香川県に住んでいた、天才療術家・中井房五郎氏(故人)が考案した東洋の養生術の一種です。当時全国的に流行した体操でしたが、ラジオ体操のようなリズミカルな西洋式体操が普及するにつれて、いつしか忘れ去られていきました。
そんな中で「生命の貯蓄体操」の創始者である矢野順一(生命の貯蓄体操普及会理事長)は、この体操が単なる体力づくりに効果があるばかりではなく、成人病の予防や機能回復、内因性諸症状などにも効果が大きいことを自らの体験で実証しました。そして、昭和四十四年から生命の貯蓄体操の一つの種目に取り入れ、西洋医学と東洋医学の両面からの理論づけと 実技の指導法を独自に確立し、「生命の貯蓄体操」の一環として普及に努めています。

健康な体づくり、体質の改善には効果があるとわかつていても、長続きさせるのは困難なものです。でも、二人が互いに助け合いながら行えば、楽しさが増し、長続きさせることができます。
生命の貯蓄体操の中の組み体操は二人一組になって行い、全部で十五の動作があります。要の体操や、白彊術の各動作をやりやすくする他、自分で発見しにくい身体のゆがみや老化をお互いに矯正し合うことができます。
組み体操で大切なことは、双方が助け合いの精神によって一体になることです。補助運動を受ける人は感謝を、行う人は誠意を持ってお互いに信頼し合いながらすすめることが大切です。