
なお、観測データは通信レート4bpsのパイナリーコード(10bit)で受信され、インターフェイスを介してRS232Cコードに変換され、処理局のパソナル・コンピュータに転送される。コンピュータ内では受信時間とデータのチェック及び時系列ファイルの作成が行われ、端末からの呼び出しによりデータが転送される仕組みとなっている。
8)流星バースト
流星バースト通信(Meteor Burst Communication、MBC)は確率的に発生する流星の飛跡による低VHF帯電波(30〜100MHZ、多くは30〜50MHZ)の反射現象を利用した見通し外通信で、小容量で且つ数秒ないし数分程度の遅れを問題としないデータの伝送には、極めて有効な通信システムであると言われている(福田,1992)。図2.2.23に流星バースト通信の模式図を示すように、高度100km付近に発生した流星バーストにより2,000km以内の2点間で通信が可能となる。
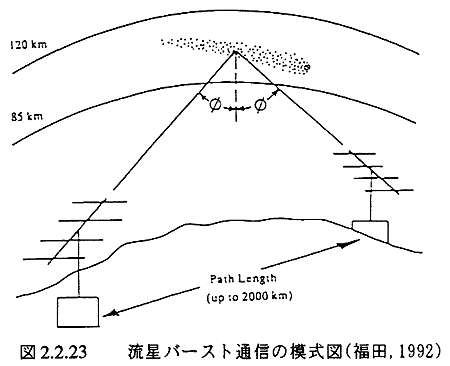
流星バーストの発生に日変動と季節変動が認められており、流星数の日変動は朝方極大、夕方極小、また、季節変動は北半球で夏季極大、冬季極小のパターンを呈し、平均発生間隔は10秒程度、さらに、流星バースト通信路の存続時間はUnderdenseバーストの場合、平均して数分の1秒の指数分布をなすと言われている(福田,1992)。なお、流星バースト通信調査研究会(1993)よりMBCの長所と短所を以下に取りまとめて示す。
「長所」
◎システムの構築が安価である。
◎運用が容易である。
◎信頼性が高い。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|