診は本症の早期発見に役だっていないと結論づけている。
これまでも胆汁酸、直接型ビリルビン、リポブロテインXなど種々のスクリーニング法が提案されてきたが、いずれも実用には至っていない。そこで松井らが1994年から栃木県と埼玉県で、約5万5千人を目標に便色調カラーカードによるパイロットスタディを開始し、開始後2ヶ月弱で2例の本症がスクリーニングされた。
筆者は以前、1ヶ月健診を行っていた際に、神奈川県からの里帰り分娩の母親が持参した母子手帳の1ヶ月健診のぺージに「便の色はレモン色、○○色…」と具体的な色が記載されているのを見た。青森県の母子手帳は「便の色は何色ですか」としか記載されておらず、加えて実際に1ヶ月健診時に便色が記入されていない例が非常に多く、筆者はその項目の意義に疑問を感じていたために、神奈川県の母子手帳に新鮮な感動を覚えた。そうした時に松井らの報告に触れ、神奈川県の母子手帳以上に具体的かつ簡便な方法と思われ導入するに至った。
図4に当科でのマススクリーニングシステムを示す。乳児は産科退院前と1ヶ月健診で2度小児科医の診察を受け、健診でカードによるスクリーニングを受ける。これで異常があれば再受診させ便を確認し、必要があれば検査を行う。本症がより強く疑われた場合、さらに高次の医療機関に紹介する。健診の前後に便色調に異常が見つかれば親が当科へ連絡してくることも期待している。その意味でこのシステムにおいては、稀な疾患である本症に対する親の認識の高揚が最も需要であると思われる。
今回我々が行ったアンケート調査では、当地のような僻地においても本症に対する関心の高さがうかがわれた。しかし、決して少ないとは言えない数の母親が乳児の便色に関心が薄いと思われ、母子手帳の便色の記入もれの多さを加味すると、本症と便色の関連性の認識は乏しいことが予想される。すなわち、アンケートの質問(5)の結果から、カードの利用は、親の認識の中で本症と便色を結びつける非常に有効な教育手段であると思われた。
しかし、カードの利用についてはいくつかの問題点もある。便色の評価はあくまでも親であるから、特にカードを持参するのを忘れるような親の場合、こちらが考えているほどカードに意義を感じておらず、丁寧な便色の評価がなされていないかもしれない。また、当院では診断のための検査機器、技術に制約があり、マンパワーにおいても負担が大きい。そして現状では当院のシステムは、高次医療機関との連携すなわちバックアップ体制が整わないままスタートしたことになる。スクリーニングの目的は早期発見、早期治療であるから、システムの中のバックアップ体制の充実は今後の重要な課題として関係機関への働きかけを行っていきたい。
当院では本法の導入からまだ期間が短く、胆道閉鎖症はスクリーニングされていない。しかし、先に述べたように本法の簡便さと親への教育効果は何物にも代え難く、今後もスクリーニング対象数を蓄積してより多くの親への啓蒙を図るとともに、松井らが推進する本法の確立に寄与していきたいと考えている。
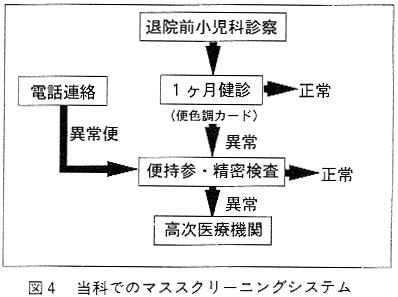
VII.結語
1.本法の導入により胆道閉鎖症は未だスクリーニングされていないが、その後の観察でも発症者はいなかった。
2.本法は便色調を判断するのに簡便で良い目安となる。
3.僻地医療の中で本法を進めていくためには、高次医療機関のバックアップ体制の充実が必要である。
本論文の要旨は、第111回日本小児科学会青森地方会(1995年11月、青森市)で発表した。
最後に御校閲いただいた弘前大学医学部小児科学教室横山碓教授と本法の導入にあたって無償でカードをお譲りいただき、数多くの御助言を賜わりました自治医科大学小児科学教室松井陽氏に深く感謝致します。