
3)患者の所在別人数(図-10)
患者の所在別では自宅が38人で、老人ホーム等施設に入っている者が62人であった。
施設入所者の内訳はテンカン専門の国立療養所寺泊病院に入院していた患者が5人、老人ホーム入所者が38人、老健施設入所者が19人であった。
4)初診時の年代別人数(図-11)
20代の2人と30代の1人はいずれもテンカン専門の国立療養所寺泊病院に入院していた患者である。
70才以上の患者の合計は83人で、83%を占めている。通院できる患者でも70才を超える高齢者は隠れた疾病を抱えているため、歯科的な処置を行うに際して、細心の注意を払っているが、通院の著しく困難なこれら高齢者はまさにハイリスクな患者ばかりということになる。
5)初診年別人数(図-12)
1992年から急に人数が増えているのには理由がある。それも、その年の5月からである。この月の初めに内科の先生が病気のために入院し、往診用の車があいたからである。残念なことに、この内科の先生は2ヵ月後に肝臓癌のため亡くなった。その2ヵ月後の9月1日から新しい内科の先生が診療を再開したが、この時点で、歯科でも往診用の車を使えるシステムにしたので、それ以後も歯科訪問診療の申し込みはコンスタントにある。
1996年7月からは内科、歯科のそれぞれが往診用の車を持てるようになった。また、1994年は前年の3倍を超えている。これにも理由がある。在宅寝たきり老人に入浴サービス等を行っている町のヘルパーを通して、入れ歯の状態が悪くて困っている人に積極的に歯科訪問診療を勧めてもらった結果、このように件数が増えた。
1996年の分は8ヵ月間のものであるが、57人と前年の4.4倍近くの初診患者数となっている。これは、町当局はじめ関係する方々のご理解により、今年の1月から町にある入所者150人の「養護老人ホーム」とベッド数128床の「老人保健施設」に歯科訪問診療をすることができるようになったからである。ポータブルの歯科治療器械を購入してもらい、訪問先でも診療室における治療と同じことができるようになったことが、この二つの施設に歯科訪問診療を自信を持って行う大きな力となっている。車といいポータブルの歯科治療器械といい、道具や手段がいかにいままでがまんしていた患者に、幸せをもたらすかといういい例である。
ポータブルの歯科治療器械の購入は、過去10年間における延べ360回の歯科訪問診療の実績が認められ、県からの補助金を得て、昨年の12月に実現した。歯科専用の往診車の購入は、今年の1月から5月の5ヵ月間に延べ429人に対し歯科訪問診療をした実績が町当局に理解され、実現した。
1996年の初診患者57人のうち34人は老人ホーム入所者で、19人は老人保健施設入所者で、残り4人が在宅寝たきり老人である。
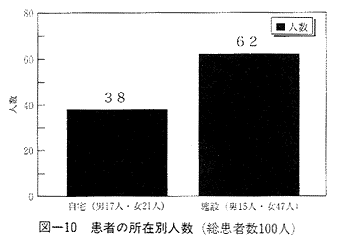
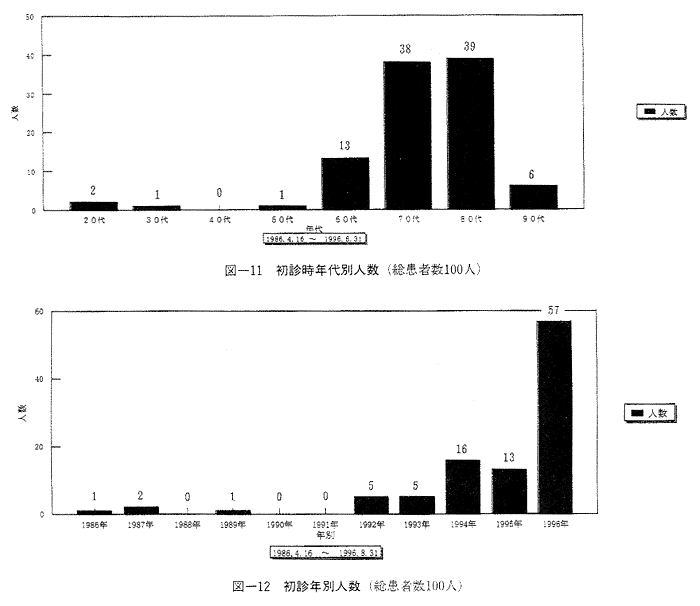
前ページ 目次へ 次ページ
|

|