
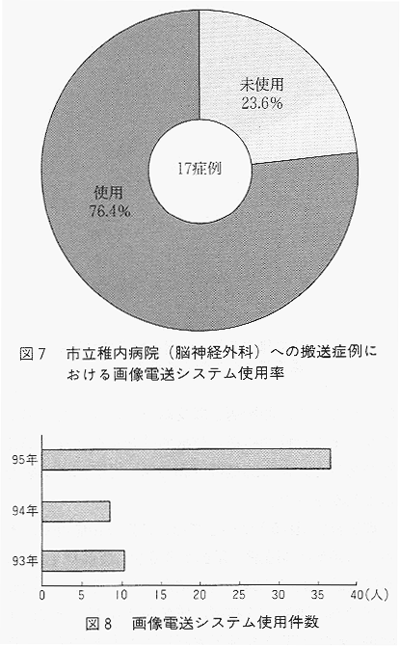
急搬送時の適応を正確に見極めることが同システムにより可能になった。すなわち、出血部位、出血量、骨折の有無、骨折脳実質への損傷程度など、こちらで頭部CTや単純X線写真などの情報を依頼先の脳外科医へ電話連絡を行った場合、こちらで伝えたい情報が100%伝わるか、CTの読影に誤りや不十分なところがないかなど双方の医師に不安が生じる。しかし、“百聞は一見にしかず”という諺があるように、画像電送システムを使用すれば、写真を供覧しながら説明することが可能となり、迅速かつ的確に患者の状況を伝えることができ、依頼先の医師からも適切な指示を仰ぐことができる。
また、今回の検討で同システムを使用することにより、40.3%の患者が搬送または受診しなくてもよくなった。これらの症例に、もし電話連絡のみの相談では、ほとんどの症例で受診することになっていたと思われ、患者の不必要な受診が避けられたことになる。これは、患者にとって、経済的、時間的または肉体的に負担を軽減できたものと考える。
このように、画像電送システムは離島の医療にとって非常に有効な医療支援機器といえる。広大な面積を有する北海道では、離島はもちろんのこと、後方支援病院まで100km(車で1時間30分)を超える地域が数多くある。このような地域に、単純X線写真やCT写真などを電送できるシステムを整備、拡充してゆく必要がある。
さらに、われわれの施設では後方支援病院である市立稚内病院以外に、大学病院への搬送もある。この際、大学病院には同システムが導入されておらず、搬送は電話のみの依頼で行われている。大学附属病院救急治療部のようにあらゆる病院から搬送依頼のある高次救急医療施設にも導入設置が必要と考える。そして、このようなシステムが拡充していくなかで情報の互換性は最優先されるべきである。たとえば、表2のように北海道には当院のほかにも高次医療施設との間で画像電送システムを導入している病院がある。しかし、採用している機種が異なるため、特定の後方支援病院として交信できないのが現状である。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|