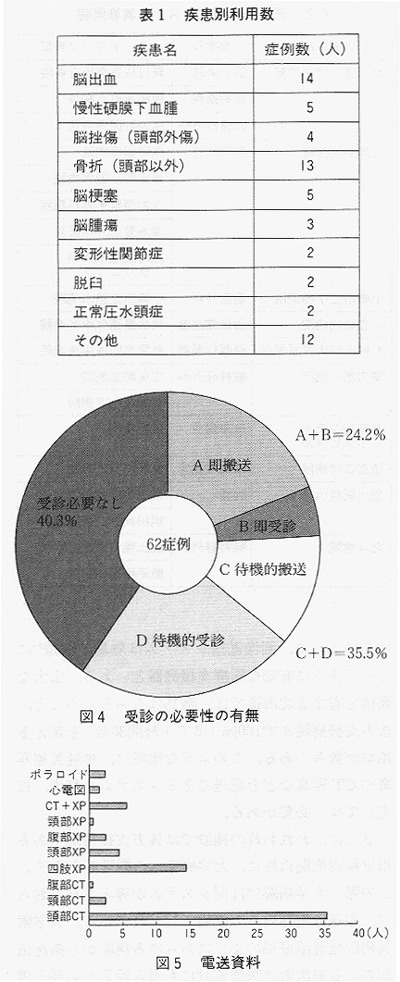
例は頭部外傷と脳出血症例であるが、出血範囲が拡大しないため当院で保存的に治療し、待機的搬送や待機的受診となった。そのほかにも、広範囲脳梗塞1例や脳腫瘍1例で脳実質の経時的な変化が搬送の判断に必要とされたため、1人に2回、画像電送システムを使用している。
全症例について受診の必要性の有無(図4)を集計したところ、即搬送と即受診を合わせて24.2%であり、また待機的搬送と待機的受診を合わせて35.5%であった。逆に25症例(40.3%)で受診の必要なしと判断された。
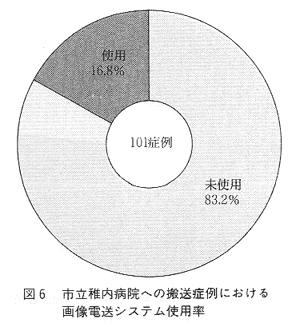
電送資料(図5)に関しては、CTが40症例で、そのうち頭部が36症例、頸部が3症例、腹部が1症例。単純X線写真では24症例が電送され、そのうち四肢が15症例、頭部が5症例、腹部が3症例、頸部が1症例。また、CTと単純X線写真の両方を電送した症例は6症例、そのほか、心電図が2症例、ポラロイド写真が3症例であった。
期間中の全搬送例は114症例で、うち市立稚内病院への搬送は101症例であった。その101症例のうち画像電送システム使用例は17症例(16.8%)であった(図6)。しかし、同期間の脳神経外科領域での搬送症例は全部で21症例であり、うち市立稚内病院への搬送は17症例であった。その17症例で画像電送システムを使用したのは13症例(76.4%)であった(図7)。
画像電送システム使用件数は、増加傾向にある(図8)。
IV.考察
当院では1993年4月から、市立稚内病院との間で画像電送システムが導入され、日常診療や救急搬送時に大いに役立てられている。
今回の検討で画像電送システムは、脳神経外科と整形外科疾患で主に使用されていた。また、脳神経外科疾患では特に、頭蓋内出血や頭部外傷患者の救