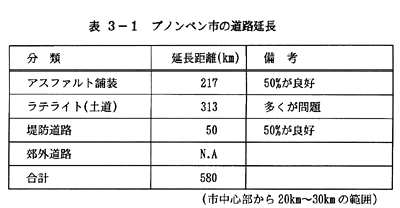
(2) 道路の分類
道路構造は明確な構造令は無く、旧宗主国のフランスが建設した道路網を引き継いでおり、その後独自の道路構造令を定めているわけではない。そこで市内道路は道路分類による区分けはできない。さらに幅員別、車線数別の延長距離も明確でない。日本からの専門家によれば幅員は約10〜11m程度の道路が大部分であるとのことである。
また市内の道路は道路ヒエラルキー的に自動車の走行可能な幹線道路と準幹線、及び街路に分けることができる。この分類は道路構造令のような明確な基準が有るわけではなく、現在進められている世銀のプロジェクト(*2)では以下の様に分類している。
- 主要幹線道路(Primary Road)
一般的に交通量が多く、進入規制や駐車規制など交通流に優先度が付された道路であり、道路沿道に都市の発展を誘発する。市全体規模の交通に対応している。
- 準幹線道路(Secondary Road)
主要幹線へのアクセス、及び域内での交通を分散する役目を担う。いくつかの地域を結んでおり、旅行速度は約30−50km/h程度である。
- 街路
旅行速度が概ね10〜30km/hの道路であり、ごく小さな地域の交通を受け持つ。業務用交通は限られている。
これらの道路区分別の道路網状況を図3−1に示す。