
|
広域の避難計画でもこれより安全側に設定すべきとされている。同じ物質でも条件によって値は異なるものとなろうが、本報告では人体が1分間痛みを耐える限界値2,334(Wm −2)(2,000kcalm −2h ―1)を目安とする。
2.2.3 熱放射
熱放射による伝熱量は絶対温度の4乗の差に比例するため、高温体になると伝熱の大きな部分を占めることとなる。火炎からの放射は広範な波長にわたり、その強さは、放射体の大きさ、放射率、高温ガス層の厚さに依存する。放射率が1に近い場合、伝熱量は次式で与えられる。
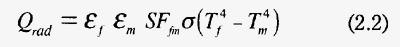
ここで、火炎と受熱体面をf,mで示しεは放射率、Qは伝熱量(W)、Sは火炎の放射面積(m 2)、Fは形態係数、σはStefan Boltzman定数(5.73×10 −8Wm −2K −4)、Tは温度(K)を表す。
[火炎形状]
熱放射による伝熱量は火炎の放射面積に依存し、放射面積は火炎長に、さらに火炎長は熱発生率に依存すると考えることができよう。
火源上に形成される火炎と上昇気流は、火炎域、間歇炎域、プルーム(plume)域の3つの都分に分類されている4)。(図2.2.2参照)
炎域では軸上の温度がほぼ一定で、流速はほぼ火炎の高さの平方根に比例する。上昇気流の拡がりは高さ方向にほぼ一様で、温度と流速は火炎から外れると急速に低下する。火炎とその周囲高温流体は円柱状の高温体とみなせる。
間歇火炎域では軸上の温度は高さに反比例し、鉛直方向流速はほぼ一定で、上昇気流の幅はほぼ高さの平方根に比例して拡がる。
プルーム域ではもはや火炎は見られず、温度は高さの5/3乗に反比例して低下し、鉛直方向流速は高さの1/3乗に反比例し、上昇気流の幅はほぼ高さに比例する。横風の影響が大きく、乱流拡散によって周囲空気との混合が進み、遠方で温度は周囲大気とほぼ等しくなる。[燃焼速度]
燃焼速度は熱発生率を決める要素であり、単位は液面の低下速度で(mm/min)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|