[16]「浮体式空港の設計と環境外力の推定に関する検討」
井上義行、多部田茂、武井康将(横浜国大)
ポンツーン型の浮体式空港の概略設計を行い、この構造浮体に対して浮体式防波堤で囲まれた場合と防波堤のない場合の両者について、環境外力を推定した。また係留設計を行い、空港機能にとって重要な位置保持性能や浮体の挙動の安全性を検討した。浮体の応答解析では領域分割法を用いて弾性挙動の推定を行った。
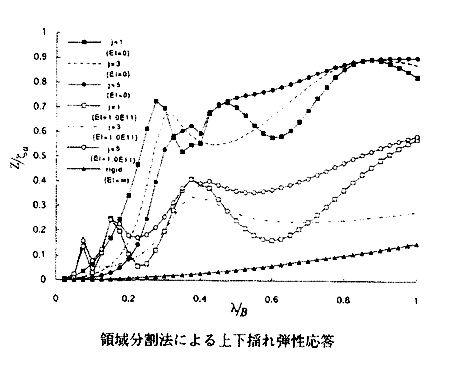
[17]超大型浮体に働く波力・流体力の推定法に関する研究
影本浩、藤野正隆、朱庭耀(東大)
海洋空間利用のための長さ、幅数km規模の超大型浮体に働く波力や流体力を計算するにあたって、既存の数値計算法をそのまま適用しようとすると、浮体が非常に大きいために計算量が膨大になり、実際に解を得ることは困難である。このような難点を克服するためには、本研究では、浮体が非常に大きいことを逆に利用して、精度を損なうことなく、計算量を大幅に減少させることができることを示す。
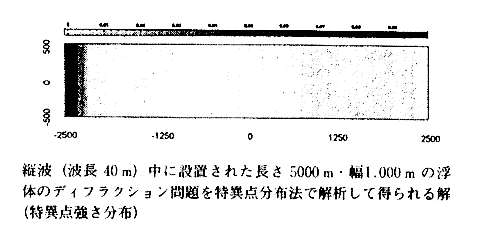
[18]高次境界要素法による波漂流減衰の推定(英文)
Bin Teng(大連工科大学)、加藤俊司、星野邦弘(船研)
波傾斜及び一様流速を微小パラメータとする摂動法をべースに任意3次元浮体の波漂流減衰の数値計算法を新たに開発した。本法を、円柱及び半球浮体の波漂流減衰の推定に応用し、半解析解と比較した。その結果、Timmam−Newmanの関係式がほぼ満足され、半解析解ともよく一致する事から本法の有効性が示された。また、本法を4本のtruncated
cylinderの波漂流減衰推定に応用したところ、ある波周波数範囲で負の減衰が生じる事がわかった。
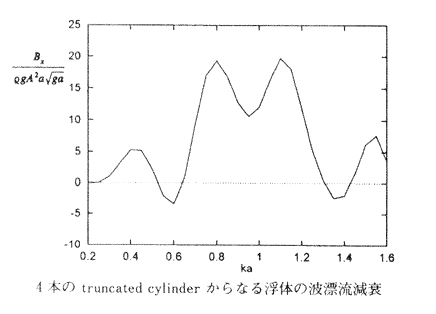
[19]海洋環境総合観測ロボット「FLING
FISH」の開発研究
小寺山亘、山口悟、中村昌彦(九大応力研)、赤松毅人(MHI)
海洋汚染の防止、環境と調和のとれた資源・空間開発法の確立等とともに、海洋環境の計測法の開発が重要な課題として期待されている。長時間連続データを取得するためのブイシステムを補完する空間連続計測手法として、九州大学応用研究所の研究プロジェクト「大気海洋間の物質・熱・運動量の交換過程の計測法の開発研究」において開発された曳航式の観測ロボットF1ying
Fishについて述べる。
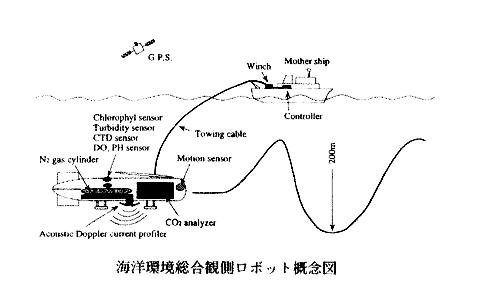
前ページ 目次へ 次ページ