1−3 赤煉瓦のまちづ<りの経緯
1)赤煉瓦のまち・舞鶴のはじまり
舞鶴市は旧海軍のまちであったことから、赤煉瓦の建造物が数多く残っているが、積極的に保存されて残ってきたものではなく、他の用途で使用され、放置されてきたものであり、戦争の遺物として暗いイメージを持つ人も多かった。
ところが、近年になって、これら赤煉瓦建造物をふるさとの財産として見直そうという動きが市民の間で活発に行われるようになった。平成元年に折りからのリゾートブームに乗り、丹後リゾート構想の重点整備地区として赤煉瓦倉庫群の転活用が組み込まれ、一躍赤煉瓦がまちづくりの主役として登場してきた。翌年には、赤煉瓦を生かした、まちづくりをめざし、北海道煉瓦視察ツアー「レイエリアin北海道」に、約100名の市民が参加し、小樽行きのフェリーの中、今後のまちづくりについて熱い議論がたたかわされている。この頃から赤煉瓦を取り巻く市民グルーブ等の動きも活発になり、赤煉瓦倉庫の転活用の機運が盛り上がってきた。
昭和63年に設立された市若手職員の自主研究グルーブ舞鶴まちづくり調査研究会(以下「舞鶴まち研」)が横浜市職員で組織する横浜まちづくり研究会(以下「横浜まち研」)と交流する中で、赤煉瓦に着目した活動を開始し、平成元年11月末から舞鶴まち研が市所有の赤煉瓦倉庫のライトアッブを行っている。また、これまで市内に残る赤煉瓦建造物の所在の確認調査もされておらず顧問に舞鶴市出身の現・京都工芸繊維大学日向進教授を迎え舞鶴まち研の育志によりまいづる建築探偵団(以下「探偵団」)を結成し、市内に残る赤煉瓦建造物の調査に取りかかった。特に市内神崎に残る煉瓦窯の調査では、横浜まち研、現・金沢学院大学水野信太郎助教授も参加され、当時全国で5例目の発見となるホフマン式輪窯であると確認するなど70以上の赤煉瓦建造物を調査している。
?活発な市民運動
平成2年11月、舞鶴まち研、横浜まち研、探偵団により、赤煉瓦の良さを再確認し、まちづくりのきっかけをつくろうと第1回赤煉瓦シンポジウムin舞鶴が開催され、全国20都市から約180人が参加した。参加者には赤煉瓦建造物の調査結果をマップにして配布。会場では、赤煉瓦の魅力について熱心に討議され、舞鶴市が赤煉瓦の宝庫であることがはじめて明らかにされた。
このシンポジウムをきっかけに、赤煉瓦にゆかりのある北海道江別市、横浜市、舞鶴市、呉市などのグループ、個人等の参加により「赤煉瓦ネットワーク」と、まちづくりの民間団体「赤煉瓦倶
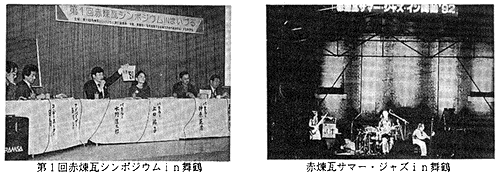
第1回赤煉瓦シンポジウムin舞鶴
赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴