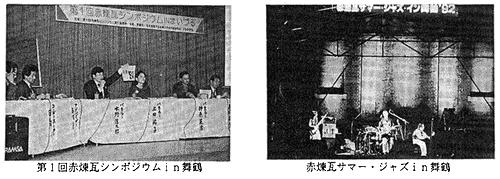1−2 赤煉瓦建造物建設の歴史的背景
(1)舞鶴海軍鎮守府の開庁
近代日本で本格的に海軍が整備されだしたのは、明治10年代になってからである。朝鮮の領有をめぐって日本と精国との対立が深まり、海軍力の整備は緊急の課題となっていた。明治19年(1886)には、対清戦争の拠点として、横須賀、呉、佐世保の各軍港施設が決定し、同22年(1889)には対ロシア戦略上の拠点として目本海側の舞鶴に鎮守府を設けることが決まった。舞鶴湾は湾口が狭く、防御に適しており、湾内は波静かで多くの艦船が停泊できるなど軍港としては格好の地形であった。
なお同29年(1896)5月、舞鶴鎮守府の建設着工にあたって、東京に臨時海軍建築部、舞鶴に臨時海軍建築支部が設置されたが、主力は舞鶴にあった。しかし、二軍港(呉、佐世保)の整備が優先され、舞鶴の軍港建設費用には日清戦争によって清国から支払われた陪償金があてられた。
敷地開削工事には莫大な費用と手数を要したが、明治32年(1899)切暮れにいたり、土地改造工事がほぼできあがった。これに平行して鎮守府諸施設の工事が始まり、数百件の工事が進められた。かくして明冶34年(1901)10月1目、舞鶴鎮守府が開庁、初代指令長官は東郷平八郎(当時海軍中将)であった。後に連合艦隊指令長官として目露戦争の勝敗を決した日本海海戦で指揮をとった名将である。
以後舞観は昭和20年(1945)の終戦まで海軍のまちとして特異な発展をみせる。