リーダー報告
「派遣を終えて」
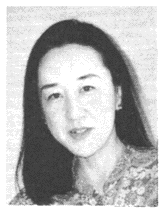
身障青少年の国際体験
リーダー 角谷昌子
身障青少年の国際体験派遣事業は、日本船舶振興会(日本財団)の補助事業として、今回で7回目を迎え、プログラムは、ますます充実してきている。私が、(財)世界青少年交流協会のボランティア・リーダーとして派遣事業に参加してから、足掛け9年になるが、このプログラムのリーダーとなるのは、初めてであった。
派遣国は、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、フランスの4ヶ国。プログラムは、ろう学校、聴覚障害者学校、身障者訓練センター、ろう協会などの訪問、市長表敬訪問、聴覚障害者に関する講義等、盛り沢山の内容であった。いずれの訪問先においても、言語の相違に戸惑いを見せず、すぐに手話や身振りを通じて相互にうちとけ合う光景が、印象的であった。
次に、訪問国別に、感想などを簡単にまとめてみた。
ドイツ
プファルツろう学校は、明るく開かれた雰囲気の学校で、生徒の年齢や障害の程度に応じてクラス分けされ、少人数制の授業が実施されていた。授業や、機能訓練の様子を見学したが、非常に合理的な教育方針だと思えた。
ドイツでは、口話教育が中心で、我々が見学した授業も、教師の指示に従い、生徒は発声練習や聞き取り、唇の読み取りを行っていた。確かに、聴覚障害者が社会に進出し、聴者とコミュニケーションをするために口話教育は、必要である。しかし、障害を持つ人達に、さらなる努力を強いなくてはならない側面をも痛感した。口話教育一辺倒ではなく、手話もコミュニケーション手段として尊重されるべきであろう。社会はあまりにも聴者中心に構成されており、聴者からの歩み寄りが少ないと、手話知識の乏しい自分自身の反省をも含めて再確認させられた。
ハイデンベルク、フランクフルトの両ろう協会では、手作りの料理や菓子などが用意され、温かいもてなしを受けた。また、参加者の名前を漢字で和紙に書く実演や、日本のお土産の説明などをして、日本の文化の一端に触れてもらった。
オーストリア
連邦社会省にて、聴覚障害者の現状、障害者対策、行政上の取り組みなどの講義を受ける。各担当者がホワイト・ボードの前に並び、順番に説明してくれたが、独―日通訳、手話通訳を介しての講義は時間がかかり、詳細にわたる説明や、質疑応答のための時間的余裕が少なかったのが、惜しまれた。行政面でも、一般の会社に対して、雇用条件を設けるなどして、障害者の雇用促進を図ってはいるが、現時点では、残念ながら殆どが公務員で、一般の会社での雇用は乏しいというのが実情である。
前ページ 目次へ 次ページ