|
5−3 CTP不参加事例とプライベートセクター
以上のように、CTPは地域住民のニーズに合った観光の形態であり、貧困層の多い農村部においては住民参加型開発は、貧困緩和への「万能薬」に見えるかも知れない。しかしながら、必ずしも「万能薬」ではないことは、同地区の他の村が参加していないことからも明らかである。不参加の理由は地域により異なる部分があるが、アルメル地区での不参加村はOldadai, Nambere, Bangataの3カ村である。なぜ、CTPに参加していないのか。主としてカルチュラル・ツーリズムに関して、各村の村長および代表者に対して不参加の理由を中心に、面接法による調査を行った。不参加の主な理由は、(1)自分の村にアトラクションが少ない、(2)設備が不十分である、もしくは適切でない、(3)文化や伝統への影響を危惧、といった項目が挙げられた。理由の中でも、「設備が不十分、もしくは適切でない」ということが不参加の主たる要因で、宿泊だけでなく安全性の確保などの面からも参加に踏み切れなかった、と言う。しかし、すでにCTP運営が軌道に乗っている前出のNg'iresi村、Olgilai村のガイドやコーディネーターの協力を得て、現在では3カ村のうち2カ村がCTPの開始に向け、準備をすすめている段階にある。
これまで見てきたカルチュラル・ツーリズムは、SNVとTTBという比較的大きな組織による運営が行われているものであったが、アルーシャ市周辺では、ツアーガイドおよびツアー会社といったプライベートセクターがカルチュラル・ツーリズムを行っている場合もある。ツアーそのものの内容的には大差はないが、地域住民への収益の還元という点では、運営側によって方針が異なり、中には全く還元を行っていない業者も存在する。収益の地元住民への還元率や還元方法はプログラムによって異なっているのが現状である。
独自のカルチュラル・ツアーを行うJohn Henryは、1998年からNgurudoto村を中心にトレッキングとホームステイを中心としたツアーを主催しており、1年に約30人前後の個人観光客をガイドする。Ngurudoto村には6864人、572世帯が生活をしており、その内訳は、大人が2288名、小学生以下の子供が4576名である。村議会の議長であるReuben A. Nassari氏によれば、小学校に通う児童のうちの約75%が経済的な理由により進学することが出来ない状態にあるという。小学校に通うためにかかる費用は一年につき児童一人あたり、約9000Tsh.である。この金額は、タンザニアの平均年収の約3%に相当するが、就学児童数の多いNgurudoto村のような貧困層の多い村では、各世帯の負担も人数分多くなり、さらに家計を圧迫する。周辺の他地域と同様に、この村においても貧困の緩和は大きな課題となっている。また、学校設備と医療の問題も無視することは出来ない。SNVプログラムと同様、この地域で行われるツアー料金にも開発支援費が組み込まれているが、その還元率はSNVによるCTPに比べ、低くなっている。主な理由は、(1)個人による営業活動には、より多くのコストがかかること、(2)実際の集客頻度が低いため、生活を維持するためには多くを還元することは難しいこと、であると言う。実際、繁忙期以外は集客が難しいため、得た収入を貯蓄しておく必要があり、一定の開発支援費の割合を決めていても監視役が存在しないため、その収益の分配は個人の匙加減となる可能性も否めない。そのような点からも、個人によるツアーの運営を維持していくことは非常に難しいと言える。
以上のように、個人で行われるカルチュラル・ツアーの場合には、組織によって運営されるプログラムに比べ、難点があることは明らかである。所得配分の問題のみならず、地域の協力体制を短期間のうちに構築することも容易ではない。また、ツアーを始めることによって、観光客からの寄付を当てにしている場合も多く見受けられる。実際に「なぜ、カルチュラル・ツーリズムに賛成なのか」という問いに対しても、もっとも大きな理由としては「村の諸設備がよくなるから」という回答の次に、「寄付が(得られる機会が)増えるから」という回答が多かった。Ngurudoto村で、このカルチュラル・ツアーに協力をしている前出のReuben A. Nassari氏も、「観光客からの寄付は村の大きな収入源でもあり、出来る限り観光客を増やしていきたい」と、その参加動機を語っており、カルチュラル・ツーリズムを通じて得られる寄付への依存度の高さが伺える。とは言え、カルチュラル・ツアーが開始されて以来、この村では開発支援費を通じて、小学校にドアつきのトイレが設置され、教室と教師用の家が建設された。個人運営につきまとう収益のマネー・フローの不透明さは否定できないものの、実際に効果が形になっていることから、村民の協力体制も徐々に進みつつあるようだ。
6. 住民参加型開発とエコツーリズムの今後
コミュニティ・ベースの協力の方策として、従来どおり農業分野での協力を行うこともむろん重要ではあるが、今後の可能性を模索するという意味においては、先述のとおり新たな基幹産業の創出が重要であろう。そのような観点から言えば、観光産業は極めて潜在力の高い産業であり、住民参加によって運営されるカルチュラル・ツーリズムをはじめとするエコツーリズムの諸形態はコミュニティ・ベースの持続可能な観光であることから、地域住民の真のニーズを反映出来る可能性が高い。海外への観光客数は年を追うごとに増加の一途をたどり、間違いなく観光産業は世界経済に影響を及ぼしている。国際エコツーリズム年を迎え、途上国における観光産業の可能性は広がりをみせていくと考えられる。
もちろん、住民参加型のエコツーリズムにも課題はある。たとえば、参加地域間の収益格差の問題がある。SNVによるカルチュラル・ツーリズムのように、近隣に成功例があれば、それを取り入れたいと考えることは必然的にあり得ることである。その際、観光客数の増加率に対して参加地域の供給過剰が起こったり、あるいは観光商品としての各地域の特色の多様性に限界があったりすると、参加する地域によって収益の格差が生じる可能性がある。これに対する対策としては、参加する地域の特色ごとにグループ分けを行い、担当制でプログラムに参加する方法が考えられる。開発支援費、あるいはそれに準ずるものを、どのようにして参加住民に還元するのかという問題もある。これについては、全てのプログラム参加村に分配する方式が考えられる。開発支援費として支払われた料金を、各参加村に対して必要なものに換えてから供給するという方法である。しかし、この方法には各村の努力が直接の利益に反映されないため、参加住民の意欲を減退させる可能性を内包しており、工夫が必要である。
エコツーリズムの中でもカルチュラル・ツーリズムに問題を限定した場合には、やはり「持続性」という点での限界も考慮しなければならない。主として自然資源の鑑賞を観光商品とするネイチャー・ツーリズムは自然の変化を楽しむため、繰り返しの来訪を期待出来るが、カルチュラル・ツーリズムは観光商品そのものに変化がなく、繰り返しの来訪は期待薄である。結果として、持続可能性に乏しいとの見方もある。それだけに、一つの地域の中で類似した文化的特色を持つ他の村が同じCTPに参加する場合はどのように共存するのかという問題が生じる。このような問題に対する提言としては、まず、総合的なプログラムの管理と多様化のための努力が何よりも必要である。数が少ないうちは各地域が文化的特色と考えるものを進めていくだけでも問題はないが、多数になればなるほど、その内容全体を統括する制度が必要になってくるであろう。総合的な運営を行うことを通じて、地域によってのメリットもデメリットも相互扶助的に上手く活用することが可能になる。その場合には、政府やその下部組織などが地元住民との連携を深めながら自立的運営を行っていかなくてはならない。
次に、開発を通じた文化変容などネガティブ・インパクトの問題もある。文化変容への対策としては、自己の伝統や文化を観光商品にすることにより、その維持に努めると同時に、開発を通じて変化した部分をも観光商品として観光客に公開していくことも必要である。「変化」は必ずしも負の変容であるとは限らない。現状の変化を外部の人々(観光客)に知ってもらうことも、カルチュラル・ツーリズムが担える役割でもある。また、継続性を考える上では、次世代に対しての環境教育を行うことも不可欠である。エコツーリズムにせよ、カルチュラル・ツーリズムにせよ、そのツアープログラムを円滑に進めるためには、観光資源としての「場所」と「人」は何よりも重要である。プログラムが行われる環境の保全とは、何も自然資源のみを指しているのではない。観光を通じての学びを行う「場」と、それを提供する「人」はいずれも不可欠な観光資源である。そして、それを守り育んでいくのは次世代を担う子供達であり、エコツーリズムを通じて得た利益を還元することで初等教育の徹底を図り、その場で環境教育を行うことによって、CTPをはじめとするエコツーリズムの諸形態を単なる利益循環型ツアーではなく、次世代を巻き込んだ有効性の高いプログラムにすることが可能となる。現時点では、各小学校において特別な環境教育のシステムは確立されていないが、今後、そういった将来世代への対策も必要になってくると考えられる。
エコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムには、過開発への懸念が存在することも事実である。もっともな懸念ではあるが、農村部などの貧困者の多い地域における観光開発のプログラムに関しては、持続可能性とは何かという問題設定も必要だろう。仮にタンザニアにおける観光の場合、過開発によって、エコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムの長所(アトラクション)が一定の範囲で減衰したとしても、それまでに得た利益が不当に使われることなく、観光産業従事者である地元住民や参加住民、あるいは地元コミュニティーに直接的に還元されれば、その地域の生活水準底上が可能となるはずである。それにより教育水準や就学率が向上し、BHNが満たされることで、農業から他の産業への転換を図ることが出来れば、それはそれで地域社会に資するはずである。その結果、エコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムによる生活水準向上が無かった場合に直面したであろう自然や文化遺産の大規模な破壊を回避できると考えられる。また、エコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムの収益によって農業から他の産業への転換が進めば、その段階ではエコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムヘの依存度も減り、自然や文化遺産への過度な開発の危険も減ると考えられる。したがって、持続可能性を問う場合、現時点のプログラムの持続可能性を考えるだけではなく、そのプログラムを実施しなかった場合の自然や文化遺産の持続不可能性や、プログラムが役割を終えた後の自然や文化遺産の持続可能性も同時に考慮し、対策を構築していかねばならない。
以上のような諸点に配慮しながら進めていけば、エコツーリズムやカルチュラル・ツーリズムは途上国支援の一つのアプローチとして有効な方法だと考えられる。タンザニアだけに限らず、今後のアフリカ援助を考える上で、誰に対する何のための援助なのかという点を常に認識しつつ、ドナー側のエゴに走らない援助を考えることが不可欠であり、その際に忘れてはならないのが「その土地で暮らす人々の本当に望むものは何か」という点である。途上国の開発援助という国際協力を進めていくうえで、「開発援助」という言葉の「援助」とは、一体、何に対する援助なのかを常に念頭においておく必要がある。「持続可能な開発」という言葉が開発のあらゆる場面で用いられる昨今だが、「持続可能性」とは、被援助国の社会と住民の現在と未来に有益で、さらに発展の可能性を持つものに使われるべき用語である。タンザニアに限らず、途上国には様々な問題が山積しているが、支援を行うことを通じ、何らかの成長が見られる「芽」を伸ばす援助が、今後の全体支援に向けての足がかりとなるはずである。その意味において、住民参加型のエコツーリズムは有効に機能する開発手法であると考えられる。住民参加型の「開発援助」とは先進国だけが行うものではなく、援助する側と受ける側の双方向の活動であることを認識し、援助を受ける側の可能性を見極めた支援体制の確立を今後は目指していく必要があると言えよう。
| (拡大画面:436KB) |
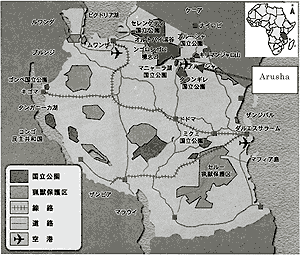 |
タンザニア連合共和国 地図
|