|
(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年2月5日02時20分
愛媛県今治港
(北緯34度03.4分 東経133度01.6分)
2 船舶の要目等
(1)要目
| 船種船名 |
貨物船第八進洋丸 |
|
| 総トン数 |
496トン |
|
| 全長 |
65.50メートル |
|
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
|
| 出力 |
735キロワット |
|
| 船種船名 |
押船第二十一富士鷹丸 |
被押バージ第20富士鷹丸 |
| 総トン数 |
99トン |
693トン |
| 全長 |
|
53.50メートル |
| 登録長 |
20.11メートル |
|
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
|
| 出力 |
735キロワット |
|
(2)設備及び性能等
ア 第八進洋丸
第八進洋丸(以下「進洋丸」という。)は,昭和62年7月に進水した,バウスラスターを有する航海速力9.5ノットの船尾船橋型鋼製砂利採取運搬船で,船橋前面の窓に面して設置されているコンソールスタンドの中央部に磁気コンパス,操舵輪及び操舵切替スイッチ,左舷側にレーダー2台及び発電機遠隔制御盤,右舷側にGPS,機関及びバウスラスターの遠隔制御盤が,それぞれ装備されており,専ら瀬戸内海で砂利運搬に従事していた。
イ 第二十一富士鷹丸
第二十一富士鷹丸(以下「富士鷹丸」という。)は,平成6年2月に進水した鋼製押船で,その船首部を第20富士鷹丸の船尾凹部に嵌合して,全長約65メートルの押船列(以下「富士鷹丸押船列」という。)を構成し,専ら瀬戸内海で砂利運搬に従事していた。
ウ 第20富士鷹丸
第20富士鷹丸(以下「バージ」という。)は,非自航の鋼製台船で,船首部に旋回式ジブクレーン1基を設け,前示押船列を構成していた。
3 事実の経過
進洋丸は,A受審人ほか3人が乗り組み,空倉で,船首1.3メートル船尾2.7メートルの喫水をもって,平成17年2月4日23時00分広島県福山港を発し,愛媛県今治港に向かった。
A受審人は,船橋当直を一等航海士,甲板員,自らの順番による単独1時間30分交替の3直制に定め,出港後一等航海士に船橋当直を任せて降橋した。
ところで,進洋丸の操舵切替スイッチは,操舵輪の左下方にあり,左から自動,手動,遠隔及びレバー各操舵の4段階切替スイッチとなっており,A受審人は,平素出入港や揚投錨時には遠隔操舵に切り替えて操船していた。
翌5日01時50分A受審人は,今治港沖合で再び昇橋し,前直の甲板員から船橋当直を引き継ぎ,02時00分今治港蔵敷防波堤灯台(以下「蔵敷防波堤灯台」という。)から054度(真方位,以下同じ。)3.0海里の地点に達したとき,今治港内に錨泊している富士鷹丸押船列をレーダーと肉眼で3.1海里先に認めて向首し,針路を223度に定め,機関を全速力前進の回転数毎分260にかけ,9.5ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,法定灯火を表示し,自動操舵によって進行した。
針路を定めたとき,A受審人は,富士鷹丸押船列に0.5海里まで接近した地点で,遠隔操舵に切り替え,その後右転して投錨するつもりで,レーダーにより同押船列との距離を測定しながら続航した。
02時17分わずか前A受審人は,蔵敷防波堤灯台から096度1,320メートルの地点に至り,富士鷹丸押船列まで0.5海里となったとき,自動操舵から遠隔操舵に切り替えるため,操舵切替スイッチを操作したが,慣れた操作なのでまさか間違えるとは思わず,直ちに遠隔操舵器のダイヤルを回すなど,舵の切替確認を十分に行わなかったので,操舵切替スイッチが遠隔操舵の位置になっていないことに気付かないまま,その後主機を港内微速とし減速しながら進行した。
02時18分A受審人は,蔵敷防波堤灯台から114度1,140メートルの地点に達し,富士鷹丸押船列に正船首方向500メートルまで接近したとき,右転するためコンソールスタンドに置いてある遠隔操舵器のダイヤルを回したところ,右転することができず,間近に迫った同押船列に危険を感じ,機関を後進としたが効なく,02時20分蔵敷防波堤灯台から141度1,090メートルの地点において,進洋丸は,原針路のまま,5.0ノットの速力で,その船首が,バージの右舷中央部に後方から70度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は上げ潮の初期で,視界は良好であった。
また,富士鷹丸は,船長ほか2人が乗り組み,船首2.0メートル船尾2.8メートルの喫水をもって船首1.6メートル船尾1.9メートルの喫水となったバージと押船列を形成して,同月4日08時30分岡山県牛窓港を発し,今治港に向かった。
15時30分船長は,前示衝突地点付近に至り,バージの船首から右舷錨を投じ,錨鎖を3節まで延ばして錨泊し,17時00分船橋周りに500ワットの作業灯を4個,バージの甲板上とジブクレーンに500ワットの作業灯6個をそれぞれ点灯した。
船長は,視界が良く海面も穏やかで,通常通航船が利用しない水域であることから,自らが適宜昇橋して異常がないか確認することで,特に守錨直を立てなかったところ,293度に向首したバージの右舷側に進洋丸の船首が前示のとおり衝突した。
衝突の結果,進洋丸は,バルバスバウに凹損を生じ,バージは,右舷側外板に破口を生じたが,のち修理された。
(航法の適用)
本件は,港則法に規定された特定港である今治港において,航行中の進洋丸と,錨泊中の富士鷹丸押船列が衝突したものであり,同法には適用される規定がなく,一般法である海上衝突予防法(以下「予防法」という。)が適用されることとなるが,予防法には,航行している船舶と錨泊している船舶に関する航法規定がないので,予防法第38条及び第39条の船員の常務で律するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
A受審人が,操舵切替スイッチを操作した際,慣れた操作なのでまさか間違えるとは思わず,遠隔操舵器のダイヤルを回すなど,舵の切替確認を十分に行わなかったこと
(原因の考察)
進洋丸は,夜間,自動操舵から遠隔操舵とするため,操舵切替スイッチを操作したとき,直ちに遠隔操舵器のダイヤルを回すなど,舵の切替確認を十分に行なえば,同スイッチが遠隔操舵の位置になっていないことに容易に気付き,富士鷹丸押船列との衝突を回避できたものと認められる。
したがって,A受審人が,操舵切替スイッチを操作したとき,直ちに遠隔操舵器のダイヤルを回すなど,舵の切替確認を十分に行わなかったことは,本件発生の原因となる。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,愛媛県今治港沖合において,進洋丸が錨地に向けて航行中,自動操舵から遠隔操舵とするため,操舵切替スイッチを操作した際,舵の切替確認が不十分で,同スイッチが遠隔操舵の位置になっていないまま富士鷹丸押船列に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,愛媛県今治港沖合を錨地に向け航行中,自動操舵から遠隔操舵とするため,操舵切替スイッチを操作した場合,直ちに遠隔操舵器のダイヤルを回すなど,舵の切替確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,慣れた操作なので,まさか間違えるとは思わず,舵の切替確認を十分に行わなかった職務上の過失により,同スイッチが遠隔操舵の位置になっていないことに気付かず,遠隔操舵がとれないまま錨泊していた富士鷹丸押船列に向首進行して衝突を招き,自船のバルバスバウに凹損が生じ,バージの右舷側外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
| (拡大画面:26KB) |
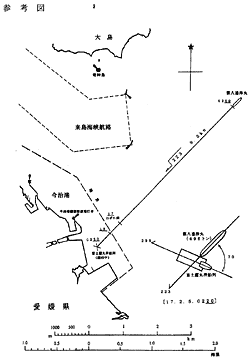
|
|