|
(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年7月4日18時45分
北海道岩内港北西方沖合
(北緯43度02分 東経140度24分)
2 船舶の要目等
(1)要目
| 船種船名 |
漁船第十五海洋丸 |
漁船第八美笠丸 |
| 総トン数 |
19.74トン |
9.99トン |
| 登録長 |
16.70メートル |
12.61メートル |
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
| 漁船法馬力数 |
180 |
80 |
(2)設備及び性能等
ア 第十五海洋丸
第十五海洋丸(以下「海洋丸」という。)は,昭和52年8月に進水したいか一本釣り漁業などに従事する鋼製漁船で,ほぼ船体中央部に操舵室を有し,同室にレーダー2台,GPSプロッタ及び魚群探知機各1台が備えられ,船首部から船尾部の両舷にいか釣り機が設置されていた。
イ 第八美笠丸
第八美笠丸(以下「美笠丸」という。)は,昭和51年3月に進水したいか一本釣り漁業などに従事するFRP製漁船で,ほぼ船体中央部に操舵室を有し,同室中央に舵輪,右舷側にレーダー,GPSプロッタ及び右舷側後部に魚群探知機各1台が備えられ,同室後部中央に機関室天井の一部が幅30センチメートル高さ70センチメートルの形状で張り出していた。
3 事実の経過
海洋丸は,A受審人が1人で乗り組み,いか釣り漁の目的で,船首1.2メートル船尾2.4メートルの喫水をもって,平成15年7月4日15時30分北海道岩内港を発し,同港北西方沖合6海里ばかりの漁場に向かった。
A受審人は,16時30分前示漁場に着き,機関を停止したあと,船首からパラシュート型シーアンカーを投入し,船尾にスパンカーを掲げたほか3キロワットの白熱灯を点灯して漂泊を開始し,17時ごろから10台のいか釣り機を作動させて操業を始めた。
A受審人は,操舵室前方の甲板上の作業台で船尾方を向き,釣れたいかの箱詰め作業を行っていたところ,18時41分岩内港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から295度(真方位,以下同じ。)5.3海里の地点において,折からの南東風により船首が135度を向いていたとき,右舷正横1,110メートルのところに自船に向首する美笠丸を視認することができ,その後,同船が衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況にあったが,同作業に気を奪われ,周囲の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,警告信号を行わないまま同作業を続けた。
こうして,海洋丸は,漂泊中,18時45分西防波堤灯台から295度5.3海里の地点において,船首を135度に向けていたとき,その右舷中央部に,美笠丸の船首がほぼ直角に衝突した。
当時,天候は晴で風力2の南東風が吹き,潮候は下げ潮の初期で,日没時刻は19時20分であった。
また,美笠丸は,B受審人が1人で乗り組み,いか釣り漁の目的で,船首0.8メートル船尾1.3メートルの喫水をもって,同日16時00分岩内港を発し,同港西方沖合9.5海里の漁場に向かった。
B受審人は,17時00分前示漁場に着き,操業を開始したところ釣果がなく,僚船から岩内港北西方沖合6海里ばかりの漁模様がよいとの情報を得て漁場を移動することとし,17時30分ごろ操業をやめて北東方向に向けて発進し,途中,周囲で操業している僚船の漁模様を見るため,針路を左右に変えながら航行した。
B受審人は,操舵室後部中央の機関室の天井張り出し部に腰をもたれ掛け,レーダーを3海里レンジで作動させ,遠隔装置による手動操舵と見張りに当たり,18時38分西防波堤灯台から285度5.7海里の地点に達したとき,針路をGPSプロッタに入力した目的の漁場に向く045度に定め,機関を回転数毎分1,800にかけ,9.0ノットの対地速力で進行した。
18時41分B受審人は,西防波堤灯台から289度5.5海里の地点に至ったとき,正船首1,110メートルのところに漂泊して操業中の海洋丸を視認することができ,その後,衝突のおそれのある態勢で向首接近しているのを認め得る状況にあったが,作動中の魚群探知機を見ることに気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,海洋丸を避けずに続航中,美笠丸は,原針路,原速力のまま,前示の通り衝突した。
衝突の結果,海洋丸は,右舷側中央部ブルワーク及び操舵室右舷側側壁に凹損並びにいか釣り機などを損傷し,美笠丸は,船首ブルワークに凹損を生じた。
(航法の適用)
本件は,北海道岩内港北西方沖合において,漂泊中の海洋丸と北東進中の美笠丸とが衝突したものであり,発生海域により一般法の海上衝突予防法が適用されることになる。しかしながら,同法には航行船と漂泊船との関係について規定した条文がないので,同法第38条及び第39条により律するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 海洋丸
(1)釣れたいかの箱詰め作業に気を奪われ,見張りを十分に行わなかったこと
(2)警告信号を行わなかったこと
2 美笠丸
(1)作動中の魚群探知機を見ることに気をとられ,見張りを十分に行わなかったこと
(2)漂泊中の海洋丸を避けなかったこと
(原因の考察)
本件は,シーアンカーを投入して漂泊中の海洋丸が,見張りを十分に行っていれば,接近する美笠丸を認識して警告信号を行い,衝突を回避できたと認められる。
したがって,A受審人が,いかの箱詰め作業に気を奪われ,周囲の見張りを十分に行わなかったこと及び警告信号を行わなかったことは,本件発生の原因となる。
一方,北東進中の美笠丸が,見張りを十分に行っていれば,前路に漂泊中の海洋丸を認識して同船を避けることができ,衝突を回避できたと認められる。
したがって,B受審人が,作動中の魚群探知機を見ることに気をとられ,前路の見張りを十分に行わず,漂泊中の海洋丸を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
(海難の原因)
本件衝突は,北海道岩内港北西方沖合において,漁場移動のため北東進中の美笠丸が,見張り不十分で,前路でシーアンカーを投入して漂泊中の海洋丸を避けなかったことによって発生したが,海洋丸が,見張り不十分で,警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は,北海道岩内港北西方沖合において,漁場移動のために北東進する場合,前路で漂泊中の海洋丸を見落とさないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし,同受審人は,作動中の魚群探知機を見ることに気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,漂泊中の海洋丸に気付かず,同船を避けないまま進行して衝突を招き,海洋丸の右舷側中央部ブルワーク及び操舵室右舷側側壁に凹損並びにいか釣り機などに損傷を,美笠丸の船首ブルワークに凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は,北海道岩内港北西方沖合において,パラシュート型シーアンカーを投入して漂泊し,操業を行う場合,右舷正横方から接近する美笠丸を見落とさないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし,同受審人は,釣れたいかの箱詰め作業に気を奪われ,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,接近する美笠丸に気付かず,警告信号を行わないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き,両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
| (拡大画面:16KB) |
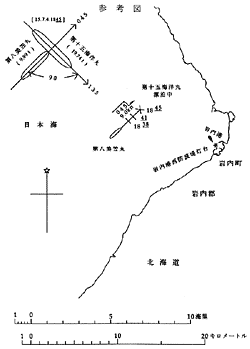
|
|