|
(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年9月23日20時30分
宮城県金華山南西方沖合
(北緯38度01.1分 東経141度24.8分)
2 船舶の要目等
(1)要目
| 船種船名 |
貨物船大豊丸漁船 |
第八十八稲荷丸 |
| 総トン数 |
498トン |
80トン |
| 全長 |
72.01メートル |
|
| 登録長 |
|
28.95メートル |
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
| 出力 |
735キロワット |
672キロワット |
(2)設備及び性能等
ア 大豊丸
大豊丸は,平成7年10月に進水した全通二層甲板を有する船尾船橋型鋼製貨物船兼砂利運搬船で,船橋にレーダー2台及びGPSが設置され,船首甲板上にジブクレーンが装備されていたが,船首方に航行の支障となる死角が生じる状況ではなかった。
海上公試運転成績表によると,舵角35度とした旋回試験における最大縦距及び最大横距は,速力11.46ノットで航走して右旋回を行った場合,それぞれ約182メートル及び約142メートル,速力11.56ノットで航走して左旋回を行った場合,それぞれ約217メートル及び約188メートルであった。
イ 第八十八稲荷丸
第八十八稲荷丸(以下「稲荷丸」という。)は,昭和59年7月に進水した,船体中央より少し前方に船橋を有する鋼製漁船で,大中型まき網漁業の網船として,千葉県勝浦沖から青森県八戸沖に至る離岸距離約20海里までの沖合において,いわし,あじ,さばを対象魚としたまき網による漁ろうに従事していた。
稲荷丸のまき網は,長さ約1,300メートルで,その上縁の浮子網には黄色の浮子が一定間隔で取り付けられていたが,灯火による標識は取り付けられていなかった。
3 事実の経過
大豊丸は,A受審人ほか4人が乗り組み,硫安1,138トンを積み,船首3.5メートル船尾4.6メートルの喫水をもって,平成16年9月22日17時30分千葉県木更津港を発し,岩手県宮古港に向かった。
A受審人は,船橋当直を単独4時間交替の3直制として,00時から04時及び12時から16時までを一等航海士,04時から08時及び16時から20時までを甲板長,08時から12時及び20時から24時までを自らがそれぞれ入直することとし,同当直に従って房総半島沖合から本州東岸沖合を北上し,翌23日の夜間,金華山南西方沖合に至った。
A受審人は,早めに昇橋して甲板長と船橋当直を交替し,19時50分金華山灯台から210.5度(真方位,以下同じ。)24.0海里の地点で,針路を038度に定めて自動操舵とし,機関を全速力前進にかけて10.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で進行した。
20時15分A受審人は,右舷船首方約2.5海里に稲荷丸と同船の僚船が点灯している明るい灯火を初認し,漁ろうに従事している船舶の灯火を識別できなかったものの,漁船が止まって操業しているものと判断し,早期に稲荷丸との航過距離を広げる針路とせず,同船を右舷正横約300メートル離れて航過する態勢で,同じ針路のまま続航した。
A受審人は,周囲に多数のまき網船団が操業しており,それらの漁船が明るい作業灯を多数点灯していることから,前路に視認した数隻の漁船が船団を構成して漁網を展張していることが予想できる状況下,20時18分半金華山灯台から209度19.3海里の地点に達したとき,稲荷丸が右舷船首5度2.0海里となり,その後,南西方に向首した同船右舷側のほぼ円状に展張されたまき網に衝突のおそれのある態勢で接近したが,同船との航過距離が約300メートルあったので,このくらい離れていれば無難に航過できると思い,同船を大幅に避けないまま進行中,20時30分金華山灯台から208度17.5海里の地点において,大豊丸は,原針路,原速力のまま,稲荷丸が展張した同網上縁の浮子網に衝突し,これを乗り切った。
当時,天候は曇で風力2の北東風が吹き,視程は約4海里であった。
A受審人は,まき網と衝突したことに気付かず,そのまま北上したが,船名を確認したB受審人からの衛星船舶電話でその事実を知らされ,発生地点に戻って事後の措置に当たった。
また,稲荷丸は,B受審人ほか23人が乗り組み,船尾にレッコボートと称する総トン数5トン未満の小型作業船を曳航し,操業の目的で,船首1.2メートル船尾4.0メートルの喫水をもって,同月23日17時40分宮城県石巻港を発し,金華山南西方沖合の漁場に向かった。
ところで,B受審人は,運搬船2隻及び探索船1隻とともにまき網漁業の船団を構成し,日曜祝祭日及び荒天時以外は,夕刻発航して夜間に操業を行い,翌朝帰航して夕刻まで休息を取る操業形態を繰り返していた。
B受審人は,発航後,魚群の探索を行いながら漁場に向かい,20時00分前示衝突地点付近に至って操業を開始することとし,漁ろう中である船舶の所定の灯火に加え,黄色の船団識別灯や甲板上に多数の作業灯などを点灯し,20時10分金華山灯台から207度17.4海里の地点で,レッコボートにまき網の一端を係止して洋上に停留させ,右旋回を行いながら投網を開始した。
20時17分B受審人は,投網開始地点に戻って右舷側に同網を直径約350メートルの円状に展張し終え,機関を中立運転として探索船に自船の左舷側を引かせ,揚網を援助する裏漕ぎと称する作業を行わせながら揚網作業を開始した。
B受審人は,投網開始地点で,218度に向首して網を絞り始めたころ,20時18分半右舷船首5度2.0海里に大豊丸の白,白,緑3灯を視認できる状況であったが,船橋内の右舷側で,目視や0.5海里レンジとしたレーダーによって展張したまき網の形状を確認したり,ソナーを監視したりするなど,揚網作業に専念し,周囲の見張りを十分に行わなかったので,同船の存在も,その後展張した同網に衝突のおそれのある態勢で接近することにも気付かなかった。
B受審人は,大豊丸が更に接近したが,依然見張り不十分で,警告信号を行わないまま揚網作業中,他の船団から接近する他船がある旨の無線電話を受けて初めて至近に迫った大豊丸に気付き,汽笛により短音数回を吹鳴し,僚船が探照灯で浮子を照射したが効なく,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,大豊丸に損傷はなかったが,稲荷丸は,まき網上縁の浮子網を破網した。
(航法の適用)
本件漁具衝突は,夜間,金華山南西方沖合において,まき網漁業による漁ろうに従事中の稲荷丸が展張したまき網と,木更津港から宮古港に向けて北上中の大豊丸とが衝突したもので,まき網船団の網船に接して展張された同網は同船と一体のものと認められ,漁ろうに従事している船舶と航行中の動力船との関係を定めた,海上衝突予防法第18条の規定を適用するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 大豊丸
(1)早期に稲荷丸との航過距離を広げる針路としなかったこと
(2)稲荷丸との航過距離が約300メートルあったので,このくらい離れていれば無難に航過できると思ったこと
(3)稲荷丸を大幅に避けなかったこと
2 稲荷丸
(1)揚網作業に専念していたこと
(2)周囲の見張りを十分に行わなかったこと
(3)大豊丸が展張したまき網に衝突のおそれのある態勢で接近することに気付かなかったこと
(4)警告信号を行わなかったこと
(原因の考察)
本件は,大豊丸が,漁ろうに従事中の稲荷丸を大幅に避けていれば発生しなかったものと認められる。
しかしながら,A受審人は,稲荷丸との航過距離が約300メートルあったので,このくらい離れていれば無難に航過できると思い,同船を大幅に避けなかったものである。
したがって,A受審人が,漁ろうに従事中の稲荷丸を大幅に避けなかったことは本件発生の原因となる。
A受審人が,早期に稲荷丸との航過距離を広げる針路としなかったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件発生と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,これは,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
一方,稲荷丸が,周囲の見張りを十分に行っていれば大豊丸が展張したまき網に衝突のおそれのある態勢で接近することに気付き,警告信号を行って大豊丸の避航を促し,本件発生を避けることができたものと認められる。
ところで,警告信号は,同信号を聴取した相手船が,状況を判断して効果的な避航動作を取ることができる時間的余裕を持って行われなければならない。
しかしながら,B受審人は,揚網作業に専念し,周囲の見張りを十分に行わなかったので,大豊丸が展張したまき網に衝突のおそれのある態勢で接近することに気付かず,時間的余裕を持って警告信号を行わなかったものである。
したがって,B受審人が,周囲の見張りが不十分で,警告信号を行わなかったことは本件発生の原因となる。
(海難の原因)
本件漁具衝突は,夜間,金華山南西方沖合において,宮古港に向けて北上する大豊丸が,前路でまき網による漁ろうに従事中の稲荷丸を大幅に避けなかったことによって発生したが,稲荷丸が,見張り不十分で,警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,金華山南西方沖合において,宮古港に向けて北上中,前路に操業している稲荷丸と漁船群の明るい灯火を認めた場合,それらの漁船が船団を組んで漁網を展張しているおそれがあったから,漁網に著しく接近することのないよう,稲荷丸を大幅に避けるべき注意義務があった。しかるに,同人は,稲荷丸との航過距離が約300メートルあったので,このくらい離れていれば無難に航過できると思い,同船を大幅に避けなかった職務上の過失により,同船が展張したまき網に衝突し,同網上縁の浮子網を破網する事態を招くに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,夜間,金華山南西方沖合において,まき網を展張して漁ろうに従事する場合,展張した同網に接近する他船を見落とすことのないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,揚網作業に専念し,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,展張した同網に衝突のおそれのある態勢で接近する大豊丸に気付かず,警告信号を行わないまま同作業を続行して同船と同網との衝突を招き,前示の事態を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
| (拡大画面:16KB) |
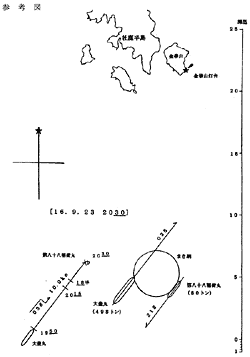
|
|