|
(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年5月14日01時05分
備讃瀬戸東航路
(北緯34度24.6分 東経134度12.8分)
2 船舶の要目等
(1)要目
| 船種船名 |
貨物船第二日之出丸 |
漁船五輪丸 |
| 総トン数 |
498トン |
4.9トン |
| 全長 |
54.87メートル |
15.21メートル |
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
| 出力 |
588キロワット |
48キロワット |
(2)設備及び性能等
ア 第二日之出丸
第二日之出丸(以下「日之出丸」という。)は,昭和63年12月に進水した船尾船橋型の鋼製石材運搬船で,船橋前方の上甲板上にはクレーンの運転室があったものの,操船位置を左右に移動するなどして死角を解消することが可能で,見張りの妨げにならなかった。
また,航海計器として,レーダーとGPSプロッタを設備していた。
試運転成績表写によると,360度回頭に要する時間は約2分,旋回径は船の長さの2倍で,全速力前進中,機関を後進にかけたとき,船体停止までの時間は約1分であった。
イ 五輪丸
五輪丸は,平成14年4月に進水した底びき網漁業に従事するFRP製漁船で,船体中央部に操舵室を有しており,その前方には,見張りの妨げとなる構造物はなかった。
また,航海計器として,レーダーとGPSプロッタを設備していた。
速力は,機関の回転数が毎分3,200のとき約9ノットであった。
3 事実の経過
日之出丸は,A受審人及びB指定海難関係人ほか1人が乗り組み,空倉のまま,船首0.6メートル船尾2.8メートルの喫水をもって,平成16年5月13日22時40分徳島県亀浦港を発し,広島県能美島にある山砂の積載地に向かった。
これより先,A受審人は,夜間,発航操船に当たるに際し,いつも一等航海士が発航操船を行い,所定の灯火を点灯していたところ,今回,同航海士が体調不良で休養したことから,自身で同灯火を点灯することを失念し,所定の灯火を表示しなかった。
発航後,A受審人は,船橋当直を自らとB指定海難関係人による単独4時間2直制とし,発航操船に引き続いて同当直に当たり,23時00分徳島県島田島北方沖合において,昇橋してきたB指定海難関係人に船橋当直を行わせることとしたが,他船を視認したら動静監視を行うよう指示せず,同当直を交替して降橋した。
B指定海難関係人は,入直時に灯火を確認する習慣がなかったことから,灯火の表示確認を十分に行わず,無灯火の状態であることに気付かないまま,単独の船橋当直に就き,23時05分阿波瀬戸港北泊外防波堤灯台から350度(真方位,以下同じ。)2.3海里の地点において,針路を295度に定め,機関を全速力前進にかけ10.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,舵輪後方に置いたいすに腰掛け,自動操舵により進行した。
翌14日00時58分B指定海難関係人は,地蔵埼灯台から170度1,050メートルの地点に達したとき,3海里レンジとしたレーダーで,右舷船首31度1.5海里のところに,南下中の五輪丸の映像を探知し,続いてその白,紅2灯を視認したが,底びき網漁船で速力が遅いようなので,少し左転すればその前路を替わせると思い,282度に針路を転じただけで,動静監視を行わなかった。
01時01分B指定海難関係人は,地蔵埼灯台から215度1,070メートルの地点に達したとき,五輪丸が右舷船首47度1,570メートルに近づき,その後衝突のおそれがある態勢で接近したが,依然動静監視を十分に行わなかったので,このことに気付かず,衝突を避けるための措置がとられないまま続航した。
01時05分わずか前B指定海難関係人は,至近に迫った五輪丸を認めて衝突の危険を感じ,左舵をとったが及ばず,01時05分地蔵埼灯台から253度1.1海里の備讃瀬戸東航路において,日之出丸は,原針路原速力のまま,その右舷側中央部に,五輪丸の左舷船首部が,後方から78度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候はほぼ低潮時であった。
A受審人は,自室で休息中,自動操舵装置の警報音を聞き,船窓を通して至近に五輪丸の灯火を認め,急ぎ昇橋して事後の措置に当たった。
また,五輪丸は,C受審人が1人で乗り組み,操業の目的で,船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって,同月13日15時00分香川県庵治漁港を発し,備讃瀬戸の漁場に向かった。
C受審人は,目的地に着いて操業を続け,たいやえびなど約40キログラム漁獲したところで漁場を移動することとし,翌14日00時56分半地蔵埼灯台から323度1.1海里の地点において,針路を大串埼沖灯標に向首する188度に定め,機関を全速力前進にかけ9.0ノットの速力とし,所定の灯火を表示し,船首甲板に前方を向いた姿勢で立ち,漁獲物を選別しながら周囲を見張り,自動操舵により進行した。
01時01分C受審人は,地蔵埼灯台から289度1,500メートルの地点に達し,投網予定地点に向け針路を204度に転じたとき,左舷船首55度1,570メートルのところに,西行中の日之出丸が存在し,その後衝突のおそれがある態勢で接近したが,同船が無灯火の状態であったので,視認することができず,このことに気付かないで続航し,五輪丸は,原針路原速力のまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,日之出丸は,右舷側外板に擦過傷を生じさせ,五輪丸は,左舷船首部外板を破損し,のち修理された。また,C受審人が左耳介挫創などを負った。
(航法の適用)
本件衝突は,夜間,備讃瀬戸東航路において,西行する日之出丸と南下する五輪丸とが互いに衝突のおそれがある態勢で接近して衝突したものであるが,日之出丸が所定の灯火を表示せず,無灯火の状態であったので,定型航法は適用できず,海上衝突予防法の船員の常務で律するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 日之出丸
(1)A受審人が所定の灯火を表示しなかったこと
(2)A受審人が他船を視認したら動静監視を行うよう指示しなかったこと
(3)B指定海難関係人が入直時に灯火を確認する習慣がなかったことから,灯火の表示確認を十分行わなかったこと
(4)動静監視を十分に行わなかったこと
(5)衝突を避けるための措置をとらなかったこと
2 五輪丸
漁獲物を選別しながら,周囲の見張りを行っていたこと
(原因の考察)
本件は,日之出丸が,所定の灯火を表示しておれば,五輪丸が衝突のおそれがある態勢で接近している日之出丸に気付き,避航措置をとり,衝突を回避することが可能であったと認められる。
また,日之出丸が,五輪丸の存在に気付いていたのであるから,動静監視を十分に行い,衝突を避けるための措置をとっておれば,衝突を回避することが可能であった。
したがって,日之出丸が,無灯火の状態で航行したこと及び動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
A受審人が所定の灯火を表示せず,他船を視認したら動静監視を行うよう指示しなかったこと及びB指定海難関係人が所定の灯火の表示確認を行わず,他船を視認した際,動静監視を行わなかったことは,いずれも本件発生の原因となる。
他方,五輪丸が,漁獲物を選別しながら,周囲の見張りを行っていたことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,備讃瀬戸東航路において,日之出丸が,無灯火の状態で航行したばかりか,動静監視不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
日之出丸の運航が適切でなかったのは,船長が,所定の灯火を表示せず,無資格の船橋当直者に対し,他船を視認したら動静監視を行うよう指示しなかったことと,船橋当直者が,所定の灯火の表示確認を行わず,他船を視認した際,動静監視を行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は,夜間,発航操船に当たる場合,無灯火航行とならないよう,所定の灯火を表示すべき注意義務があった。しかるに,同人は,いつも一等航海士が発航操船を行い,同灯火を表示していたことから,所定の灯火を点灯することを失念し,同灯火を表示しなかった職務上の過失により,無灯火の状態で航行して五輪丸との衝突を招き,日之出丸の右舷側外板に擦過傷を生じさせ,五輪丸の左舷船首部外板を破損させ,C受審人が左耳介挫創などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が,夜間,単独の船橋当直に就く際,所定の灯火の表示確認を十分に行わなかったことは,本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては,勧告しないが,入直時に所定の灯火の表示確認を行うことが望まれる。
C受審人の所為は,本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
| (拡大画面:18KB) |
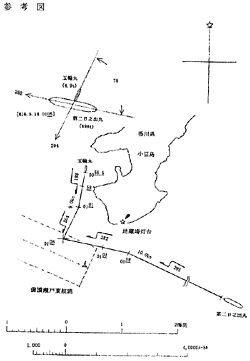
|
|