|
(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年2月12日23時15分
熊野灘
(北緯33度43.6分 東経136度14.9分)
2 船舶の要目等
(1)要目
| 船種船名 |
貨物船第二しんせい |
漁船第七政吉丸 |
| 総トン数 |
413トン |
9.7トン |
| 全長 |
71.23メートル |
17.60メートル |
| 機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
| 出力 |
735キロワット |
463キロワット |
(2)設備及び性能等
ア 第二しんせい
第二しんせい(以下「しんせい」という。)は,平成3年に進水した船尾船橋型の鋼製貨物船で,特に船橋からの見通しを妨げるようなものはなかった。
イ 第七政吉丸
第七政吉丸(以下「政吉丸」という。)は,平成5年に進水したFRP製漁船で,まき網船団の灯船として使われ,船体中央部に操縦室があり,操舵位置からの見通し状況は良好であった。
3 事実の経過
しんせいは,A受審人ほか3人が乗り組み,空倉で,船首1.9メートル船尾3.4メートルの喫水をもって,平成17年2月12日14時20分名古屋港を発し,広島県福山港に向かった。
A受審人は,20時45分単独の船橋当直に就き,法定灯火の表示を確認し,自動操舵によって熊野灘の三木埼東方沖合を南下した。
22時45分A受審人は,鵜殿港南防波堤灯台から079度(真方位,以下同じ。)15.8海里の地点で,針路を230度に定め,機関を全速力前進にかけ,11.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で進行した。
A受審人は,時折,レーダーや双眼鏡を使用して見張りに当たり,23時12分鵜殿港南防波堤灯台から092度11.6海里の地点に達したとき,右舷船首43度1.0海里に政吉丸の灯火を視認できる状況であったが,右舷側や左舷側を北行する船舶に気をとられ,前路の見張りを十分に行っていなかったので,その存在に気付かず,その後,政吉丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが,このことに気付かないまま,速やかに行きあしを停止するなど同船の進路を避けないで続航した。
23時14分A受審人は,右舷船首43度615メートルに接近した政吉丸の紅灯を初めて視認し,前路を左方に横切る小型の船舶と知ったが,小型の船舶が至近に接近してから急に針路を変えることがあるから,どのように避航しようかと考えているうちにも更に接近し,23時15分わずか前機関を停止したものの効なく,23時15分鵜殿港南防波堤灯台から093度11.4海里の地点において,しんせいは,原針路,原速力のまま,その右舷船首に政吉丸の船首が前方から75度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力2の北風が吹き,視界は良好であった。
また,政吉丸は,B受審人ほか1人が乗り組み,操業の目的で,船首0.5メートル船尾2.0メートルの喫水をもって,同日16時三重県長島港を発し,熊野灘の漁場に向かった。
B受審人は,17時00分三木埼の南東沖合で魚群探索を開始し,鵜殿港沖合にかけての水域で探索を続けたが魚群を発見できなかった。
22時48分B受審人は,自船団の他の灯船から魚群発見の連絡を受け,鵜殿港南防波堤灯台から064度6.8海里の地点で,針路を125度に定め,法定の灯火を表示し,機関回転数毎分1,800回転として,14.0ノットの速力でソナーによる魚群探索を続けながら連絡を受けた僚船に向けて手動操舵によって進行した。
23時12分B受審人は,左舷船首32度1.0海里にしんせいのレーダー映像を認めたが,レーダー画面を一瞥(いちべつ)しただけで自船がしんせいの前路を無難に航過するものと思い,肉眼やレーダーを使用するなどしてその動静を監視することなく,ソナー監視を続けた。
その後,しんせいが前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが,B受審人は,このことに気付かず,警告信号を行うことも,更に間近に接近しても行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作もとらないまま続航し,23時15分わずか前至近に迫ったしんせいを視認し,機関を中立としたが効なく,政吉丸は,原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,しんせいは右舷外板に擦過傷を生じ,政吉丸は,船首部を圧壊し,B受審人が左眼窩(がんか)吹き抜け骨折などを負った。
(本件発生に至る事由)
1 しんせい
(1)A受審人が,見張りを十分に行わなかったこと
(2)A受審人が,政吉丸の進路を避けなかったこと
2 政吉丸
(1)B受審人が,動静監視を十分に行わなかったこと
(2)B受審人が,警告信号を行わなかったこと
(3)B受審人が,衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと
(原因の考察)
本件は,A受審人が,見張りを十分に行っていれば,前路を左方に横切る政吉丸の存在に気付き,その進路を避けることによって防止できたものと認められる。
したがって,A受審人が,十分な見張りを行わず,政吉丸の存在に気付かないままその進路を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
一方,B受審人が,レーダーでしんせいを認めたのち,その動静を十分に監視していれば,警告信号を行い,更に間近に接近したとき,衝突を避けるための協力動作をとることによって衝突を防止できたと認められる。
したがって,B受審人が,十分な動静監視を行わず,しんせいが衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず,警告信号を吹鳴せず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,熊野灘において,両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中,南下中のしんせいが,見張り不十分で,前路を左方に横切る政吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが,東行中の政吉丸が,動静監視不十分で,警告信号を行わず,しんせいとの衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,熊野灘を南下する場合,接近する政吉丸を見落とさないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,右舷側や左舷側を北行する船舶に気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,政吉丸に気付かず,その進路を避けないまま進行して政吉丸との衝突を招き,自船の右舷外板に擦過傷を生じ,政吉丸の船首部を圧壊し,B受審人に左眼窩吹き抜け骨折などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号の規定を適用して同人を戒告する。
B受審人は,夜間,熊野灘を東行中,南行するしんせいのレーダー映像を認めた場合,衝突のおそれの有無を判断できるよう,肉眼やレーダーを使用するなどしてその動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,レーダー画面を一瞥しただけで自船がしんせいの前路を無難に航過するものと思い,動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により,しんせいが衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず,警告信号を行うことも衝突を避けるための協力動作もとらないまま進行して同船との衝突を招き,前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
| (拡大画面:12KB) |
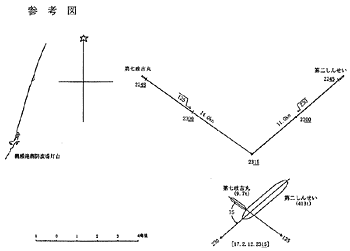
|
|