|
CaseAおよびCaseBの実験により、各水道から入ってくる津波の伝播特性を把握することができた。次に、紀伊水道と豊後水道の両水道から入ってくる津波の影響を評価する。
図5-4(1)〜5-4(10)は、実験CaseCの各地点における津波波高の時間変化を示したものである。紀伊水道における津波の最大高さや到達時間はCaseAの実験結果と同様であり、また豊後水道における津波の振る舞いもCaseBの実験結果と同じである。しかし、瀬戸内海中央部にあたる燧灘では、紀伊水道から入ってくる津波と豊後水道から入ってくる津波が重なり合って波高が高くなっている。
水理模型内で津波実験の状況をみていると、津波は陸地を遡上することなく完全反射している。これは、瀬戸内海大型水理模型の海岸地形はモルタルを使って垂直に作られているからである。津波の第1波目は、この反射の影響は受けず、また数波目ぐらいまでは影響が小さいものと思われる。 図5-5は、CaseCにおける津波第1波目の波高最大値の分布を、 図5-6は、その時の時刻を示したものである。 図5-5の波高最大値の分布をみると、紀伊水道海域で約150〜400cm、大阪湾海域で約50〜95cm、播磨灘海域で約20〜60cm、備讃瀬戸海域で約15cm、燧灘海域で約5〜20cm、広島湾海域で約20〜40cm、伊予灘海域で約20〜30cm、周防灘海域で約20〜50cm、豊後水道海域で約90〜150cmとなっている。
また津波第1波目の波高最大値の時刻は、紀淡海峡、鳴門海峡で1時間後、大阪湾海域で約1〜2時間後、播磨灘海域で1.3〜2.3時間後、備讃瀬戸海域で2.1〜2.8時間後、燧灘海域で2.9〜3.8時間後、広島湾海域で2,9〜3.8時間後、伊予灘海域で1.1〜2.2時間後、周防灘海域で1.3〜3.4時間後、別府湾で1.7時間後、豊予海峡で1.1時間後となっている。
| 図5-4(1) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseC: 紀伊、豊後両水道から津波発生) |
|
(拡大画面:155KB)
|
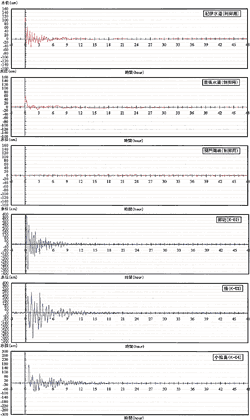 |
| 図5-4(2) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseC: 紀伊、豊後両水道から津波発生) |
|
(拡大画面:174KB)
|
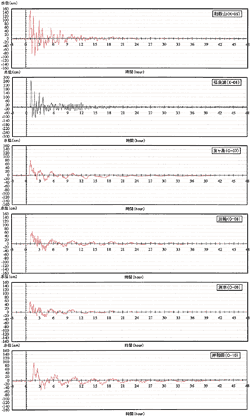 |
| 図5-4(3) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseC: 紀伊、豊後両水道から津波発生) |
|
(拡大画面:176KB)
|
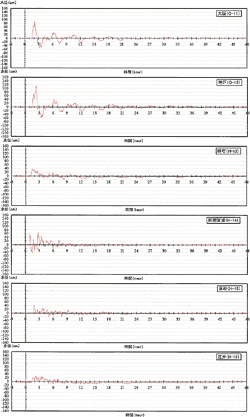 |
| 図5-4(4) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseC: 紀伊、豊後両水道から津波発生) |
|
(拡大画面:139KB)
|
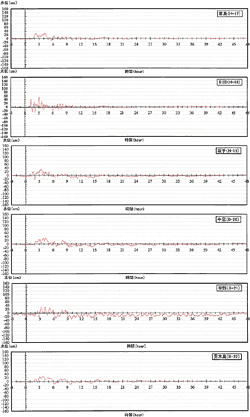 |
| 図5-4(5) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseC: 紀伊、豊後両水道から津波発生) |
|
(拡大画面:136KB)
|
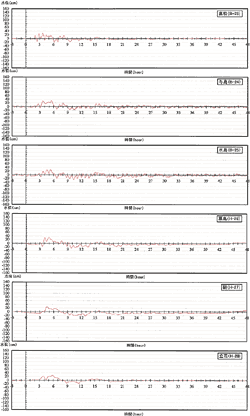 |
|