|
個別支援経過表
I.M.さんの経過
|
(拡大画面:39KB)
|
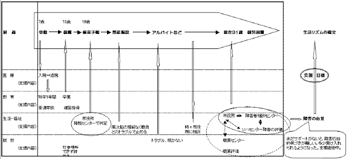 |
★一貫して地域の学校で過ごしてきている。事故後1年のみ障害児学級在籍。その後は普通クラスに戻る。家族も本人も、どういった特徴や弱点があるかを自覚していない。
★就労で失敗して以後、障害について知的に気づくことができた。しかし、具体的内容に関しては、周囲も本人も気付いていない。授産施設や就労先で同じ失敗を繰り返し、辞める。
★家族との生活に飽きてくると、市役所の福祉の窓口に行って、就職先の相談を繰り返す。本人の要求に沿って、そのつど就労先を探すといった単発的な援助の繰り返し。
K.K.さんの経過
|
(拡大画面:36KB)
|
 |
★両親は早い時期に亡くなっており、祖父母との暮らしが続いていた。祖父の入院、祖母の身体的障害があり、介護保険の家事援助で、何とか生活をつないでいた。
★地域療育支援事業施設の、コーディネーターと町の福祉行政窓口の連携で、地域の生活支援施設で援助を受けることができていた。
★支援施設やコーディネーターに高次脳機能障害、中でも遂行機能障害に関する知識がない。適切な支援内容を作成し地域での生活を続けるための評価希望。
K.M.さんの経過
|
(拡大画面:30KB)
|
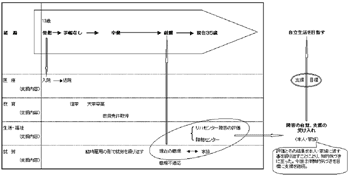 |
★意味的把握と記憶が極端に悪いが、単純記憶の繰り返しと本人の努力で、大学を卒業することができた。教員免許を取得後、産休代替教員も経験している。
★教員免許を持っていることが本人の誇りであり、気持ちの支えでもある。
★一斉横並びの仕事は、比較的うまくこなせるが、一人で作業手順に従ってこなしていくことはほとんど難しい状態であることに、まったく気付いていない。
★いくつもの高次脳機能障害に関する認知テストを繰り返し、本人の障害評価をきちんと返していくことで、自分には記憶を中心とした高次脳機能障害があるということを肯定できるようになった。
H.S.さんの経過
|
(拡大画面:31KB)
|
 |
★受傷前から離婚しており、母親との二人暮らし。退院後は、身体的な障害の後遺症が重く、ほとんど家の中での生活。日常生活は弟の嫁が、母親の分も含めて世話をしてくれている。
★流暢型失語のため、市の福祉担当も周りの家族も、本人の失語については気づかず。
★知的障害者のための通所施設紹介するが、言語でするために、本人にはまったく理解できず。通うことを拒む。それ以後窓口に来ないので放置状態。
★高齢の母親が突然倒れて入院。そのまま死亡。一人住まいになる。
★これまで訪問には中核地域支援センターコーディネーターとも連携して市の窓口に、障相センター・千葉リハと一緒に、今後のことで相談に出かけていた。
★支援施設のショートステイを利用しながら、自宅で一人生活を継続。
A.X.さんの経過
|
(拡大画面:32KB)
|
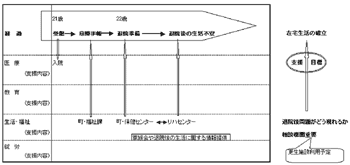 |
★受傷直後、精神的な不穏状況が目立ち、転院を求められた。
★高次脳機能障害回復期のリハビリテーションを含めた医療機関の受入が悪く、家族の不安がたかまる。
★居住地に近い医療機関での受け入れ後、落ち着き、退院を目前にして、周囲に相談する人もないため対応の仕方が分からない。
★居住地の保健センターに相談したところ、香取保健所での当事業の相談窓口があることがホームページに載っており、相談を依頼した。
Y.T.さんの経過
|
(拡大画面:30KB)
|
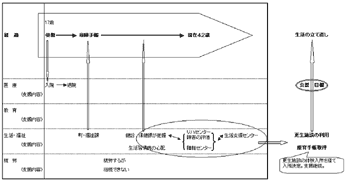 |
|