|
4.3 グループ討論
Group Discussion on New Experimental Techniques and Facilities
田村謙吉(海技研)
「新しい実験技術及び施設」という題名のこのグループ討論は、会議初日の最後に、CFD関連のグループ討論とパラレルで行われた。オランダMARIN理事長であるGeorge Remery氏の司会により、委員会とは異なった和やかな雰囲気の中、3件の発表が行われた。
1件目はMARINのIr. Jan Holtrop氏による半経験的手法による実験結果解析についての紹介であった。同様な解析手法の経験者からは、本手法の有効性についての鋭い質問が出ていた。
2件目はリオデジャネイロCOPPE/UFRJ大のAntonio Carlos Fernandes教授による、現在建設中の深海ピット付きの海洋工学水槽Lab Oceanoの紹介であった。順調に建設が進み、2002年度中に竣工との話であった。パソコンがうまく動かず、動画での説明がないのが残念であったが、水槽紹介のCD-ROMが希望者に配布された。
3件目は田村が、海技研に新設された深海域再現水槽の紹介を行った。特に、円形水槽での造波の動画映像には注目が集まった。司会者から、この水槽を使用して何を研究するのかという質問があり、究極的には新たな資源・エネルギーの開発のための研究だと回答した。また、この水槽を使用してのVortex Induced Vibrationの研究にはどんな計測機器が必要かといった質問も出され、当面、現状の光学的計測の精度を上げることにより対応すると答えた。
Group Discussion on Accuracy of CFD Predictions
児玉良明(海技研)
会議初日の最後のプログラムとして、西日の射す暑い小さな部屋で、熱心な聴衆多数を集めて行われた。先ず、司会のWittekind博士(HSVA)から、ACの見解として、ITTCではこれまでCFDは各委員会で個々に取り上げられ、それだけを総合的に検討する組織は無かったとのコメントが紹介され、次に、現在CFDは流れの把握(波形、流線、圧力分布など)に主に用いられているが、ITTCのprocedureは抵抗値、所所要馬力、最大速力などの値を求めることにむしろ用いられるべきであるとの意見があった。次に、5人のうちの最初のパネリストとしてJensen教授(ハンブルク大)が、ITTCはCFDを評価できるツールを開発すべきであると主張し、従来の見方では誤った結論に導かれるようなCFD計算結果の例を示した。2番目のパネリストのStern教授(アイオワ大)は、CFDワークショップなどにおいて行われる、同一船型に関する多数の計算結果は、実験値(“真値”)のまわりに正規分布をなす傾向があり、CFDコードが類似の問題に適用された場合には統計的手法が適用できる、と主張した。3番目のパネリストのSalvatore博士(INCEAN)は、格子の細分化により、プロペラ翼面上のキャビテーションの発生範囲を良い精度で予測できることを示した。4番目のパネリストのLoukakis教授(アテネ工大)は、実験における状態設定によってCFD計算結果の精度が大きく影響を受けること、CFD計算によって滑走型のボートの抵抗が、低速の排水型状態および高速のブレーニング状態の両方において推定可能であることが示された。5番目のパネリストのJiang博士(デュイスブルグ大)は浅水状態のCFD計算結果を示した。
発表に続いて討論があった。そして司会のWittekind博士により、セッションを締めくくる形で、下記の2つの問題
1 一般的なCFDコードの正確さ、
2 あるCFDコードを用いていくつかの状態を計算した場合の正確さ、
があること、後者の場合には熟練した技術者が必要であること、そして最後に、ITTCはこれらの問題について勧告を出しておらず、第24期のITTCにおいて決める必要があることが示された。
本報告を書くにあたって、概要を提供して頂いた司会者のWittekind博士に感謝いたします。
Group Discussion on Model Manufacturing and Accuracy
右近良孝(海技研)
本年3月にGoeteborgで開催された第23期国際試験水槽会議(ITTC)第3回評議会(Advisory Council : AC)でグループ・ディスカッション(GD)が開催されることとなった。総会への委員会報告書ではまとめて取り上げられなかったことを取り上げようというものである。
このGD(2B)は最近各機関で新しい模型船削成機やプロペラ削成機が導入されていることから、最近の情報交換の意味合いが強いセッションとなった。このGDの担当はACでMurdy(IMD)が指名されたが、部下のRandellがChairmanとなった。発表はHoltrop(Marin)、Gustaffson(SSPA)、J-T. Lee(KRISO)、Benedetti(INCEAN)、Y. Ukon(NMRI)及びRandell(IMD)の6名であった。
HoltroPは97年からのMARINの施設近代化で導入された模型船とプロペラ削成機の機能が向上した点(模型は2日でできる、IGESファイルでCAD/CAM間の受け渡し、模型のNURBS表示)について発表した。Gustaffsonは最近導入されたロボット型の模型船削成機について発表した。Leeは元気な韓国を象徴するように最新鋭の5軸制御の模型船とプロペラそれぞれの削成機及びそのCAD/CAMシステムについて発表した。精度向上と模型作成時間短縮を成し遂げたとの報告であった。Benedettiは3軸と5軸のNC削成機での模型製作と設計のための完全3次元モデル表示技術について長々と発表した。
Ukonはこれらの発表とは全く異なる観点から模型製作精度と試験結果との関係を話題として発表した。海技研は第22、23期ITTCのResistance Committeeの依頼を受けて、KRISOから提供されたコンテナ船模型オフセットデータを用いて模型船を内作し、CFD検証用データを提供すべく船体表面圧力と船尾流場計測を実施し、不確かさ解析も行った。しかしながら、この際両機関の模型船作成方法の違いなどから、模型船の長さが最終的に試験終了時には6mm近く短くなり、変形は船尾付近で大きかったなどの問題が生じた。このため、同一形状の模型を最終的に3隻製作し、寸法計測と水槽試験の繰り返しを行なった。この経過と試験結果の一部について海技研の模型削成機や3次元形状計測装置を紹介しながら発表した。3隻の模型船はそれぞれ異なる方法(メーカー、削成機、NCデータ、材料、塗料など)で製作され、それぞれの模型船について繰り返し試験を行い、今期ITTCのResistance Committeeが作成したスプレッドシートを用いて不確かさ解析の結果について発表した。試験結果に影響を及ぼす要因としては、模型船削成機の精度や製作方法ばかりでなく、線図(NCデータ)表現法、データの受け渡し(互換性)、試験前後、途中での模型船の変形、水槽・時期の違いなどが挙げられる。このうち、模型船のどこの変形が水槽試験結果に影響を与えるかを特定できないと不確かさ解析を含めた適切な精度管理は難しいと主張した。討論では、温度変化による模型船変形の水糟試験結果に及ぼす影響について質問があったが、今回の不確かさ解析での考慮しておらず、局所的影響をどう考慮するかか今後の課題であると回答した。
最後にRandellが自分のところのNC機器を用いた種々の模型削成法と各種市販ソフトウェアとの連動及び削成された模型の製作精度計測法について発表した。これらの発表についてChairmanであるRandellが取りまとめをし、報告書のVol.3に掲載されることになっているが、「言い放しになる」の印象は否めない。
Group Discussion on IMO Standards and ITTC
平野雅祥(三井昭研)
会議2日目の夕方(16:30〜18:00)のプログラムとして本グループ討論が実施された。本年3月開催のAC(Advisory Council)において、今回のITTC総会におけるグループ討論の一候補として「IMO操縦性基準に関する討論」を提案した経緯があり、小職が本グループ討論の企画、司会を仰せつかった。
最近IMOでは、従来の事故統計などの経験則をもとに策定された安全基準に代わり、合理的で広範な種類の船舶に対して適用可能な基準を目指して、「操縦性基準」やRORO旅客船の損傷時復原性に関する「ストックホルム合意」で導入されたような、「性能を直接ベースとした基準(Performance-Based Standards)」策定へと向かう大きな動きがある。性能ベースの基準では、基準満足の証明のために模型実験、数値シミュレーション、或いは実船実験といったTankery Workが大変重要な手段となる。このような動向を背景とし、「IMO基準に対するITTCの役割」を主たるテーマとして本グループ討論が実施された。参加者は約70名を数え、狭い部屋で10数人は立見席であったが、色々な切り口での熱心で活発な多くの議論がなされた。
本グループ討論に関するBriefing(小職)に続いて、まず4名の基調講演者(操縦性分野からはDr. Clarke、 Prof. Kijima、復原性分野からはDr. de Kat、Prof. Vassalos)による各10分程度の講演が行われ、続いて残りの時間を使って会場からの討論がなされた。会場からは操縦性、復原性合わせて計11件もの多くの討論が予定されたが、後述のように討論開始に手間取り、時間的な制約もあり会場からは結局6名の討論になってしまった。残りの討論者には申し訳ないことをしてしまい残念である。
本グループ討論で行われた議論をまとめると、これからの「IMO基準に対するITTCの役割」に関して次の2点に集約されよう。
(1)ITTCはIMOにおけるConsultative Statusの取得に向けて議論を始めるべきである。但し、国連の下部機関としてのIMOに参加するためにはITTCとして固定した事務局が必要となり、この点については可能な方策をIMOと協議する必要がある。
(2)性能ベースの基準に対しては、模型実験、数値シミュレーション、或いは実船実験が重要な役割を演じることとなり、IMO基準を念頭に置いて、ITTCはTankey Workに関する標準的な手法あるいはガイドラインの開発、整備に取り組むべきである。
最後に、小職のBriefingも含め各討論者からはパワーポイントの原稿が前以て事務局宛にE-mailで送付されており、Secretaryからも事前に会場のコンピュータにセットしておくとの返事を貰っていた。これがイタリア的と言えば失礼かもしれないが、討論会場が直前まで決まらず、結局は何の準備もされておらず、CDの新たな読み込みなどでグループ討論開始に15分以上もの無駄な時間を費やしてしまった。
5 ソシアルアクティビティー
児玉良明(海技研)、木下みどり(木下健夫人)(東大)
今回のITTCの会場が世界的な観光地ベニスであり、ソシアルアクティビティーは、これまでのITTCと同様、大変充実していた。
先ずレセプションが、開催日前日の日曜日の夕刻、アルセナーレ(旧海軍造船所)の入り口近くで開かれた、入り口で登録を済ませた後、軽食と飲み物のサービスがあり、旧交を温め合う参加者同士の歓談が和やかに行われた。登録者には2冊のプロシーディングスとQuality Manualの入った頑丈なカバンが手渡された。その重さは合計約10kgもあり、会議終了後、リアルト橋近くの中央郵便局から郵送された方が多かった。
同伴者のためのプログラムも充実しており、下記の4つの半日(HD)ツアーと1つの1日(FD)ツアーが行われた。
| |
HD1
|
:
|
サン・マルコ広場、サン・マルコ聖堂、ドゥカーレ宮殿など(写真2)。
|
| |
HD2
|
:
|
ティチアーノ、ドナテッロの名画を巡る。マイナー・ベニス徒歩ツアー。
|
| |
HD3
|
:
|
べニスの仮面製作の現場訪問。
|
| |
HD4
|
:
|
アルセナーレと船舶史博物館。
|
| |
FD
|
:
|
河口の島々巡り。ベネチアン・グラスのムラノ島、レースのブラノ島、トルチェロ島。
|
HD3ではマスクが家内工業で、しかも手作業で作られていて、若い人が楽しそうに創作しており、FDのムラノ島のガラス工場でも、ちゃんと後継者がいるようで感心させられた。伝統芸術に誇りをもって維持しているという意気込みを強く感じた。団体で訪れたからこそ、詳しい説明を受けたり、実演をやって頂け大変興味深かった。HD4の造船所見学は似たような船の説明が長くて、少々疲れたが、海運で富を築いたヴェネチアの昔を偲ばせるものであった。追加ブログラムのフリーゲート艦「AVIERE」見学がとても興味深かった。甲板から操縦室など、船内を案内してもらい、武器や弾薬などについての説明も受け戦争というものを改めて認識させられた。
|
写真2
|
サン・マルコ広場の鐘楼からサン・サルーテ教会方面を望む
|
澄んだ青空と強い陽射しのもと、日焼けした人々のなかを、ヴェネチアではウォーキングシューズが必需品かなと思うほどよく歩き、一方では時間大丈夫かなと思ってしまうほど、のんびりとしたイタリア流の見学であった。プログラムが当日に内容変更されたり、多少、残念!がっかり!という事もあった。
会議3日目の水曜日に1日ツアーが行われた。観光バス6台を連ねて朝8時に、当初の申し込みをはるかに上回る計300名がベニスを出発した。バスは高速道路を北西に走り、昼前にヴェローナの町に到着し、1時間程度の間、市中心部のアリーナ(ローマ帝国時代の円形闘技場)や、特に日本女性に人気の高いジュリエットの家などを訪れた。その後、再び北西に走り、避暑地で有名なガルダ湖の畔、ワイン産地バルドリーノの町に到着し、ホテルの大広間で昼食をとった。さすがイタリア、延々2時間以上の大昼食会であった。その後、分散して近所の小さなワイナリーを訪問し、ブドウ畑の散策やワイン・テースティングを楽しみ、また湖畔を訪れた。帰着したのは夜9時過ぎであった。
会議5日目の夜8時半から晩餐会が、本土に渡ったところにあるホテル“ラグーナ・パレス”で開かれた。本ITTC組織委員会委員長のGrazioli氏(INCEAN)などの表彰式や、宮廷の衣装を着た出演者によるバロック演奏と踊りがあり、和やか且つ華やかな雰囲気の中で夜が更けていった。
会議6日目は最終日で、議事は午前中で終了し、その日に帰還の途につく方も多かったが、残った方のために、午後に、船でブレンタ河を遡り18世紀の貴族の別荘を巡る半日ツアーが行われた。
6 24期ITTCに向けて
木下 健(東大)
24期の理事会は、次期総会の開催責任者のIncecik(Newcastle大学)がチェアマンを、Clarke(Newcastle大学)がセクレタリーをつとめ、地域代表は23期からアメリカ、東アジア、太平洋諸島の3地域で代表の交替があり、Compton(アメリカ、Webb Institute)、Remery(中央ヨーロッパ、MARIN)、Nielsen(北ヨーロパ、DMI)、Thiery(南ヨーロッパ、d'Essais des Carenes水槽)、Wu(東アジア、CSSRC)、木下(太平洋諸島、東大)の6人である。その他メンバーとして、理事会前チェアマンのGrazioli(INSEAN)、評議会(AC)チェアマンのMurdey(IMD)とセクレタリーのvan Berlekom(SSPA)が加わることになる。24期の技術委員会とグループの名簿を表3に示す。
|
表3
|
Technical Committees and Group of the 24th ITTC
(*: chairman)
|
| (拡大画面:96KB) |
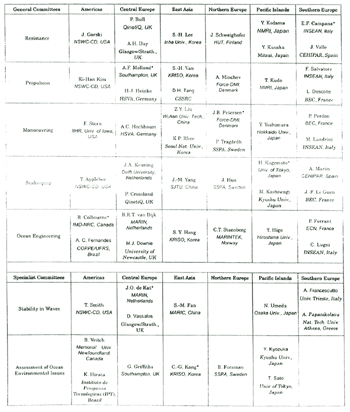 |
| (拡大画面:71KB) |
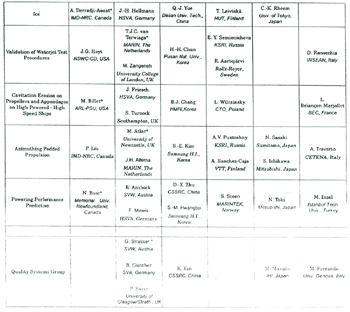 |
|