|
事例報告
(1)長野県の事例
長野県は、「PPKの里」として全国から注目を浴びている11)。「PPK」とは「ピンピンコロリ」の頭文字をとった略語で、「いつまでも元気で生き抜き、病まずに死ぬ」「できる限り元気で生きて、長患いをせずに死ぬ」ことを指すが、長野県がそう表現されるのは、平均寿命が長い、老人医療費が少ない、平均在院日数が短い、在宅介護率が高いなど、元気な高齢者像を示す数値が揃っているからである(表2)。ところで、「PPK」を直接的に示す数値は、平均自立期間割合(平均自立期間÷平均余命×100、つまり「ピンピン」生きていられる期間のパーセンテージ)と考えられるが、平成7年のデータでは、長野県の65歳平均自立期間割合は男女ともに4位となっている。
(2)長野県北御牧村の事例
長野県北御牧村は、平成7年4月に保健・医療・福祉の総合施設ケアポートみまきが開所し、地域医療・福祉事業、健康増進事業を推進してきた。国民健康保険中央会の調査では12)、温泉を有する市町村のうち、平成6年から9年にかけての国保老人医療費減少率がもっとも大きかった村として注目されたが、その後も継続して減少傾向を示している(図2)。本格的な介護予防事業に取り組んだのは平成12年からで、介護予防事業と医療費低減との関連の検討は今後の課題である。また同村では、先に示したように健脚度測定を継続的に実施しており、測定参加者の健脚度の向上傾向も見られている(図3)。さらに長期的な追跡の中で、医療費低減の傾向、および村在住高齢者の移動能力が維持・向上する傾向が見られれば、介護予防の取り組みに一定の成果が得られたと評価することができるであろう。
(3)島根県吉田村の事例
島根県吉田村は、平成6年5月にケアポートよしだが開所し、在宅福祉の充実とともに、早くから介護予防に積極的に取り組んできた。平成7年度より始まったシルバー大学は、自立高齢者を対象に、健脚度測定や運動・生活指導、生きがい活動支援といった教室を継続的に実施している。その結果、教室参加者の健脚度の評価は標準的な集団に比べて高く、また、取り組みに熱心な高齢者においては5年以上経過してもなお、健脚度が維持・向上している傾向も見られる。一方で、前述した健康余命に関する島根県の調査において、平均自立期間、および平均自立期間割合ともに、高い水準のデータを示しており(表3)、介護予防の取り組みを評価しうるデータとなっている。
| (拡大画像:108KB) |
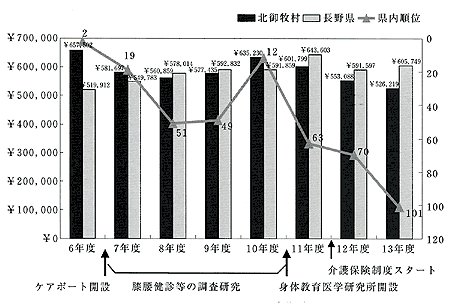 |
図2 北御牧村の国保老人医療費(年間1人当たり)の変化(平成6〜13年度)
図3 北御牧村健脚度測定参加者の10m全力歩行5段階評価分布の年度間比較
(上段:男性 下段:女性)
表3 島根県吉田村の健康余命関連データ
| 年齢 |
項目 |
データ |
| 65歳 |
平均自立期間(年) |
男 :17.92 |
(県平均16.21 2位) |
| 女 :21.66 |
(県平均20.16 2位) |
| 平均自立期間割合(%) |
男 :95.5 |
(県平均92.1 2位) |
| 女 :92.1 |
(県平均88.7 2位) |
| 75歳 |
平均自立期間(年) |
男 :11.26 |
(県平均9.29 1位) |
| 女 :13.05 |
(県平均11.63 1位) |
| 平均自立期間割合(%) |
男 :92.3 |
(県平均92.1 1位) |
| 女 :87.1 |
(県平均81.8 2位) |
| 前掲書6)より |
|
まとめ
高齢化の進展から今後ますます重要となる各自治体による介護予防の取り組みに対し、その成果を評価しうる有用な指標について検討した。
健康余命は、平均余命では反映できなかった地域住民の健康状態を踏まえて算出される。介護保険制度の要介護認定基準によって同質の情報を継続的に得やすくなったことから、今後は各自治体の健康水準を示す指標として活用されるであろう。
老人医療費は、制度改革の影響による変動や、小規模自治体では高額医療者の発生による誤差など、指標として扱う上で考慮すべき点がいくつかあるが、介護予防の取り組みの影響を受けることも十分に考えられ、ひとつの指標として重要である。
健脚度測定は、科学的で、教育的で、効率的な下肢機能評価法であり、介護予防の取り組みにおいて、個々の高齢者の身体機能とその変化を示すことができ、個人、および集団に対して有益な情報を与える。介護予防の成果をあげるには地域高齢者への具体的な働きかけが重要であり、健脚度測定に基づく運動・生活指導によって、個々の運動実践の継続を促すことも可能となる。
介護予防の取り組みは、高齢者の自立を支援することであり、その成果が、要介護高齢者数の低減、老人医療費の低減といった形であらわれる。これらを示す指標は事業展開に重要な示唆を与えるものであり、それぞれの経年変化を複合的にとらえながら追跡することによって、各自治体が取り組む事業成果を的確に分析した知見が、政策への有効なフィードバックとなるであろう。
●附記
本研究は、次の事業助成の一部を受けて行われた。
1)平成13年度太陽生命ひまわり厚生財団助成研究「温水プール・温泉を活用した介護予防・医療費削減に関する政策論的研究」
2)平成14年度日本財団助成事業「ケアポートを核とした元気むらづくり事業」
●参考文献
1)岡田真平, 掛川一郎:北御牧村の介護予防推進計画.身体教育医学研究, 1(1) : 48−55, 2000.
2)健康・体力づくり事業財団編:健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動について), 2000.
3)厚生統計協会編:国民衛生の動向・厚生の指標(臨時増刊), pp67-71, 49(9), 2002.
4)厚生統計協会編:前掲書4), pp422-427.
5)宮下光令, 橋本修二, 尾島俊之ほか:高齢者における要介護者割合と平均自立期間−既存統計にもとづく都道府県別推計−.厚生の指標, 25-29, 46(5), 1999.
6)島根県保健環境科学研究所編:「島根県における健康寿命(平均自立期間)の地域格差に関する研究」報告書, pp2-13, 2002.
7)厚生労働省編:前掲書1)p408, 2002.
8)長野県社会部厚生課編:平成13年度老人医療事業年報, 2002.
9)上岡洋晴, 岡田真平:健脚度の測定・評価. 武藤芳照, 黒柳律雄, 上野勝則, 太田美穂(編), 転倒予防教室第2版, pp89-97, 日本医事新報社, 東京, 2002.
10)岡田真平, 上岡洋晴, 小林佳澄ほか:農村在住高齢者移動能力・バランス能力とその関連事項に関する考察−北御牧村研究−. 身体教育医学研究, 2(1) : 13-20, 2001.
11)水野肇, 青山英康編著:PPKのすすめ, 紀伊国屋書店, 東京, 1998.
12)国民健康保険中央会編:医療・介護保険制度下における温泉の役割や活用方法に関する研究, 2001.
|