|
HRリーダー養成講座最終レポート
レポートタイトル
「数字の書かれていないものさしをいくつもっているか?」
河端啓吾
実習期間 9月10日〜13日 はぐれ雲 10月17日〜20日 いこいの里
10月26日〜30日 はじめ塾 11月2日〜9日 YSC
設定目標・・・実習を通じ各機関の特性、入所者への援助体制のプラス面マイナス面や状況、運営方法などを見る。
実習期間中の注意事項・・・各機関それぞれの規則や特性があるのでそれに従い、臨機応変に動き、郷にいれば郷に従えの精神で行動。
短期間の実習なので自分からアクションを起こすよりも見ること聞く事に重点を置く。
実習を通じて
各機関の入所者のニーズ、現状が多種多様なためその援助方法実践を4つの機関を通じて見ることができたため、私にとって非常に勉強になり実習という表面的な理解度ではあるが、今まで学んできた紙の上や頭で描いていたものを納得するとともに自分への多少の自信に変えることができた。
この実習は短期間ながらも多数の機関を周れたのは私にとって非常に身になるものとなった。
共通する援助システム内容とすれば衣食住の生活リズムの形成であった。人間の生活は衣食住といわれているが、食べること寝ること運動することを整えることが基盤となっていること。その中でも作業(それに類似するもの)はどこの機関でも存在していた。作業は日常スケジュールにおける中心的なものであり、人間の生理的な面で言ったバランスのとれた生活を支える役割を持っていた。その作業の中でちょくちょくグループワークのテクニックという面が見られた。たくさんの人数がいた場合でも狭いスペースを使った方がまとまり具合が良いことや、リーダーとなる人の意欲や態度がもろに作業に現れる、よく「背中を見て育つ」といわれるがいくらベテランのスタッフでも一緒に作業を行わなければならない重要性を感じた。
入所者は本当に4つの機関においてニーズ、状態、それぞれなので一概にはとても言えるものではない。私はこの実習を通じて入所者に対して「この人はどんな人なのだろう?」「どういった状態にあるのであろう?」といった事は考えないようにしてきた。考えたところであの短期間の実習では分かるはずもなく、分かったところでどうしようもない、知ったかぶりになってしまう可能性があったので意識してそれはしないようにした。
しかし各機関それぞれのカラーを感じることはできた。
具体的に例に挙げると、〔はじめ塾〕の場合、入所者は本当にまじめである。良い状態の子ども達をパックにしているという感じを受けたが、これは和田先生の方針上のもので「無理をしないシステム」のためであろう。普通の社会と同じような環境を作り、子どもの自立心を養う〜というものであるから、入所者は各自大人である。印象に残ったのは例会(週に一回入所者スタッフ全員で参加)である。これはなんでも遠慮無しに言い合える、後で恨みっこはなしのような感じで子ども達の手で進められていく、これははじめ塾の一番のカラーとともに伝統となっているのであろう、言いたい事が言える事により、力関係が生じにくく、ストレスを抱え込みにくい。そうしてまわりを考えるようになる。全体的に周りが優秀なため状態の悪い子でも持ち上げられていく〜。その分はじめ塾はスタッフの数は必要ない、ある程度それぞれ同じ方向をむいていた。入所者各自が腹を割って話すことのできる環境設定を作り出す事のできる和田先生の技術に驚かされた。しかし、ただ一つ気になる点とすれば、先に皆ある程度同じ方向を見ているといったが、70年間血族だけで運営してきたためか、多少、考え方に潔癖的な面を持っているように感じた。それを表しているものの一つが食事であった。無農薬な米、野菜、飲料水、肉は食べないといった生理的には健康な食事である。肉を食べないせいか子ども達は年齢的なギラギラしたものを感じず、穏やかな雰囲気である。しかしその分、一般の成長期の子ども達より体がひとまわり小さいように感じた。確かに健康的には違いなく皆それが良いと思い込んでいたが、良し悪しは別にして私はそこに疑問符を抱いた。
もう一つ例にあげたい機関は〔いこいの里〕である。蔵王山にあり他と接触がないせいも手伝って閉鎖的であった。そして建物内の暗さ、そのためか入所者も元気がない、そして何より衛生面での管理の不十分(特に入所者が寝起きする館)そして入所者が心を開ける機会やスタッフがいないようであった。必然的に入所者が各自ストレスを溜め込んでしまっている。当初いこいの里の特徴は他と比べて厳しい規則にあると聞いていたが、その厳しさの内容が私自身個人的に理解に苦しむものであり、厳しいというよりも楽しみを消す規則のように感じた。自由や楽しみをマイナスもしくは悪影響と捉え、それを奪う事により更生していくと考えたものであろうが、自由を奪う事によりそこに上下関係が生まれるという事が今まで実地で学んだ事である。入所者もスタッフ側も上下関係が出来上がっており、そのため他の考えやカラーが入りにくく子どもを評価してしまっていた。そのためお互いに不信関係が出来上がっており悪循環しているように感じるものがあった。いこいの里の問題はそれに気づいていない点にある。やはり全体でしっかりと話しのできる環境を設定する事が重要である事を認識できた。そういった意味でいこいの里は大変勉強になった。
この実習のもう一つの課題は運営面を見る事にあったが、やはり一人の入所者につき高額な月額をもらわなければならないのは現状当然である。ひきこもりのこのような場合には入所は絶対条件の一つである事も分かったので、それは仕方のない事である。しかし金銭的に余裕がない家庭で引きこもりが生じてしまった場合対応する機関はほとんどといって存在しない、バックアップするものがない限り自力での運営は難しいため金銭での課題は直接現場の問題となってしまう。運営面で軌道に乗っているため塾でも金銭面での問題は難題の一つである。金の廻しかたのコツに「平等より公平」という考え方を聞かせてもらった。
全体のまとめ
今回は短期間の実習という事もあり、入所者と積極的に関わるというより見る聞く事を中心に進めていった。しかしそうする事により冷静に聞く事、見る事ができたように思う。
“他者理解”というものが支援者側にも入所者側にも、いや人間の心を考える上で大切な事のように思う。どれだけの数、色、カタチのものさし(尺度)を備えているか?備えられるか?その意味においてタメ塾のスタッフ数の多さは他には無いとても良い要素である。スタッフが多い分さまざまな人のカラーで多くの環境設定ができ、それを利用者がチョイスするという、他の機関には無かったシステムであった。そういったことからスタッフ数というものはとても重要なようその一つであると理解できた。他者理解というのは家庭訪問をはじめとする一連の支援体制にそれが不可欠であり、それをふまえた上での忍耐力、持久力、スピードが必要であり、加えてニーズの違った入所者が時代に伴い入所する事により柔軟さも持たなくてはならないと認識した。
タメ塾には比較的長い時間入れた事と実習のラストという事もあり、総体的なものを感じる事ができた。若いスタッフも悩みながら入所者と関わり、それぞれのスタイルで挑む、人間と人間の関わり合いなのでそれで良いと、肩肘はらなくとも良いと思うようになった。
私個人的な意見になりますが、私はこの業界はこれが正しいとか、間違っているとかそういった答えは出ないと思います。もしあるとしたら答えを決めつけない事でしょうか?そうして相手の価値観考え方性質をどこまで理解できるか?相手のものさしの長さ、カタチのものさしを持つ事ができるか?長さやカタチはともかく、せめて色だけでも合わせようと努力することが大切なように思います。これはいくらベテランの人でも忘れてしまう事や見失ってしまい、ものさしにメモリが付いてしまう場合が有り得るのでそこのところを気を付けないと、他者理解が他者誤解に変わってしまう可能性があると感じます。
| (拡大画像:90KB) |
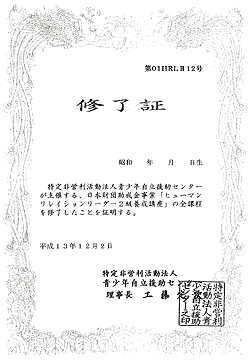 |
平成13年度日本財団助成金事業
NPO法人青少年自立援助センター
不登校児自信回復に係わるメンタルフレンド育成講座
|