|
II
サン・ファン・バウティスタと木の文化
海につどい船に学び、木の文化を知る 2002
サン・ファン・バウティスタと木の文化
東北工業大学教授 柴崎 徹
気候上、樹木環境に恵まれた日本は、豊かな木の文化を築いてきた。私たちの家はもちろんのこと、家具も什器も農具も漁具も、紙や本も、それらを作り出す道具も、衣食住のあらゆる場面に木の文化が息づいている。
木は私たち人間同様、「齢」を重ねて形成される素材である。毎年毎年外側に向かって「齢」を重ねていくので、木は年ごとに高くなり太くなる。その「齢」は人間を凌ぐものが大半で、時には数百年数千年に達するものもある。条件のよい森の中にはこうして形成された巨木が点在する。私たち人間の背丈はせいぜい2メートルだが、木の場合には少なくとも一桁上の高さにまで伸びる。これが高床式住居に始まる私たちの住空間の高度化を誘導し、さらに高い建造物をつくり出していく要因である。
特に、神社や仏閣・仏塔などのように象徴的性格から高さや大きさを具備する必要のある場合には、巨大な木をその柱や梁として用いねばならなかった。これまで知られる最も高さのある建造物は、一つは古代出雲大社でその高さは48メートルと推定されている。現存するものでは東大寺の大仏殿だが、これは高さが52メートルある。この建物は宝永6年(1709)に再建されたものだが、創建当時(勝宝4年・752)とほぼ同じ高さだとされている。また塔では、現存する最古の塔、法隆寺五重塔が34.10メートル、現存する最高の塔、東寺五重塔が54.84メートルである。何れにしても古代の巨大建造物は、巨木の存在とそれを組み上げる技術によって獲得されたものであった。
木の素材としての特徴は、(1)丈夫なこと、特に木理に平行する方向に強いこと。(2)柔らかいこと。(3)軽いこと。(4)弾力性があること。(5)吸湿性があること。(6)断熱性があること。そして、(7)加工が用意であること。などが挙げられる。このような素材としてのすぐれた性質から木は多方面に用いられてきたが、その木に対しての利用手段とそこから生じる用途や製品の関係を示すと表1のようになる。
表1 木(幹)の利用手段と用途など
| (拡大画面:314KB) |
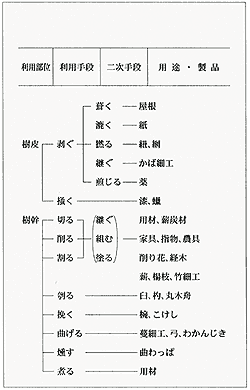 |
特に石材やレンガ材など、木以外の他の素材では得られない利用手段に、「剥ぐ」「掻く」そして「挽く」「曲げる」「燻す」「煮る」があり、それによって得られる製品は木独特のものである。東北地方の木の文化を形づくるものに、こけし、漆器、かば細工、桐細工、桐家具、曲わっぱ、わかんじきなどが挙げられるが、これらはどれも木独特の性質によっている。
これらのさまざまな利用手段を多用しながら組み上げていく構造物が建物、橋、そして船であろう。建物や橋は土台の上に組み上げられていく構造物で垂直に立てた柱と水平にした梁や桁の軸材が基本になっている。これに対して船はそれ自体独立した浮上構造物で、水による抵抗を少なくし水圧に耐えるよう曲線が基本である。そして利用手段の多用さから見ると、船は建物や橋よりさらに多用である。この傾向は船が大型になればさらに増す。そのように見ると、「木造船は木の文化の集大成」と言えると思う。
本年は、サン・ファン・バウティスタの復元船が完工してからちょうど10周年にあたる。サン・ファン・バウティスタは、慶長18年、仙台藩主伊達政宗が藩士支倉常長を使者としてローマに派遣する時、太平洋横断のために建造させた帆船である。サン・ファン・バウティスタ(Sant Juan Bautista)とは、聖ヨハネ・バブティスト、すなわちイエスに洗礼を授けたバブテスマのヨハネという意味で、この船の建造に携わったスペイン人ビスカイノらが、政宗に初めて謁見した日が、ちょうど聖ヨハネの祭日だったから、それを記念して命名されたと言われている。サン・ファン・バウティスタによる太平洋横断は1613年のことであるから、幕末の萬延元年(1860)、オランダから購入した洋式軍艦・成臨丸による太平洋横断(日本人のみ操船)に先立つこと250年前のことであった。
サン・ファン・バウティスタ復元船を見て私たちが驚くのは、その大きさと船の形の異様さである。もちろんそれは、木で造られた建造物としての大きさへの驚きであり、それでいながら見事な曲線を持つマッシィブヘの驚きである。もしも、一杯に帆を張って大海原を進むサン・ファン・バウティスタを眺めたならば、その驚きはさらに増幅するに違いない。この船には、私たち現代の人間が忘れ去ろうとしている、木の構造物を介した大自然への飽くなき挑戦が読み取れると思う。木に託した挑戦である。
復元船は「伊達治家記録」の記事に基づいて原寸大で造られた。とは言っても、十分でない資料から復元船まで設計するのには並大抵でない関係者の努力があった。こうして全長55.35メートル、垂線間長(船の吃水線長)34.28メートル、竜骨長(船底にある船の基礎部位の長さ)26.06メートル、最大幅11.25メートル、型幅10.91メートル、深さ(竜骨底から舷側位置までの高さ)4.55メートル、吃水約3.80メートル、高さ(竜骨底からメインマスト上先端までの高さ)48.80メートル、そしてメインマスト32.43メートル、フォアマスト18.19メートル、平成の帆船が復元されたのである。総トン数は約500トンである。
江戸時代に日本周辺の近海で活躍した一枚帆で走る千石船(ベザイ船)の大きさが、船長18メートル前後、帆柱の高さが15メートルぐらい、明治18年に造られた最大級の木造船と言われる小管丸が149トンであったことと比較すると、いかに大きな船であったかが分かる。
船の場合、建物や橋と違って重量はすべて浮力によって支えなければならない。水の中に新たな空間をつくり出し、排水した分の浮力を得る構造である。周囲からの水圧に耐え、風波の強い悪条件下でも安定した船位を保つことのできる構造でなければならない。木造帆船の場合、高く帆を張るので強度を確保する構造はさらに吟味が必要になる。木は収縮するので合わせ目の水漏れよけの技術も必要になる。つまり、船が大きくなればなるほど、すぐれた材料と組み上げる高度な技術が求められることになる。先に「木造船は木の文化の集大成」と言ったのは、そういう意味である。
サン・ファン・バウティスタ復元船の(1)構造にかかわる部材(2)外壁・甲板にかかわる部材(3)帆柱および操船にかかわる部材(4)その他−に分けて、その材質を外観すると表2のようになる。
表2 サン・ファン・バウティスタ復元船の部材と材質の概要
| (拡大画面:47KB) |
 |
ここには、船底の基礎にあたる竜骨やその上に立ち上がる骨格の肋骨材、外圧を支える梁材などの構造材にはマツが、それらの部材の継ぎ材になる曲材にはケヤキが、外壁・甲板にはスギが、マストやヤードには米マツとスギが用いられたことが示されている。何れにしても、米マツを除けば、マツとスギとケヤキが主たる材料になっている。
このうち、曲げ・圧縮・せん断に対する強度は何れもケヤキが一番高い。しかし、比重は3者の中で一番重い。スギは各強度がケヤキの6割前後であるが、材としては一番軽い。マツはこの両者のほぼ中間の材として知られ、強度も結構強いし比重もケヤキより軽い。ただしマツには耐朽性が少し劣るという欠点がある。マツが構造材として多量に使われ、最も強度を必要とする部分にケヤキが使われているのはそのためである。位置によって本一本異なった彎曲を持つ肋骨材などには、自然に彎曲したたくさんのマツ材から合致する適当な材を選んで組み立て、さらに「鉤形継ぎ手」という堅牢な方法で継いで強度を損なわないようにしている。
外板や縦通材として使われているスギは、材質が比較的柔らかいので、板にすると釜で適度に蒸して肋骨に合わせた曲げ板を得ることができるが、今回は材が大型なので特製の蒸し釜が用いられている。
外板で一番問題になるのは水漏れ防止策だが、復元船のように大型になると、小型の和船で使われてきた接合面を叩いて柔らかくして合わせる「木ごろし」や鋸で両者の接合面を挽く「すり合わせ」などの方法では間に合わないので、ヒノキの皮の埋木を外板の間に埋め込む「巻ハダ」の技法が採られている。
「伊達の黒船物語」の中には、これらの材の調達についても詳しく記載されているが、マツは4千本が志津川、鮎川、気仙沼、登米などから、スギは樹齢80〜100年のものも含めて千3百本が地元桃浦から、そしてケヤキは30本が岩手県釜石あたりから、ホオノキは気仙沼から調達されている。これに竜骨材やマストなどに使われた米マツが加わるから一隻の木造帆船を復元するために結集された木材は厖大なものであった。
サン・ファン・バウティスタ復元船を眺めると、その巨大さと威容さに驚かされるが、中に入ると今度はその構造の堅牢さと見事さにさらに驚かされる。そこには多様な木の素材が多様な利用手段のもとに多様な集合技術を駆使している姿が読み取れるのである。和船の時代にあって和船を跳び越え、まだ近海航海の時代にあって独り太平洋を横断していったサン・ファン・バウティスタには、日本の和船の技術と西洋帆船の歴史が同時に息づいている。それは異質の文化が木の文化の共通性を介して辿り着いた一つの大きな成果と言えるであろう。そしてその具体的な作業が私たちのすぐ傍でなされたことも驚きである。復元船はそのことをもう一度私たちに教えてくれている。
〈参考文献〉
「伊達の黒船物語」
財団法人慶長遣欧使節船協会 (平成12年)
「甦った慶長遣欧使節船」
跡部進一「イリューム第12号」 (平成6年)
「改訂船体各部名称図」池田 勝 (昭和54年)
|